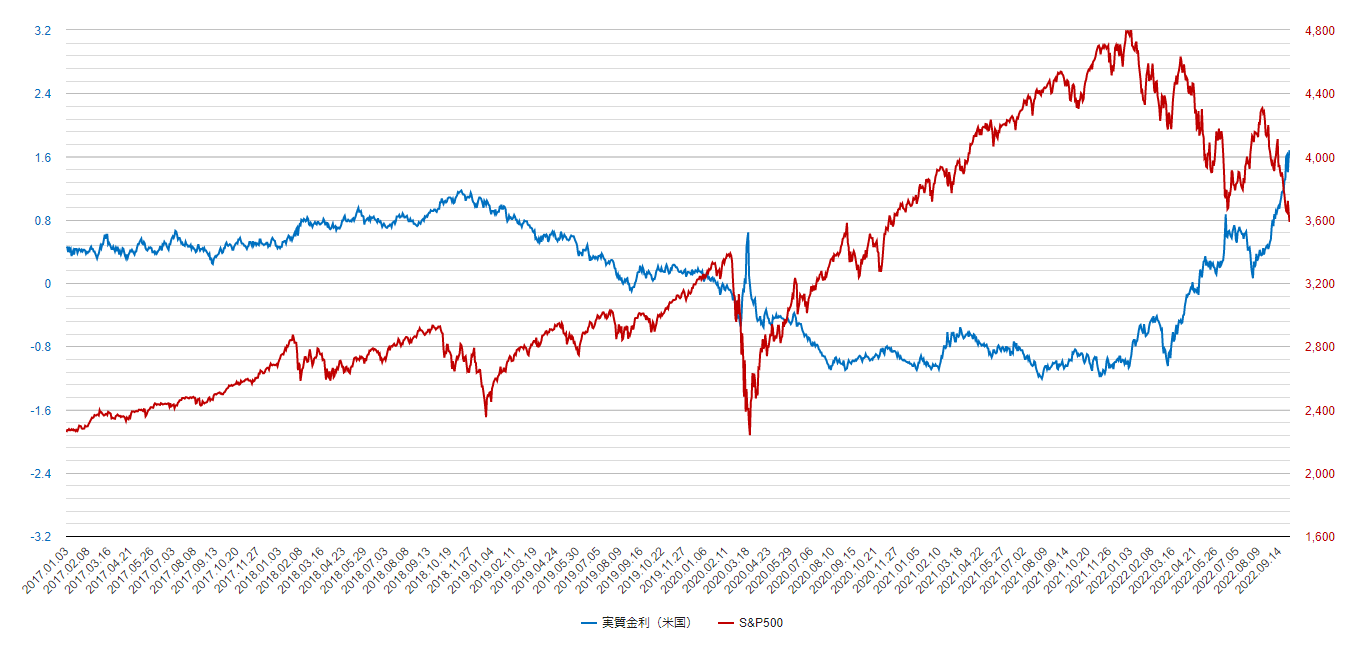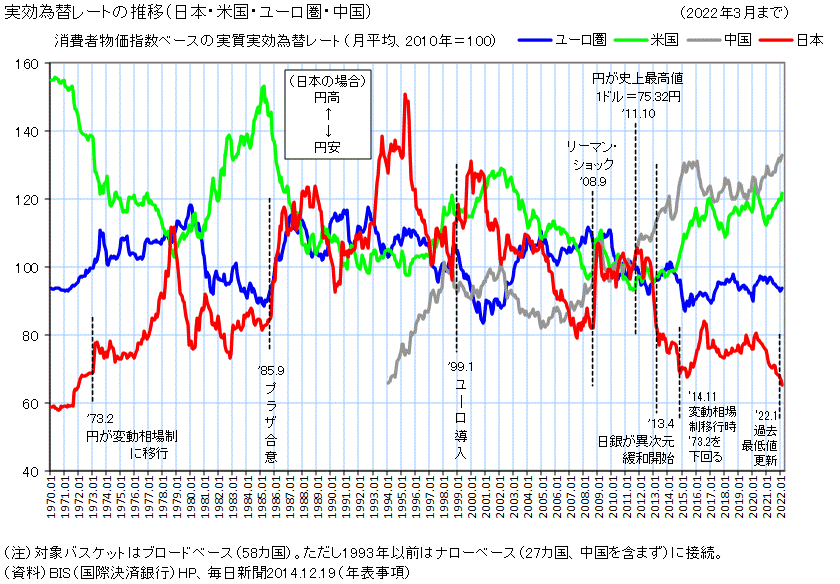Blogブログ
2026.01.12
タコが上げたマーケット
2025年の株式市場は日米ともに急激な上昇となりました。トランプ政権は4月、全輸入品に10%の関税を課し加えて国別に税率を上乗せ。通常このような政策は世界の景気後退を招くので株価下落になりこそすれ、上昇することは無いはずです。実際、発表後の株価は大幅に下落しパニック売りを招き一日の下げ幅は歴代3位となりました。しかしその3日後には急激に上昇し歴代2位の上昇をみせました。
かくも激しい変動の理由は、あまりの株価下落に驚いた大統領が関税の 90 日間の一時停止を発表したからです。この事態の対処には財務長官ベッセント氏の影響が大きか ったと伝えられています。
トランプ大統領は世界を驚かすような政策を打ち出しますが、反応が大き過ぎるとすぐにひっこめるということで、TACO(Trump always chickens out トランプはいつでもビビってやめるとファイナンシャル・タイムスのコラムニストに揶揄されています。しかしなんと言われようと、あそこで急激な方向転換をしていなかったら昨年の株式市場は惨憺たる状況になっていたことは想像に難くありません
その後、一時 125%まで引き上げられた中国への関税も10%に変更されました。報復関税の応酬を経て11月に中国の打ち出したレアアース輸出規制にビビッて再び TACO が出たからですが、結果として世界経済の安定は保たれ株価も上昇しました。
トランプ政権が相互関税を導入したのは米国の貿易赤字への対策としてです。赤字額が増加の一途をたどっていたのでこれは国家の「非常事態」であると認定した訳です。米国憲法上関税を決定する権限があるのは議会であり、議会が 1977 年に制定した IEEPA(国際緊急経済権限法)によれば大統領が「国家非常事態」を宣言した場合に、同法に基づく経済措置を発動できることになっています。しかしそもそも貿易赤字拡大は「国家非常事態」なのでしょうか
大統領の権限等についての司法判断は米国連邦最高裁判所によってなされることになっています。下級裁判所の判断と異なり最終判断となるので政権敗訴となれば支払われた関税の還付が必要となります。これは米国財政に大きな影響を及ぼし株価への影響も避けられないと思われます。26 年の株式市場への大きな不安要因となりそうです。
かくも激しい変動の理由は、あまりの株価下落に驚いた大統領が関税の 90 日間の一時停止を発表したからです。この事態の対処には財務長官ベッセント氏の影響が大きか ったと伝えられています。
トランプ大統領は世界を驚かすような政策を打ち出しますが、反応が大き過ぎるとすぐにひっこめるということで、TACO(Trump always chickens out トランプはいつでもビビってやめるとファイナンシャル・タイムスのコラムニストに揶揄されています。しかしなんと言われようと、あそこで急激な方向転換をしていなかったら昨年の株式市場は惨憺たる状況になっていたことは想像に難くありません
その後、一時 125%まで引き上げられた中国への関税も10%に変更されました。報復関税の応酬を経て11月に中国の打ち出したレアアース輸出規制にビビッて再び TACO が出たからですが、結果として世界経済の安定は保たれ株価も上昇しました。
トランプ政権が相互関税を導入したのは米国の貿易赤字への対策としてです。赤字額が増加の一途をたどっていたのでこれは国家の「非常事態」であると認定した訳です。米国憲法上関税を決定する権限があるのは議会であり、議会が 1977 年に制定した IEEPA(国際緊急経済権限法)によれば大統領が「国家非常事態」を宣言した場合に、同法に基づく経済措置を発動できることになっています。しかしそもそも貿易赤字拡大は「国家非常事態」なのでしょうか
大統領の権限等についての司法判断は米国連邦最高裁判所によってなされることになっています。下級裁判所の判断と異なり最終判断となるので政権敗訴となれば支払われた関税の還付が必要となります。これは米国財政に大きな影響を及ぼし株価への影響も避けられないと思われます。26 年の株式市場への大きな不安要因となりそうです。
2025.07.03
驚きのマカオ
まもなく参院選が始まります。各党の論点の中心は給付金。これを消費税で行うか、定額給付で行うかということであります。インフレで生活が圧迫されているので、国民の一番の関心事は政治がこの問題にどのように向き合ってくれるのかということになります。
今後インフレが年々高まっていくなら、できるだけ効果の高い生活支援対策を講じてほしい。そうした多数の願望に答えて国民の評価を勝ち取るかが争点と考えているのでしょう。その対策の1つとして消費税率の引き下げが各党から出ています。
この主張の問題点は財源です。我が国の債務残高はGDP比2.5倍に達しており支出の多くを国債発行に依存しています。
過度の国債依存は金利の上昇を招きますが、それは日本や国民の重大な損失につながります。金利の急激な上昇がいつ起きるか誰にも判らないところに問題の恐ろしさがあります。
短期的にはそんなことは起きないだろうということで、赤字国債はここまで膨張してきました。確かに今までのところ何も起きていません。今回も大丈夫だろうということで、候補者は国民の期待に寄り添った政策を打ち出して国会の議席を狙いにゆきます。しかし、これにより財政破綻が現実のものとなった時、ワリを食うのは国民です。国会の椅子を勝ち取った議員は国民の支持を得て実行しただけなので責任を問われることはありません。
世界を見渡すとこうした不安とは無縁の場所があります。例えばマカオ。この国(特別行政区)において消費税は0です。何を買おうが、食べようが、どんな高級なホテルに宿泊しようが消費税が課されることはありません。旅行者だけでなく、住民も同様。さらに住民は医療費(12歳以下と65歳以上)や学費(幼稚園から高校までの15年)も無料という住みやすさです。
これを可能ならしめているのがカジノを含むIR(統合型リゾート)からの収入です。カジノ総収入の35%が税金として徴収され、それがマカオ政府歳入の80%をしめています。これにより社会インフラ、社会福祉向上(教育、医療、住民への給付)が実現されています。
国民の負担を軽減し、同時に国の財源不足の心配をも払拭するということが見事に実現されています。国民や企業から徴収する税金をもって足らざるところを埋めるということだけをやっている限り、国も国民も不安から逃れることはできません。
国や自治体は、いかにして独自収益を確保するのかという方向に頭を切り替えるべきではないでしょうか。マカオのIRは大いに参考になると思います。
今後インフレが年々高まっていくなら、できるだけ効果の高い生活支援対策を講じてほしい。そうした多数の願望に答えて国民の評価を勝ち取るかが争点と考えているのでしょう。その対策の1つとして消費税率の引き下げが各党から出ています。
この主張の問題点は財源です。我が国の債務残高はGDP比2.5倍に達しており支出の多くを国債発行に依存しています。
過度の国債依存は金利の上昇を招きますが、それは日本や国民の重大な損失につながります。金利の急激な上昇がいつ起きるか誰にも判らないところに問題の恐ろしさがあります。
短期的にはそんなことは起きないだろうということで、赤字国債はここまで膨張してきました。確かに今までのところ何も起きていません。今回も大丈夫だろうということで、候補者は国民の期待に寄り添った政策を打ち出して国会の議席を狙いにゆきます。しかし、これにより財政破綻が現実のものとなった時、ワリを食うのは国民です。国会の椅子を勝ち取った議員は国民の支持を得て実行しただけなので責任を問われることはありません。
世界を見渡すとこうした不安とは無縁の場所があります。例えばマカオ。この国(特別行政区)において消費税は0です。何を買おうが、食べようが、どんな高級なホテルに宿泊しようが消費税が課されることはありません。旅行者だけでなく、住民も同様。さらに住民は医療費(12歳以下と65歳以上)や学費(幼稚園から高校までの15年)も無料という住みやすさです。
これを可能ならしめているのがカジノを含むIR(統合型リゾート)からの収入です。カジノ総収入の35%が税金として徴収され、それがマカオ政府歳入の80%をしめています。これにより社会インフラ、社会福祉向上(教育、医療、住民への給付)が実現されています。
国民の負担を軽減し、同時に国の財源不足の心配をも払拭するということが見事に実現されています。国民や企業から徴収する税金をもって足らざるところを埋めるということだけをやっている限り、国も国民も不安から逃れることはできません。
国や自治体は、いかにして独自収益を確保するのかという方向に頭を切り替えるべきではないでしょうか。マカオのIRは大いに参考になると思います。
2025.03.16
お化け屋敷の恐怖
お化け屋敷が怖いのはいつ、どんなお化けが、何処で出てくるのか判らないことです。さらに出口がどこにあるのか予測出来ないという恐怖も加わります。
最近の株式市場はお化け屋敷内の如し。トランプ氏が何を言うのか予測がつかず、発言内容が分かってもそれがどのように経済に影響を及ぼすのか判然としません。投資においては経済データや一国の政策が及ぼす影響を咀嚼しながら何を、いつ、どのくらい売買するかを決めるものですが、お化け屋敷市場ではそうした努力が徒労に終わるのでボラティリティー(価格変動の大きさ)が上昇することになります。
市場参加者がどのくらい恐怖にかられているのかを指数で示したものに恐怖とどん欲指数(Fear and Greed index CNN算出)があります。この指数は極度のどん欲(75~100)から極度の恐怖(0~25)まで貿易、財政の赤字25刻み5分割で示されています。ちなみに2月19日の数値は47で「中立」(neutral)を示していましたが2月26日には21の「極度の恐怖」(extreme fear)の状態に突入し、その後本日に至るまで「極度の恐怖」状況が続いています。
このような状況下、市場の動向予測はトランプ政権の発するシグナルの背景を考察することしかありません。その背景は貿易赤字と財政赤字をどのように黒字化するのかということであるように思えます。そのこと自体は一国にとって重要であり正面から取り組むべき課題です。
輸入品目に関税をかけ過剰な輸入を抑え込もうとしているのは貿易赤字を抑え込むためでしょう。また関税収入を増やすことは膨大な財政赤字を抑え込む助けにもなるというわけです。マスク氏が主導するDOGEは過剰な財政支出にメス(ナタ?)を入れ財政赤字を縮小させることが出来ると期待されてのものです。しかし今や36兆ドルにものぼる公的債務や2兆ドル近い財政赤字をこれら政策組み合わせで解決出来るでしょうか。効果より国家、国民に与える痛みが勝るのではないでしょうか。
先の第一次トランプ政権時(2017.1株式~2021.1)採られた政策は減税と財政支出の組み合わせでした。当時はこれ等が功を奏して株式市場は上昇しました。しかし今回と前回では経済社会状況が全く異なっています。一番の違いは一次と二次トランプ政権の間に起きたパンデミックによる経済社会変化です。
この時期コロナ禍対策として余儀なくされた財政支出により財政赤字は大幅に悪化。供給制約等から物価が急上昇、FRBは連続的利上げで臨みました。結果、パニックは収まりましたが副作用として過剰なマネーが市場に流れ込み株価がバブル的に押し上げられました。
このように異なる経済的背景下、関税政策を進めることは米国国内物価を押し上げインフレを助長するだけでなく景気後退を誘発することになります。また、さらに減税を行うとなれば財政支出の増大は避けられません。
トランプ政権が採用している政策と手法はスタグフレーション(景気後退とインフレの共存)に向かってしまう極めて危険な賭けのように思われます。お化け屋敷は遊園地の中だけに留めてほしいものです。
最近の株式市場はお化け屋敷内の如し。トランプ氏が何を言うのか予測がつかず、発言内容が分かってもそれがどのように経済に影響を及ぼすのか判然としません。投資においては経済データや一国の政策が及ぼす影響を咀嚼しながら何を、いつ、どのくらい売買するかを決めるものですが、お化け屋敷市場ではそうした努力が徒労に終わるのでボラティリティー(価格変動の大きさ)が上昇することになります。
市場参加者がどのくらい恐怖にかられているのかを指数で示したものに恐怖とどん欲指数(Fear and Greed index CNN算出)があります。この指数は極度のどん欲(75~100)から極度の恐怖(0~25)まで貿易、財政の赤字25刻み5分割で示されています。ちなみに2月19日の数値は47で「中立」(neutral)を示していましたが2月26日には21の「極度の恐怖」(extreme fear)の状態に突入し、その後本日に至るまで「極度の恐怖」状況が続いています。
このような状況下、市場の動向予測はトランプ政権の発するシグナルの背景を考察することしかありません。その背景は貿易赤字と財政赤字をどのように黒字化するのかということであるように思えます。そのこと自体は一国にとって重要であり正面から取り組むべき課題です。
輸入品目に関税をかけ過剰な輸入を抑え込もうとしているのは貿易赤字を抑え込むためでしょう。また関税収入を増やすことは膨大な財政赤字を抑え込む助けにもなるというわけです。マスク氏が主導するDOGEは過剰な財政支出にメス(ナタ?)を入れ財政赤字を縮小させることが出来ると期待されてのものです。しかし今や36兆ドルにものぼる公的債務や2兆ドル近い財政赤字をこれら政策組み合わせで解決出来るでしょうか。効果より国家、国民に与える痛みが勝るのではないでしょうか。
先の第一次トランプ政権時(2017.1株式~2021.1)採られた政策は減税と財政支出の組み合わせでした。当時はこれ等が功を奏して株式市場は上昇しました。しかし今回と前回では経済社会状況が全く異なっています。一番の違いは一次と二次トランプ政権の間に起きたパンデミックによる経済社会変化です。
この時期コロナ禍対策として余儀なくされた財政支出により財政赤字は大幅に悪化。供給制約等から物価が急上昇、FRBは連続的利上げで臨みました。結果、パニックは収まりましたが副作用として過剰なマネーが市場に流れ込み株価がバブル的に押し上げられました。
このように異なる経済的背景下、関税政策を進めることは米国国内物価を押し上げインフレを助長するだけでなく景気後退を誘発することになります。また、さらに減税を行うとなれば財政支出の増大は避けられません。
トランプ政権が採用している政策と手法はスタグフレーション(景気後退とインフレの共存)に向かってしまう極めて危険な賭けのように思われます。お化け屋敷は遊園地の中だけに留めてほしいものです。
2025.01.13
会社立ち上げの理由
2024年新NISAが始まり、日本人の投資行動が変わりはじめました。
昨年1年間、株や投資信託に個人が投資した金額は1~11月で約12兆円と報じられています。売却益や配当に大判振舞の税制が導入されたのが理由と思われます。
不思議なことにアベノミクスが始まった13~14年ではほぼ同額、12兆円の売り越しとなっています。アベノミクスは三本の矢によって日本の経済に刺激を与えデフレからの脱却を目指した政策でした。結果として政策は効果を表し株価は大きく上昇するきっかけとなったにもかかわらず、個人は大幅に売り越しました
バブル崩壊以降、株式投資といえば損失という体験が染みついてしまった日本人は少しでも回復したら売って損失を抑えようとしたのかもしれません。しかし同時期(13~14年)外人投資家は16兆円を買い越しています。海外勢はアベノミクスの政策によって日本は成長を遂げるはずと考え積極的に買いに入ったということでしょう。
これは自慢ですが、わがβコンサルティング(株)も2013年に会社設立、法人として株式市場に参入しました。外国勢同様、チャンス到来と判断したからです。判断の理由は3本の矢がGDPの主たる構成要素の個人消費、企業、財政投資、貿易収支に有効に働きかけるはずと考えたからでした。(詳細はHPブログの2015.2.9 「潮目の変化の読み方」をご覧ください)
次期米財務長官に任命されたスコット・ベッセント氏はヘッジファンドのCEOですが、トランプ政権にウオール街の見識を持ち込むことを期待されて就任することになりました。氏は元安倍首相の三本の矢に倣った経済政策をトランプ氏に助言したと報じられています。(ウオールストリート・ジャーナル)また2013年には三本の矢政策をみて日本市場に参入し大きく儲けたと語っています。
本年2025年はいよいよトランプ政権が始動します。1月20日の正式開始に先駆けて様々な言動が世の中を騒がせています。米国の政策は日本一国のそれとは比較にならないほど大きなインパクトを世界に与えます。打ち出す政策がどのような影響を与えるのか、これまで以上にしっかりと目を見据えていく必要がありそうです。
昨年1年間、株や投資信託に個人が投資した金額は1~11月で約12兆円と報じられています。売却益や配当に大判振舞の税制が導入されたのが理由と思われます。
不思議なことにアベノミクスが始まった13~14年ではほぼ同額、12兆円の売り越しとなっています。アベノミクスは三本の矢によって日本の経済に刺激を与えデフレからの脱却を目指した政策でした。結果として政策は効果を表し株価は大きく上昇するきっかけとなったにもかかわらず、個人は大幅に売り越しました
バブル崩壊以降、株式投資といえば損失という体験が染みついてしまった日本人は少しでも回復したら売って損失を抑えようとしたのかもしれません。しかし同時期(13~14年)外人投資家は16兆円を買い越しています。海外勢はアベノミクスの政策によって日本は成長を遂げるはずと考え積極的に買いに入ったということでしょう。
これは自慢ですが、わがβコンサルティング(株)も2013年に会社設立、法人として株式市場に参入しました。外国勢同様、チャンス到来と判断したからです。判断の理由は3本の矢がGDPの主たる構成要素の個人消費、企業、財政投資、貿易収支に有効に働きかけるはずと考えたからでした。(詳細はHPブログの2015.2.9 「潮目の変化の読み方」をご覧ください)
次期米財務長官に任命されたスコット・ベッセント氏はヘッジファンドのCEOですが、トランプ政権にウオール街の見識を持ち込むことを期待されて就任することになりました。氏は元安倍首相の三本の矢に倣った経済政策をトランプ氏に助言したと報じられています。(ウオールストリート・ジャーナル)また2013年には三本の矢政策をみて日本市場に参入し大きく儲けたと語っています。
本年2025年はいよいよトランプ政権が始動します。1月20日の正式開始に先駆けて様々な言動が世の中を騒がせています。米国の政策は日本一国のそれとは比較にならないほど大きなインパクトを世界に与えます。打ち出す政策がどのような影響を与えるのか、これまで以上にしっかりと目を見据えていく必要がありそうです。
2024.11.25
持続的な悲惨ゴールに向かう世界
米国大統領選挙後、株式市場は勢いよく上昇しましたが長くは続かず下落から横ばいが続いています。原因は米国債の利回りの上昇。トランプ氏の施策が実現のものとなりつつあることで、市場はインフレリスクを警戒しており、これが債券利回りを押し上げています。
トランプ氏が選挙中から主張していた減税、関税引き上げ、移民抑制策はすべからくインフレにつながるもの。米国財政は悪化の一途をたどっているのに、今後さらに国債を発行することになれば利回りが上昇するのは自明の理です。また関税引き上げにより米国内への生産回帰を目指す自国第一主義を追求すれば米国のみならず世界にインフレと景気悪化をばらまくことになります。移民抑制策は労働力低下によるインフレの原因となります。
米国債利回り上昇は日米金利差拡大を通じて円安ドル高をもたらします。トランプ氏はドル安にすべきと主張していますが、実際は円安ドル高と反対方向にむかっています。IIF(国際金融協会)は世界の政府債務は2030年末にはコロナ禍前の3倍に膨らむと予測。新型コロナ対策として世界各国がカネをばらまいたからですが、これに加えて米国第一主義の施策分が加わるなら貨幣の価値は下落を免れません。
さすがにこれはまずいと考えたのか、イーロン.マスク氏にDCGE(政府効率化省)を主導させ歳出削減により過剰支出を終わらせるとの方針を打ち出しています。しかしマスク氏は
いくつもの企業CEOであり自社の利益と、米国民の利益との利益相反問題をどのように回避できるのでしょうか。
選挙に勝つために国民が望む目先の利益を提供するポピュリズム。長期的安寧よりも自分の利益、これは将来の世代につけが回ることを意味します。SDG(Sustainable Development Goals )のDが「発展」ではなく「悲惨な」(Disastrous)を意味する世界に向かうとするなら、我々は何をしておけばよいのでしょうか。今後の米国政策の行方をしっかりフォローしてゆく必要がありそうです。
トランプ氏が選挙中から主張していた減税、関税引き上げ、移民抑制策はすべからくインフレにつながるもの。米国財政は悪化の一途をたどっているのに、今後さらに国債を発行することになれば利回りが上昇するのは自明の理です。また関税引き上げにより米国内への生産回帰を目指す自国第一主義を追求すれば米国のみならず世界にインフレと景気悪化をばらまくことになります。移民抑制策は労働力低下によるインフレの原因となります。
米国債利回り上昇は日米金利差拡大を通じて円安ドル高をもたらします。トランプ氏はドル安にすべきと主張していますが、実際は円安ドル高と反対方向にむかっています。IIF(国際金融協会)は世界の政府債務は2030年末にはコロナ禍前の3倍に膨らむと予測。新型コロナ対策として世界各国がカネをばらまいたからですが、これに加えて米国第一主義の施策分が加わるなら貨幣の価値は下落を免れません。
さすがにこれはまずいと考えたのか、イーロン.マスク氏にDCGE(政府効率化省)を主導させ歳出削減により過剰支出を終わらせるとの方針を打ち出しています。しかしマスク氏は
いくつもの企業CEOであり自社の利益と、米国民の利益との利益相反問題をどのように回避できるのでしょうか。
選挙に勝つために国民が望む目先の利益を提供するポピュリズム。長期的安寧よりも自分の利益、これは将来の世代につけが回ることを意味します。SDG(Sustainable Development Goals )のDが「発展」ではなく「悲惨な」(Disastrous)を意味する世界に向かうとするなら、我々は何をしておけばよいのでしょうか。今後の米国政策の行方をしっかりフォローしてゆく必要がありそうです。
2024.08.15
BAD NEWS IS BAD NEWS
8月初旬、株式市場は大暴落の洗礼をうけました。5日の日経平均下落幅は1987年のブラック・マンデーを超えて史上最悪の下落です。ことの本質は米国の失業率が上昇し続けていることにあります。(3月3.8%→7月4.3%)
日本株の下落幅が大きかったのは円キャリートレードの巻き戻しと言われています。日銀の利上げに驚いた海外投資家が保有していた膨大な「円売り、日本株買い」ポジションの反対売買を迫られたということです。またオプションの売り手が無限大の損失を回避するため先物を売ったことが日本株の下落に拍車をかけたというのも事実と思われます。
しかし日米共に株価が下落したのは失業率の上昇と雇用統計の予想を上回る悪化というマクロ要因によるというべきでしょう。米国においてはこれまでBAD NEWS IS GOOD NEWSと言われていました。失業率上昇など通常ならBAD NESと考えられる出来事はインフレを抑え込むGOOD NEWSとみなされてきました。インフレが進んでしまうと金利を引き上げねばならず株式市場にとってはネガティブな要因と見なされてきたからです。
ところが8月2日に発表された失業率、雇用統計の悪化というニュースは一転、リセッションを示唆するBAD NEWSだと市場は感じ始めました。今回の株価下落は恐れるべき対象がインフレから景気後退に変わったことを示唆しているとみるのが自然ではないでしょうか。
今後FRBは景気後退を避けるべく政策金利の引き下げを加速すると思われます。これによりソフトランディングを実現できれば良いのですが、米国政治の先行きには黒い大きな雲が沸き上がってきつつあります。民主、共和両党がともに標ぼうしている減税政策、この政策の行く末に見えるインフレがそれです。ただでも大きな財政赤字を抱えている米国が減税を実行し続けるとなると多額の米国債券を発行せざるを得ません。金融市場はどこかで米国債の吸収を諦めることになるでしょう。
Black Monday当時前後、米国のインフレと政策金利の動きをみると今後起きてくるかも知れない出来事のシナリオのように見えます。85年のプラザ合意当時インフレ率は3.63%、政策金利は8.0%でした。翌86年インフレ率は1.94%、政策金利は年末6.0%と大幅に下がっています。ところが87年に入るとインフレ率は再び3.58%に上昇、政策金利も年末7.5%に。そして同年10月20日Black Monday発生。米国インフレ率はその後も上昇を続け90年には5.42%に達しました。
現在世界を取り巻く環境は不動産、貿易、地政学リスクなどに加えて過去最大の世界債務拡大(GDP比98.1% IIF公表)という
状況にあり米国選挙後にはこの数値はさらに悪化の道をたどると見込まれます。
大暴落は今回をもって終了ということにはならないと考えておいた方が良さそうです。
日本株の下落幅が大きかったのは円キャリートレードの巻き戻しと言われています。日銀の利上げに驚いた海外投資家が保有していた膨大な「円売り、日本株買い」ポジションの反対売買を迫られたということです。またオプションの売り手が無限大の損失を回避するため先物を売ったことが日本株の下落に拍車をかけたというのも事実と思われます。
しかし日米共に株価が下落したのは失業率の上昇と雇用統計の予想を上回る悪化というマクロ要因によるというべきでしょう。米国においてはこれまでBAD NEWS IS GOOD NEWSと言われていました。失業率上昇など通常ならBAD NESと考えられる出来事はインフレを抑え込むGOOD NEWSとみなされてきました。インフレが進んでしまうと金利を引き上げねばならず株式市場にとってはネガティブな要因と見なされてきたからです。
ところが8月2日に発表された失業率、雇用統計の悪化というニュースは一転、リセッションを示唆するBAD NEWSだと市場は感じ始めました。今回の株価下落は恐れるべき対象がインフレから景気後退に変わったことを示唆しているとみるのが自然ではないでしょうか。
今後FRBは景気後退を避けるべく政策金利の引き下げを加速すると思われます。これによりソフトランディングを実現できれば良いのですが、米国政治の先行きには黒い大きな雲が沸き上がってきつつあります。民主、共和両党がともに標ぼうしている減税政策、この政策の行く末に見えるインフレがそれです。ただでも大きな財政赤字を抱えている米国が減税を実行し続けるとなると多額の米国債券を発行せざるを得ません。金融市場はどこかで米国債の吸収を諦めることになるでしょう。
Black Monday当時前後、米国のインフレと政策金利の動きをみると今後起きてくるかも知れない出来事のシナリオのように見えます。85年のプラザ合意当時インフレ率は3.63%、政策金利は8.0%でした。翌86年インフレ率は1.94%、政策金利は年末6.0%と大幅に下がっています。ところが87年に入るとインフレ率は再び3.58%に上昇、政策金利も年末7.5%に。そして同年10月20日Black Monday発生。米国インフレ率はその後も上昇を続け90年には5.42%に達しました。
現在世界を取り巻く環境は不動産、貿易、地政学リスクなどに加えて過去最大の世界債務拡大(GDP比98.1% IIF公表)という
状況にあり米国選挙後にはこの数値はさらに悪化の道をたどると見込まれます。
大暴落は今回をもって終了ということにはならないと考えておいた方が良さそうです。
2024.05.20
為替でワリを食う日本人
円安ドル高が様々な問題を提起しています。この連休、コロナ期のリベンジとして海外旅行を考えていた人々は旅費の高騰に驚いて行く先を変更した人も多かったことでしょう。このところの急激な円安にお得感を感じたのは海外からの観光客のみで、日本人旅行者は恨めし気に高い旅費を眺めていたはずです。
円安は輸入物価を押し上げるので、日常の買い物においても価格の高騰との闘いを余儀なくされます。物価以上に給料が上がらなかった人達はインフレに苦しめられ続けることになります。
国としても為替介入、口先介入などを通じて急激な円安を止めようと奮闘していますが問題の根本が日米金利差の大きさにあるので米国が金利を引き下げるか、日本が金利引き上げを行うかしなければ根本的解決にはつながりません。どちらも金利を変更するにはマクロ的経済状況の変化を待つしかないのでしょう。米国のインフレが収まるか、日本の経済が大きく上向いてくることを待つということです。
取りうる対策が限られているなかで、ドル売り円買いにつながる方法を考える必要があります。例えば日本企業が海外で保有しているドルを売って日本に還流させるなどです。殆どの場合日本企業は海外で稼いだドルを現地で投資に使ったり、運用したりしているので還流が起こりません。しかしそれ以外にも還流を妨げている理由があります。海外からの送金手数料がその一つです。
日本企業が海外で稼いだドルを日本国内に還流させるとドル売り円買いとなります。ところが海外で稼いだドルを日本に持ち込むと多額の手数料が発生します。送金手数料がもっと安ければ日本への送金により国内投資が増える可能性が高まるのではないでしょうか。海外に留保されている資金を日本にスムーズに還流させられれば円安ドル高の解消に貢献します。
日本のメガバンクは銀行間送金にスウィフトを使っており、複数の銀行を中継するので手数料は高額です。海外からの送金額の5%に加えて1$2円の為替手数料が課されることもあります。送金手数料がこれほど高額なら海外子会社の留保資金は現地で、ということにならざるを得ないでしょう。
最近では銀行以外の資金移動業者が増えておりこれを使うと送金時間や手数料は極めて有利になっています。現在は当該業者の認可や送金額に制限がかかっているため日本への送金が実施しにくいのが現状。認可の拡大や制限の縮小が円安問題の解決対策としてとりうる数少ない方法の一つとなるのではないでしょうか。
円安は輸入物価を押し上げるので、日常の買い物においても価格の高騰との闘いを余儀なくされます。物価以上に給料が上がらなかった人達はインフレに苦しめられ続けることになります。
国としても為替介入、口先介入などを通じて急激な円安を止めようと奮闘していますが問題の根本が日米金利差の大きさにあるので米国が金利を引き下げるか、日本が金利引き上げを行うかしなければ根本的解決にはつながりません。どちらも金利を変更するにはマクロ的経済状況の変化を待つしかないのでしょう。米国のインフレが収まるか、日本の経済が大きく上向いてくることを待つということです。
取りうる対策が限られているなかで、ドル売り円買いにつながる方法を考える必要があります。例えば日本企業が海外で保有しているドルを売って日本に還流させるなどです。殆どの場合日本企業は海外で稼いだドルを現地で投資に使ったり、運用したりしているので還流が起こりません。しかしそれ以外にも還流を妨げている理由があります。海外からの送金手数料がその一つです。
日本企業が海外で稼いだドルを日本国内に還流させるとドル売り円買いとなります。ところが海外で稼いだドルを日本に持ち込むと多額の手数料が発生します。送金手数料がもっと安ければ日本への送金により国内投資が増える可能性が高まるのではないでしょうか。海外に留保されている資金を日本にスムーズに還流させられれば円安ドル高の解消に貢献します。
日本のメガバンクは銀行間送金にスウィフトを使っており、複数の銀行を中継するので手数料は高額です。海外からの送金額の5%に加えて1$2円の為替手数料が課されることもあります。送金手数料がこれほど高額なら海外子会社の留保資金は現地で、ということにならざるを得ないでしょう。
最近では銀行以外の資金移動業者が増えておりこれを使うと送金時間や手数料は極めて有利になっています。現在は当該業者の認可や送金額に制限がかかっているため日本への送金が実施しにくいのが現状。認可の拡大や制限の縮小が円安問題の解決対策としてとりうる数少ない方法の一つとなるのではないでしょうか。
2024.04.08
進化を止めないジャンパー
昔、イタリアで買った茶色のジャンパーの穴をかがって着ることにしました。茶色のジャンパーをトレードマークとしているこの人にあやかりたいと思ったからです。ところがいそいそと着用に及んだ翌日、新聞を広げるとなんとその人のジャンパーは黒に代わっていました。
今回発表されたGB200という新型半導体に使用されているBlackwellというバージョンアップされたGPU(グラフィック用演算装置)にちなんだものなのでしょう。
その人の名はジェン・スン・ファン、言わずと知れたエヌビディアのCEOであります。同社はデータセンター向けGPUで92%のシェアを握っています。AIがデータを学習し、推論(生成AIが質問に答える機能)するには計算能力がモノをいいますがその能力はデータセンター内のサーバーによって供給されます。能力を高めるには膨大な計算が必要で、この演算を並列してこなし高い精度で提供できるのがGPUです。
エヌビディアの強みはこの製品である半導体に限られないところにあります。GPUを導入した企業がその能力をいかんなく発揮できるよう、当該企業の開発者の開発を初期段階から手助けするソフト(CUDA)を提供しているので、400万人を超える各企業の開発者はエヌビディアによって囲い込まれていることになります。
さらにファンCEOが今回披露した新型半導体GB200はGPUにCPU(中央演算装置)を組み合わせたサーバーで、生成AIの推論の性能を30倍に高めると言われています。学習機能のみならず推論にも強い製品を提供するならAI半導体という市場において追随を許さない地位を獲得することになるでしょう。
今後の社会では様々な産業分野においてAI半導体が必須のものとなると言われています。医療、創薬、デジタルツイン(工場や現場をデジタル上で再現するもの)
のシステム開発、気候や災害の予測などおよそ世の中に存在する産業でAI半導体のお世話にならない業界は稀だと思われます。
今後のAI開発において極めて高いスピードを求められることを見越して発表された新製品。
AI時代を切り開く先端に君臨していながら、さらに社会のニーズを先取りして進化し続ける象徴。それがファン氏のジャンパーであるということです。
株価が1年で3倍超になったことに何の不思議もありません。
今回発表されたGB200という新型半導体に使用されているBlackwellというバージョンアップされたGPU(グラフィック用演算装置)にちなんだものなのでしょう。
その人の名はジェン・スン・ファン、言わずと知れたエヌビディアのCEOであります。同社はデータセンター向けGPUで92%のシェアを握っています。AIがデータを学習し、推論(生成AIが質問に答える機能)するには計算能力がモノをいいますがその能力はデータセンター内のサーバーによって供給されます。能力を高めるには膨大な計算が必要で、この演算を並列してこなし高い精度で提供できるのがGPUです。
エヌビディアの強みはこの製品である半導体に限られないところにあります。GPUを導入した企業がその能力をいかんなく発揮できるよう、当該企業の開発者の開発を初期段階から手助けするソフト(CUDA)を提供しているので、400万人を超える各企業の開発者はエヌビディアによって囲い込まれていることになります。
さらにファンCEOが今回披露した新型半導体GB200はGPUにCPU(中央演算装置)を組み合わせたサーバーで、生成AIの推論の性能を30倍に高めると言われています。学習機能のみならず推論にも強い製品を提供するならAI半導体という市場において追随を許さない地位を獲得することになるでしょう。
今後の社会では様々な産業分野においてAI半導体が必須のものとなると言われています。医療、創薬、デジタルツイン(工場や現場をデジタル上で再現するもの)
のシステム開発、気候や災害の予測などおよそ世の中に存在する産業でAI半導体のお世話にならない業界は稀だと思われます。
今後のAI開発において極めて高いスピードを求められることを見越して発表された新製品。
AI時代を切り開く先端に君臨していながら、さらに社会のニーズを先取りして進化し続ける象徴。それがファン氏のジャンパーであるということです。
株価が1年で3倍超になったことに何の不思議もありません。
2024.01.19
日本経済を押し上げるNISA
24年日本経済は過去と決別して明るい未来に向けて動き出したようです。新NISAに多額の資金が入り日本人の投資マインドが変わるかもしれないというのが大きな要因です。1人につき1800万円の枠が与えられ、利益が出ても無税という大盤振る舞い。売却しても翌年には使った枠が回復するとなれば、投資で利益が出せている限り利益は全額投資家のものとなります。
昨今の急激な日経平均の上昇は海外投資家の買いが原因ともいわれていますが、なぜ外国人は2024年に入っていきなり買い始めたのでしょうか。過去にも日本の状況が大きく変わるという判断により日本に資金が流れ込んだことは何度かありました(アベノミクス等)。日本の個人金融資産は50%以上が預金に滞留しておりこれが日本の常識とみなされていたところ、新NISAの導入が日本人のマインドを変えるはずだ、というのが外国勢の判断だったのかもしれません。
2023年の経済財政白書によると、月の消費支出は株を持つ世帯の方がどの世帯でも増えているという結果が出ていました。特に50歳以上の世帯では35,000円の差が出たと報道されています。日本において消費はGDPの50%以上を占めるので、株式投資をする人が増え儲けを実感できれば消費が増加し経済を活性化させることにつながることでしょう。
賃金上昇と投資を比較した場合、どちらがより消費マインドが刺激されるでしょうか。人間の心理に基づくなら後者ということになるのではないでしょうか。給料が今までよりも増えた場合、上昇分の一部は貯蓄に向かうでしょうが株で儲かったからいざ貯蓄を、と考える人は多くないと思われます。たとえ売却して利益を出さなくとも、含み益が大きくなると消費マインドが刺激されるという資産効果が生まれてきます。
投資をする際リターンは多い方がよいので、投資信託など投資商品を選ぶ場合過去の利益率が高いものを探すかもしれません。但しこの数値は為替の影響が含まれていること、あくまでも過去のものであって、将来を約束するものではないことに注意が必要なのは言を俟ちません。
例えば昨年のS&P500の投資信託上昇率が前年比36%であったとした場合ドル高の影響を除くと23%上昇に過ぎないというようなものです。 また22年との比較では23%上昇であっても、21年比較ではマイナス1%というようなことが起きています。
22年のS&P500は米国の急激な利上げ継続により歴史的下落を経験しました。また日米の金利差が拡大するにつれ円安ドル高が一挙に進みました。投資はマクロ経済変動の影響を大きく受けるので指数に投資する場合には常に金利、政策、為替等に気を配る必要があります。
また海外投信が日本からの資金流出につながるからといって日本の投信の方が良いというわけでもありません。幸い23年は日本株の上昇率が22年比28%となり、上げ幅は1989年以来の大きさでした。米国S&P500の上昇率は24%だったので4%上回っていました。
どんな対象に投資をしようと、各人が利益をしっかり確保するマインドが広がれば金融資産への投資が消費を刺激し結果として日本経済にも大きく貢献することになるということです。
昨今の急激な日経平均の上昇は海外投資家の買いが原因ともいわれていますが、なぜ外国人は2024年に入っていきなり買い始めたのでしょうか。過去にも日本の状況が大きく変わるという判断により日本に資金が流れ込んだことは何度かありました(アベノミクス等)。日本の個人金融資産は50%以上が預金に滞留しておりこれが日本の常識とみなされていたところ、新NISAの導入が日本人のマインドを変えるはずだ、というのが外国勢の判断だったのかもしれません。
2023年の経済財政白書によると、月の消費支出は株を持つ世帯の方がどの世帯でも増えているという結果が出ていました。特に50歳以上の世帯では35,000円の差が出たと報道されています。日本において消費はGDPの50%以上を占めるので、株式投資をする人が増え儲けを実感できれば消費が増加し経済を活性化させることにつながることでしょう。
賃金上昇と投資を比較した場合、どちらがより消費マインドが刺激されるでしょうか。人間の心理に基づくなら後者ということになるのではないでしょうか。給料が今までよりも増えた場合、上昇分の一部は貯蓄に向かうでしょうが株で儲かったからいざ貯蓄を、と考える人は多くないと思われます。たとえ売却して利益を出さなくとも、含み益が大きくなると消費マインドが刺激されるという資産効果が生まれてきます。
投資をする際リターンは多い方がよいので、投資信託など投資商品を選ぶ場合過去の利益率が高いものを探すかもしれません。但しこの数値は為替の影響が含まれていること、あくまでも過去のものであって、将来を約束するものではないことに注意が必要なのは言を俟ちません。
例えば昨年のS&P500の投資信託上昇率が前年比36%であったとした場合ドル高の影響を除くと23%上昇に過ぎないというようなものです。 また22年との比較では23%上昇であっても、21年比較ではマイナス1%というようなことが起きています。
22年のS&P500は米国の急激な利上げ継続により歴史的下落を経験しました。また日米の金利差が拡大するにつれ円安ドル高が一挙に進みました。投資はマクロ経済変動の影響を大きく受けるので指数に投資する場合には常に金利、政策、為替等に気を配る必要があります。
また海外投信が日本からの資金流出につながるからといって日本の投信の方が良いというわけでもありません。幸い23年は日本株の上昇率が22年比28%となり、上げ幅は1989年以来の大きさでした。米国S&P500の上昇率は24%だったので4%上回っていました。
どんな対象に投資をしようと、各人が利益をしっかり確保するマインドが広がれば金融資産への投資が消費を刺激し結果として日本経済にも大きく貢献することになるということです。
2023.11.17
潮目の変わった11月
米国10年債の利回り上昇が10月の株式市場を揺さぶりました。利回り上昇はインフレに加え、米国債務が過去最高を更新したことによる財政赤字拡大が主たる原因と思われます。株式市場は利回り上昇に翻弄される形で下げ続けてきました。
ところが11月に入って政策金利追加利上げ観測が後退、一転して株価は上昇。さらに3日に発表された労働市場に関するデータが予想に反して弱含みであったことの影響も大きく出ました。これまで労働市場が好調という指標が続いたため利上げを止める段階ではないと判断されていたのが今回の発表でひっくり返った訳です。世界の株価は急反発、日経平均も一日で758円上昇しました。
続いて14日発表された米国消費者物価が予想に反して低かったことが再び株価上昇に拍車をかけました。ここまでの米国インフレ上昇懸念が逆回転を始めたと捉えられ、再び世界の株価を押し上げ、15日の日経平均は824円の爆上げです。11月に入っての株価上昇は市場の潮目変化を示唆しているのかもしれません。労働需要の過熱が収まり、インフレが収束してゆくなら実に喜ばしいことではあります。
しかしもし、今後逆に失業率が上昇を続けてゆくならどうなるでしょうか。利上げ停止が宣言され、やがて利下げという局面に入ってゆくことでしょう。さらにそう遠くない将来リセッションに入ってゆく可能性も否定できません。一番の懸念事項は世界貿易の大幅縮小。中国やロシアに対する輸出規制、ブロック経済化等により世界のGDPが最大7%下押しされると見込まれています。(IMF)
また中国の不動産バブル崩壊が同国の経済下落を煽っており、中国の国力低下は世界の消費や投資、貿易に少なからざる打撃となると思われます。今後どのような道筋を辿るのか心配はぬぐえません。
欧州はインフレと景気後退の共存であるスタグフレーションに突入しておりロシア、ウクライナの戦争等によるエネルギー危機の影響を今後もさらに受けざるを得ないでしょう。欧州の株価もこれらを織り込んで低調な水準にとどまっています。
日本は幸いにも金利は低位にコントロールされていますが、日銀の国債大量買いにより恣意的に押し下げられているところ大なので、インフレが安定的に2%を上回ったと判断されれば、金利引き上げに転換するのもそう遠い話ではなさそうです。
今のところ米国の好調が世界景気を支える格好になっていますが、米国も商業不動産の低迷、4,000万人ともいわれる大学の学生ローン返済の開始、クレジットローンの返済デフォルト等下押しのリスクが堆積しつつあります。
米国の長期金利利回りが下がると株価が上がるという図式が繰り返されてきましたが、もし利回りが継続して低下を続けるなら、経済好調の支えを失った世界経済は厳しい時代という逆の潮目に巻き込まれることになります。株高に浮かれてばかりいるわけにはいかないのであります。
ところが11月に入って政策金利追加利上げ観測が後退、一転して株価は上昇。さらに3日に発表された労働市場に関するデータが予想に反して弱含みであったことの影響も大きく出ました。これまで労働市場が好調という指標が続いたため利上げを止める段階ではないと判断されていたのが今回の発表でひっくり返った訳です。世界の株価は急反発、日経平均も一日で758円上昇しました。
続いて14日発表された米国消費者物価が予想に反して低かったことが再び株価上昇に拍車をかけました。ここまでの米国インフレ上昇懸念が逆回転を始めたと捉えられ、再び世界の株価を押し上げ、15日の日経平均は824円の爆上げです。11月に入っての株価上昇は市場の潮目変化を示唆しているのかもしれません。労働需要の過熱が収まり、インフレが収束してゆくなら実に喜ばしいことではあります。
しかしもし、今後逆に失業率が上昇を続けてゆくならどうなるでしょうか。利上げ停止が宣言され、やがて利下げという局面に入ってゆくことでしょう。さらにそう遠くない将来リセッションに入ってゆく可能性も否定できません。一番の懸念事項は世界貿易の大幅縮小。中国やロシアに対する輸出規制、ブロック経済化等により世界のGDPが最大7%下押しされると見込まれています。(IMF)
また中国の不動産バブル崩壊が同国の経済下落を煽っており、中国の国力低下は世界の消費や投資、貿易に少なからざる打撃となると思われます。今後どのような道筋を辿るのか心配はぬぐえません。
欧州はインフレと景気後退の共存であるスタグフレーションに突入しておりロシア、ウクライナの戦争等によるエネルギー危機の影響を今後もさらに受けざるを得ないでしょう。欧州の株価もこれらを織り込んで低調な水準にとどまっています。
日本は幸いにも金利は低位にコントロールされていますが、日銀の国債大量買いにより恣意的に押し下げられているところ大なので、インフレが安定的に2%を上回ったと判断されれば、金利引き上げに転換するのもそう遠い話ではなさそうです。
今のところ米国の好調が世界景気を支える格好になっていますが、米国も商業不動産の低迷、4,000万人ともいわれる大学の学生ローン返済の開始、クレジットローンの返済デフォルト等下押しのリスクが堆積しつつあります。
米国の長期金利利回りが下がると株価が上がるという図式が繰り返されてきましたが、もし利回りが継続して低下を続けるなら、経済好調の支えを失った世界経済は厳しい時代という逆の潮目に巻き込まれることになります。株高に浮かれてばかりいるわけにはいかないのであります。
2023.09.11
インバウンドとオーバーツーリズム対策
日本の至る所に外国人を見かける今日この頃。コロナのころと比べると街の景色が一変したことを実感します。夜の六本木ではツアー客の団体がガイドの説明を聞いた後、嬉しそうに飲食店に入ってゆく姿をよく見かけます。また屋外テラスでビールやシャンパンを飲みながら会話を楽しんでいる外国人も増えてきました。
インバウンド客は買い物や宿泊、交通、飲食等で多額のお金を落としてくれるので、日本経済にとってはありがたい存在です。また外国人にとっても円安の恩恵をたっぷり受けられる日本への旅行は楽しさ倍増と言ったところでしょう。あまり価格を気にすることなく日本の料理や自然、風景を味わうことが出来るのです。
一方インバウンドにおける日本サイドの問題として人材不足があります。従業員が不足して十分に稼働できない宿泊施設が結構あるようです。宿泊業の人件費が魅力的な水準になっていないことが主な原因だと思われます。(厚生省の産業別賃金によると宿泊業、飲食サービス業は最下位)ホテルや旅館は最近になって宿泊単価を上げてきていますが、装置産業である宿泊業においては上げた単価が施設の手直し等に使われるので賃金に反映されるには時間を要するかもしれません。
インバウンド増加は日本経済にとって紛れもないチャンスなので、人材不足というボトルネックは早急に解消されなければなりません。宿泊業で従業員が不足しているのは、コロナ禍で宿泊者が大幅に減少して他の業態に移ったまま戻ってきていないという側面が大きいと思われます。問題解決の為、どのような施策が考えられるでしょうか。
例えば、インバウンド客に人件費の一部を負担してもらうというのはいかがなものでしょう。良いサービスや満足感に対してチップを払うことは当然とされている諸外国の人々にとってチップの代わりに税金を付加されたとしても不満を感じることは少ないと思われます。
日本でもホテルや旅館に宿泊したとき宿泊税が加算されることがあります。場所によって金額が異なるものの、料金は100~500円程度、課税している地域も東京、大阪を始め7都道府県程度です。但し使用用途は観光振興(案内標識、案内所運営、観光プロモーション)に限定されています。
国際観光旅客税というものもあり、2020.1より出国時に1000円(航空券代などに含まれる)が徴収されます。しかしこれも観光基盤の拡充、強化の為と使用用途が決まっています。
海外ホテルでも宿泊税が課される地域は多く、例えばハワイのホテル宿泊料に課される税率は約18%(内ホテル税は13.25%)となっています。13.25%の内3%はコロナ禍での観光客減に対処するため2022.1月に導入されたものです。
インバウンドはGDPの計算上輸出としてカウントされるので貿易収支が低迷している我が国にとって大切な収入源となりつつあります。世界から旅行者を呼び込めるインフラをしっかり充実させることは今後の日本の為にも重要な施策であります。
インバウンド客により気持ちよく滞在してもらえるよう、宿泊業従事者の賃金上乗せに使える料金の徴収(外国人に負担してもらう税金の新設)や、既存の宿泊税、観光旅客税の用途変更等を検討してもよい時期にきているのではないでしょうか。
インバウンド客は買い物や宿泊、交通、飲食等で多額のお金を落としてくれるので、日本経済にとってはありがたい存在です。また外国人にとっても円安の恩恵をたっぷり受けられる日本への旅行は楽しさ倍増と言ったところでしょう。あまり価格を気にすることなく日本の料理や自然、風景を味わうことが出来るのです。
一方インバウンドにおける日本サイドの問題として人材不足があります。従業員が不足して十分に稼働できない宿泊施設が結構あるようです。宿泊業の人件費が魅力的な水準になっていないことが主な原因だと思われます。(厚生省の産業別賃金によると宿泊業、飲食サービス業は最下位)ホテルや旅館は最近になって宿泊単価を上げてきていますが、装置産業である宿泊業においては上げた単価が施設の手直し等に使われるので賃金に反映されるには時間を要するかもしれません。
インバウンド増加は日本経済にとって紛れもないチャンスなので、人材不足というボトルネックは早急に解消されなければなりません。宿泊業で従業員が不足しているのは、コロナ禍で宿泊者が大幅に減少して他の業態に移ったまま戻ってきていないという側面が大きいと思われます。問題解決の為、どのような施策が考えられるでしょうか。
例えば、インバウンド客に人件費の一部を負担してもらうというのはいかがなものでしょう。良いサービスや満足感に対してチップを払うことは当然とされている諸外国の人々にとってチップの代わりに税金を付加されたとしても不満を感じることは少ないと思われます。
日本でもホテルや旅館に宿泊したとき宿泊税が加算されることがあります。場所によって金額が異なるものの、料金は100~500円程度、課税している地域も東京、大阪を始め7都道府県程度です。但し使用用途は観光振興(案内標識、案内所運営、観光プロモーション)に限定されています。
国際観光旅客税というものもあり、2020.1より出国時に1000円(航空券代などに含まれる)が徴収されます。しかしこれも観光基盤の拡充、強化の為と使用用途が決まっています。
海外ホテルでも宿泊税が課される地域は多く、例えばハワイのホテル宿泊料に課される税率は約18%(内ホテル税は13.25%)となっています。13.25%の内3%はコロナ禍での観光客減に対処するため2022.1月に導入されたものです。
インバウンドはGDPの計算上輸出としてカウントされるので貿易収支が低迷している我が国にとって大切な収入源となりつつあります。世界から旅行者を呼び込めるインフラをしっかり充実させることは今後の日本の為にも重要な施策であります。
インバウンド客により気持ちよく滞在してもらえるよう、宿泊業従事者の賃金上乗せに使える料金の徴収(外国人に負担してもらう税金の新設)や、既存の宿泊税、観光旅客税の用途変更等を検討してもよい時期にきているのではないでしょうか。
2023.08.07
幻想のユーフォリア
米国はインフレが収まりつつあり、消費者物価も日本以下の水準にあります。(6月の物価上昇率は米国3.0%,日本3.3%)金利上昇の心配をする局面ではなくなってきているとみなされ、米国株は絶好調でダウ平均は13週連続の上げ相場を記録しました。
ただ長短金利は相変わらず逆転しており、過去を踏襲するならリセッションに向かうのが普通、なぜそうならないのか不思議ではあります。2年債と10年債の利回りは前者4.76%、後者4.03%と逆イールドになっており、3か月物に至っては5.4%です。(何れも2023.8.4現在)逆イールドは景気後退を市場が懸念していることを示しており、過去においては逆イールドの発生後には市場を大きく揺るがす事態が発生しています。ITバブル崩壊、リーマンショック、コロナショック等です。
景気後退が実現するのは0.5~1.5年後とされており、米国で逆イールドが発生したのは22年4月なので今年の10月までにはリセッション入りの可能性がありますが、今のところそのような気配が見えません。何か、これまでとは異なる要因がリセッション入りを食い止めているのでしょうか。
全世界の人々が3年近くにわたって牢獄のような生活を強いられという経験はかつてなかったことなので、これまでと異なるメンタリティーや行動が生まれても不思議はありません。こうした変化が実体経済に影響を与えこれまでと違う原理が働きだした可能性があります。
コロナ後顕著になっているのはリベンジ消費や、人生を楽しめるうちに楽しみたいというマインドの変化です。こうした情動がサービス産業への需要を膨らませているはずです。加えて自宅で働くことが普通になったことによる労働時間の減少、IT普及による労働生産性の向上等が重なって労働力不足が発生し、その結果賃金の上昇が景気を押し上げるという現象に至っていると考えられます。今後も労働力不足やインフレ鈍化が続くのであれば景気の悪化やリセッションは避けられるのかもしれません。
ただ、金利変動が経済に与える影響はそう簡単に消えてしまうものではないはず。リセッション入りの可能性は消滅したと考えるのは時期尚早ではないでしょうか。足元ではフィッチレーティングによる米国債格下げの影響で10年債の利回りは上昇を始めています。(価格は下落)絶好調を続けてきた株価に冷や水を浴びせる結果となったことを考え合わせるとリセッション入りの可能性は消え去ったと考えるべきではないと思われます。ユーフォリアは幻想、リスクには依然として警戒が必要です。
ただ長短金利は相変わらず逆転しており、過去を踏襲するならリセッションに向かうのが普通、なぜそうならないのか不思議ではあります。2年債と10年債の利回りは前者4.76%、後者4.03%と逆イールドになっており、3か月物に至っては5.4%です。(何れも2023.8.4現在)逆イールドは景気後退を市場が懸念していることを示しており、過去においては逆イールドの発生後には市場を大きく揺るがす事態が発生しています。ITバブル崩壊、リーマンショック、コロナショック等です。
景気後退が実現するのは0.5~1.5年後とされており、米国で逆イールドが発生したのは22年4月なので今年の10月までにはリセッション入りの可能性がありますが、今のところそのような気配が見えません。何か、これまでとは異なる要因がリセッション入りを食い止めているのでしょうか。
全世界の人々が3年近くにわたって牢獄のような生活を強いられという経験はかつてなかったことなので、これまでと異なるメンタリティーや行動が生まれても不思議はありません。こうした変化が実体経済に影響を与えこれまでと違う原理が働きだした可能性があります。
コロナ後顕著になっているのはリベンジ消費や、人生を楽しめるうちに楽しみたいというマインドの変化です。こうした情動がサービス産業への需要を膨らませているはずです。加えて自宅で働くことが普通になったことによる労働時間の減少、IT普及による労働生産性の向上等が重なって労働力不足が発生し、その結果賃金の上昇が景気を押し上げるという現象に至っていると考えられます。今後も労働力不足やインフレ鈍化が続くのであれば景気の悪化やリセッションは避けられるのかもしれません。
ただ、金利変動が経済に与える影響はそう簡単に消えてしまうものではないはず。リセッション入りの可能性は消滅したと考えるのは時期尚早ではないでしょうか。足元ではフィッチレーティングによる米国債格下げの影響で10年債の利回りは上昇を始めています。(価格は下落)絶好調を続けてきた株価に冷や水を浴びせる結果となったことを考え合わせるとリセッション入りの可能性は消え去ったと考えるべきではないと思われます。ユーフォリアは幻想、リスクには依然として警戒が必要です。
2023.06.14
日経平均バブル最高値超え?
5月中旬、日経平均はついに3万円を超え上昇を続けています。(6月現在:33,500円超)日経平均の過去最高値はバブル期1989年12月29日に付けた38,915円ですが、今後日経平均は上昇を続けバブル期最高値を超えるのでしょうか。
1989年当時なぜこれほどの高値を付けることになったのか、また当時が現在と比較してどれほど異常な状況にあったのかを概観してみます。当時の経済状況について見てみると1980年から1990年までの10年間、日本経済は右肩上がりの好調を続けていたことがわかります。名目GDPの時系列データを見ると268.4兆円(1980年)→614.6兆円(1990年)と見事な右肩上がりです。
経済が好調であれば株価が上昇するのは理にかなったことですが、バブルを正当化するほどの理由にはなりません。ではバブルを引き起こしたのはなんだったのでしょうか。結論から言うと急激な金利の引き下げです。
1980年から1990年までの公定歩合(現在の政策金利)の時系列を見ると8.25%(1980年)→3.25%(1990年)と急激に下がっています。通常、経済が好調な時には金利を引き上げて過熱を防ぐのが常道ですが真逆となっています。バブルが起きるのは当然と言わざるをえないでしょう。
なぜこんな金利政策を採用したのか、ここに経済政策の難しさが垣間見えます。当時の日本は国内で製造する製品の優秀さに加え、円安の恩恵もあって貿易収支は(13.6兆円(1980年)→33.1兆円(1990年)と絶好調でした。ところが米国は大幅な貿易赤字に苦しんでおり日本を含む主要5か国に協調的ドル下げを要請。(1985年プラザ合意)これに応じた結果ドル円レートは1年で44%もの大幅下落(232円→154円)となりました。
この急激な円高に日本企業は大打撃を受けます。行き過ぎた円高を回避すべく政府、日銀は協調して公定歩合を大幅に引き下げ、その結果起きたのが壮大なバブルだったというわけです。日本はそのバブルの後遺症に20年以上も苦しむことになりました。
さて現在の株高はなぜ起きているのか、バブルではないのでしょうか。結論から言うと(このままGDFや消費者物価が上昇を続けるなら)バブルであると言えます。23年1~3月期の名目GDPは前期比1.7%(年率7.1%)、年率換算の実額570兆円と過去最高を更新と報道されています。一方政策金利は0%に止め置かれています。過去のバブルは金利下げ過ぎ、現在のバブルは金利の低すぎという共通項の上に成り立っています。
前回バブル時と同様に難しいのは政治的側面にあります。政策金利引き上げは、住宅ローンの借り手や企業の回復に打撃となるので負の影響を出来るだけ小さくしたいという配慮が働きます。完全に過去のデフレ状況から脱するまでは金利引き上げは避けたいという力学が働く限り、バブル発生と日経平均の上昇は進むのでしょう。
日経平均株価が過去のバブル時を超えるか否かは分かりませんが、日銀のスタンスが変更されない限り外人買いは止まらず上昇は続くと思われます。
(注:1980~1990の名目GDP、公定歩合、貿易収支の時系列データはChatGPTのアウトプットを利用しています。)
1989年当時なぜこれほどの高値を付けることになったのか、また当時が現在と比較してどれほど異常な状況にあったのかを概観してみます。当時の経済状況について見てみると1980年から1990年までの10年間、日本経済は右肩上がりの好調を続けていたことがわかります。名目GDPの時系列データを見ると268.4兆円(1980年)→614.6兆円(1990年)と見事な右肩上がりです。
経済が好調であれば株価が上昇するのは理にかなったことですが、バブルを正当化するほどの理由にはなりません。ではバブルを引き起こしたのはなんだったのでしょうか。結論から言うと急激な金利の引き下げです。
1980年から1990年までの公定歩合(現在の政策金利)の時系列を見ると8.25%(1980年)→3.25%(1990年)と急激に下がっています。通常、経済が好調な時には金利を引き上げて過熱を防ぐのが常道ですが真逆となっています。バブルが起きるのは当然と言わざるをえないでしょう。
なぜこんな金利政策を採用したのか、ここに経済政策の難しさが垣間見えます。当時の日本は国内で製造する製品の優秀さに加え、円安の恩恵もあって貿易収支は(13.6兆円(1980年)→33.1兆円(1990年)と絶好調でした。ところが米国は大幅な貿易赤字に苦しんでおり日本を含む主要5か国に協調的ドル下げを要請。(1985年プラザ合意)これに応じた結果ドル円レートは1年で44%もの大幅下落(232円→154円)となりました。
この急激な円高に日本企業は大打撃を受けます。行き過ぎた円高を回避すべく政府、日銀は協調して公定歩合を大幅に引き下げ、その結果起きたのが壮大なバブルだったというわけです。日本はそのバブルの後遺症に20年以上も苦しむことになりました。
さて現在の株高はなぜ起きているのか、バブルではないのでしょうか。結論から言うと(このままGDFや消費者物価が上昇を続けるなら)バブルであると言えます。23年1~3月期の名目GDPは前期比1.7%(年率7.1%)、年率換算の実額570兆円と過去最高を更新と報道されています。一方政策金利は0%に止め置かれています。過去のバブルは金利下げ過ぎ、現在のバブルは金利の低すぎという共通項の上に成り立っています。
前回バブル時と同様に難しいのは政治的側面にあります。政策金利引き上げは、住宅ローンの借り手や企業の回復に打撃となるので負の影響を出来るだけ小さくしたいという配慮が働きます。完全に過去のデフレ状況から脱するまでは金利引き上げは避けたいという力学が働く限り、バブル発生と日経平均の上昇は進むのでしょう。
日経平均株価が過去のバブル時を超えるか否かは分かりませんが、日銀のスタンスが変更されない限り外人買いは止まらず上昇は続くと思われます。
(注:1980~1990の名目GDP、公定歩合、貿易収支の時系列データはChatGPTのアウトプットを利用しています。)
2023.05.12
別世界日本の根本問題
世界がインフレにおののき、さらに金利引き上げが銀行問題を引き起こしている昨今、まるで別世界の様相を呈している日本。米国の金利(政策金利)が5%を超えているのに日本の金利は0です。なんとか2%のインフレを実現したいと手を尽くしてきた日銀の苦労は諸外国から見ると贅沢な悩みに見えるかもしれません。生まれている差異は何によるのでしょうか。
根本原因は一言でいうと需要が供給を下回り続けてきたことです。そしてそれが30年近くにもわたって続いたのは①将来に対する不安が大きく②賃金が殆ど増えなかったこと。その結果日本全体の需要が増えず、経済成長率(GDP)が長い期間にわたって殆ど横ばいとなってしまったということでしょう。
ウソだと思うかもしれませんが、諸外国に比べて将来に対する不安が大きい理由の一つに日本人の気質があります。この気質の元となっている物質はセロトニントランスポーター遺伝子と呼ばれ、S型とL型に分かれています。このLが多いと安定感や幸福感が大きくなるという特性を持っています。日本人は欧米人に比べSが多いといわれており、その結果、将来に対する不安が大きくなることにつながっているようです。
例えば投資において恐怖と貪欲に打ち勝つことが成功のカギであると言われていますが、同物質の影響で恐怖が強いなら投資より安全な貯蓄を選好するという行動が日本で続いてきたことには納得がいきます。低い金利に甘んじて高い利回りを得られる投資という可能性を避けてきたことが消費需要にもブレーキをかけてきたという結果を生んでしまったのかもしれません。
賃金が増えない理由は2つ考えられます。三波春夫効果、労働契約法であります。前者において、お客様は神様なので原価が上がっても企業は販売価格になかなか転嫁できません。消費者も神様に向かって値段をあげるのはけしからんというマインドが強いので、企業は低い利益で耐えるべきだと考えがちです。それがやがて自分の首を絞めることになるのですが、神様である自分には関係のない話だと思い込んでいるように見えます。
日本の労働契約法ではレイオフに相当な理由が必要とされており、少し業績が悪化しそうというくらいで解雇することは違法となります。一方欧米では景気が悪化してくればすぐにレイオフが行われその結果企業業績は比較的早く回復します。業績が回復すれば競合との競争に勝つためにも賃金をあげるのが理にかなっているので国の全体的な景気も押し上げられるというわけです。
企業の立場から見れば景気変動に対してより柔軟な経営が行われるので利益を守りやすくなります。最近も米国の地銀問題で株価が大きく調整していたにもかかわらず、突如として株価が急騰したりしていました。理由の一つはGAFAMなどの決算発表。市場予想を超える良い決算であった為ですが、その背景には急激かつ大量の人員整理があったことが思い起こされます。
日本は解雇なしが前提であったので、企業利益を保持するには賃金を下げるしかありません。景気が回復してくれば再度雇用を増やして対処する欧米企業に対し、日本企業は変動を避けながら賃金を上げてゆくというスローペースの対応とならざるを得ません。失業はしないが、賃金は増えないということになると消費はなかなか盛り上がらない、というのがこれまでの姿でした。
しかし最も根本的な問題は、世界を変えてしまうような圧倒的ビジネスがなかなか生まれてこないことです。国や人種にかかわらず、人間であればどんな人でも使ってみたいと思うような財やサービス。こうしたものを生み出す力が出てこなかった理由は他にもあるでしょうが、教育の画一性が大きいと思われます。独創性や自由よりも規範や協調を重視することを、教育の目的としてきたことの弊害です。
生まれる子供の数が少なく、労働人口が減り続けていることが、日本の根本問題と言われていますが、これは結果(①②のような問題の)であって、原因ではないのではないでしょうか。安心して暮らせる社会実現と、アニマルスピリッツ(本能的欲求)の発揮を厭わない国民によって日本の根本問題は解消できるというのは夢物語にすぎないでしょうか。
根本原因は一言でいうと需要が供給を下回り続けてきたことです。そしてそれが30年近くにもわたって続いたのは①将来に対する不安が大きく②賃金が殆ど増えなかったこと。その結果日本全体の需要が増えず、経済成長率(GDP)が長い期間にわたって殆ど横ばいとなってしまったということでしょう。
ウソだと思うかもしれませんが、諸外国に比べて将来に対する不安が大きい理由の一つに日本人の気質があります。この気質の元となっている物質はセロトニントランスポーター遺伝子と呼ばれ、S型とL型に分かれています。このLが多いと安定感や幸福感が大きくなるという特性を持っています。日本人は欧米人に比べSが多いといわれており、その結果、将来に対する不安が大きくなることにつながっているようです。
例えば投資において恐怖と貪欲に打ち勝つことが成功のカギであると言われていますが、同物質の影響で恐怖が強いなら投資より安全な貯蓄を選好するという行動が日本で続いてきたことには納得がいきます。低い金利に甘んじて高い利回りを得られる投資という可能性を避けてきたことが消費需要にもブレーキをかけてきたという結果を生んでしまったのかもしれません。
賃金が増えない理由は2つ考えられます。三波春夫効果、労働契約法であります。前者において、お客様は神様なので原価が上がっても企業は販売価格になかなか転嫁できません。消費者も神様に向かって値段をあげるのはけしからんというマインドが強いので、企業は低い利益で耐えるべきだと考えがちです。それがやがて自分の首を絞めることになるのですが、神様である自分には関係のない話だと思い込んでいるように見えます。
日本の労働契約法ではレイオフに相当な理由が必要とされており、少し業績が悪化しそうというくらいで解雇することは違法となります。一方欧米では景気が悪化してくればすぐにレイオフが行われその結果企業業績は比較的早く回復します。業績が回復すれば競合との競争に勝つためにも賃金をあげるのが理にかなっているので国の全体的な景気も押し上げられるというわけです。
企業の立場から見れば景気変動に対してより柔軟な経営が行われるので利益を守りやすくなります。最近も米国の地銀問題で株価が大きく調整していたにもかかわらず、突如として株価が急騰したりしていました。理由の一つはGAFAMなどの決算発表。市場予想を超える良い決算であった為ですが、その背景には急激かつ大量の人員整理があったことが思い起こされます。
日本は解雇なしが前提であったので、企業利益を保持するには賃金を下げるしかありません。景気が回復してくれば再度雇用を増やして対処する欧米企業に対し、日本企業は変動を避けながら賃金を上げてゆくというスローペースの対応とならざるを得ません。失業はしないが、賃金は増えないということになると消費はなかなか盛り上がらない、というのがこれまでの姿でした。
しかし最も根本的な問題は、世界を変えてしまうような圧倒的ビジネスがなかなか生まれてこないことです。国や人種にかかわらず、人間であればどんな人でも使ってみたいと思うような財やサービス。こうしたものを生み出す力が出てこなかった理由は他にもあるでしょうが、教育の画一性が大きいと思われます。独創性や自由よりも規範や協調を重視することを、教育の目的としてきたことの弊害です。
生まれる子供の数が少なく、労働人口が減り続けていることが、日本の根本問題と言われていますが、これは結果(①②のような問題の)であって、原因ではないのではないでしょうか。安心して暮らせる社会実現と、アニマルスピリッツ(本能的欲求)の発揮を厭わない国民によって日本の根本問題は解消できるというのは夢物語にすぎないでしょうか。
2023.04.12
不思議が動かす世界へ
企業間の競争において他社との差別化が有効な要素であるということは自明の理であります。特に製造業においては昔からR&D(研究開発)の優劣が大きな差を生み出してきました。問題はとてつもない費用と時間がかかることにあります。例えば医薬品の開発には500億程度の費用と10年単位の時間が必要と言われてきました。それだけのコストをかけても画期的新薬を生み出せる確率は極めて低いというのが常識でした。
AIと量子コンピューターの融合がこのトレンドを変えようとしています。これまでは膨大なデータから病気の治療に有効な薬を見つけ出すには人の勘や経験に依存せざるを得なかったことが開発のネックでした。今後は治療に有効な化合物を特定し量産する等の作業の殆どをAIと量子が担う時代がやって来ることが現実味を帯びてきています。
医薬品のみならず化粧品の開発においてもAIと量子の組み合わせが使われ始めています。肌のみずみずしさやもっちり感といった使用感を出すにはどのような成分の原料をどのくらいの割合で配合するか。この気の遠くなるような組み合わせの結果も医薬品と同様なプロセスによって短時間で作成が可能となっています。
量子はスーパーコンピューターの1億倍の速さといわれており、1万年かかる計算を3分で実行できる(google)ということになっています。量子は波と粒子の性質を併せ持ち、複数の場所に同時に存在するという不思議な存在でもあります。(量子は原子レベル以下の極微単位で、光子(電子や光の粒)が代表例)
量子の世界には我々が実感として捉えられるモノは存在しないということになっているようです。とすると、あるのはコトのみ。量子や粒子が大量に集まってできているこの世界は何なのでしょうか。空であり、実在するのはコトのみということになるのでしょうか。
R&D(研究開発)においてもR(調査)はAI・量子に任せ、D(開発)という課題に集中する世界がやって来るとすれば、どういう効果を得たいのか(コト)を明確にすることこそが差別化の中心になってくるのかもしれません。
AIと量子コンピューターの融合がこのトレンドを変えようとしています。これまでは膨大なデータから病気の治療に有効な薬を見つけ出すには人の勘や経験に依存せざるを得なかったことが開発のネックでした。今後は治療に有効な化合物を特定し量産する等の作業の殆どをAIと量子が担う時代がやって来ることが現実味を帯びてきています。
医薬品のみならず化粧品の開発においてもAIと量子の組み合わせが使われ始めています。肌のみずみずしさやもっちり感といった使用感を出すにはどのような成分の原料をどのくらいの割合で配合するか。この気の遠くなるような組み合わせの結果も医薬品と同様なプロセスによって短時間で作成が可能となっています。
量子はスーパーコンピューターの1億倍の速さといわれており、1万年かかる計算を3分で実行できる(google)ということになっています。量子は波と粒子の性質を併せ持ち、複数の場所に同時に存在するという不思議な存在でもあります。(量子は原子レベル以下の極微単位で、光子(電子や光の粒)が代表例)
量子の世界には我々が実感として捉えられるモノは存在しないということになっているようです。とすると、あるのはコトのみ。量子や粒子が大量に集まってできているこの世界は何なのでしょうか。空であり、実在するのはコトのみということになるのでしょうか。
R&D(研究開発)においてもR(調査)はAI・量子に任せ、D(開発)という課題に集中する世界がやって来るとすれば、どういう効果を得たいのか(コト)を明確にすることこそが差別化の中心になってくるのかもしれません。
2023.03.17
SVB破綻
米国の地銀3行が連鎖的に破綻しました。中でもSVB(シリコンバレーバンク)はシリコンバレーにおけるエコシステム(生態系)の金融面での中心的存在であったため、破綻による影響は計り知れないものとなっていたはずです。また同様の銀行破綻が広がればシステミックリスクに発展することも危惧されたため米国政府はFRB、FDIC(連邦預金保険公社)と連携して素早く救済に動き3行の預金は全額保護を打ち出しました。
一番の問題は今後同じような銀行破綻が広がってゆき、リーマンショックのような破壊的事態に陥る恐れはないのかというところにあります。今回の地銀3行破綻の共通項はコロナ下の現金給付で過剰に分配された資金が銀行の預金に集まりながら、その運用にふさわしい額の融資先が確保できていなかったことにあると思われます。スタートアップや暗号資産等は融資による資金ニーズが減少していたことに加え、政策金利の急激な上昇により高騰した貸付金利が借りにくくなっていたからです。
融資先に代わる運用先として当該地銀は米国債やMBS等による運用に頼りました。ところがインフレ対策により金利が上がり続けた為、保有していた債券の価格が下落します。(債券は利回りが上昇すると価格は下落)本来、債券価格は満期まで保有すれば100%の価格で帰ってくることになっています。従ってあえて途中売却する必要のない銀行であれば満期まで持っていれば問題は起きません。ところがSVBは保有する債券の売却を発表した為、含み損が一挙に実現して問題がクローズアップされてしまいました。
預金者の60%がテックやヘルス系の企業であったため、一度銀行が危ないとなると個人が預金者の場合に比べ急激な引き出しが起こるというのも破綻が早まった理由と言えます。今後同様の破綻を防ぐにはどうしたらよいか、なかなか難しい問題ですが、少なくとも銀行の本業である貸付と預金の金利スプレッド(金利差)が十分に確保できており、実質的過小資本に陥っていないことは必要条件と言えるのではないでしょうか。
二番目の問題は今後のシリコンバレーの行く末です。米国の強さの一端がシリコンバレーにあるのは言うまでもありません。これまで当地におけるヒト、カネ、知識、経験等のエコシステムが大きな挑戦を受けてきたことは無かったと思われます。SVBのスポンサーが早く決まるのか予断を許さない状況にあるようなので、エコシステムの一環が不十分なままでこれまでのような運営が継続できるのかが危惧されます。
スタートアップ企業の運営には、テクノロジー等についての深い知識とその分野で様々な経験を積んできたメンター(助言者)となりうる人材が不可欠です。また様々なリスクを乗り越えて上場にこぎつけるまで必要とされる、膨大な資金の供給が欠かせません。従ってスポンサーには資金量の大きさや会計、金融の知識のみならずテック業界等の先行き見極めの能力が問われます。残念ながらそのような銀行は米国にも多くはないと思われます。SVBの破綻は単なる地銀の行き詰まりを遥かに超える一大事として米国の光に影を投げかけています。
一番の問題は今後同じような銀行破綻が広がってゆき、リーマンショックのような破壊的事態に陥る恐れはないのかというところにあります。今回の地銀3行破綻の共通項はコロナ下の現金給付で過剰に分配された資金が銀行の預金に集まりながら、その運用にふさわしい額の融資先が確保できていなかったことにあると思われます。スタートアップや暗号資産等は融資による資金ニーズが減少していたことに加え、政策金利の急激な上昇により高騰した貸付金利が借りにくくなっていたからです。
融資先に代わる運用先として当該地銀は米国債やMBS等による運用に頼りました。ところがインフレ対策により金利が上がり続けた為、保有していた債券の価格が下落します。(債券は利回りが上昇すると価格は下落)本来、債券価格は満期まで保有すれば100%の価格で帰ってくることになっています。従ってあえて途中売却する必要のない銀行であれば満期まで持っていれば問題は起きません。ところがSVBは保有する債券の売却を発表した為、含み損が一挙に実現して問題がクローズアップされてしまいました。
預金者の60%がテックやヘルス系の企業であったため、一度銀行が危ないとなると個人が預金者の場合に比べ急激な引き出しが起こるというのも破綻が早まった理由と言えます。今後同様の破綻を防ぐにはどうしたらよいか、なかなか難しい問題ですが、少なくとも銀行の本業である貸付と預金の金利スプレッド(金利差)が十分に確保できており、実質的過小資本に陥っていないことは必要条件と言えるのではないでしょうか。
二番目の問題は今後のシリコンバレーの行く末です。米国の強さの一端がシリコンバレーにあるのは言うまでもありません。これまで当地におけるヒト、カネ、知識、経験等のエコシステムが大きな挑戦を受けてきたことは無かったと思われます。SVBのスポンサーが早く決まるのか予断を許さない状況にあるようなので、エコシステムの一環が不十分なままでこれまでのような運営が継続できるのかが危惧されます。
スタートアップ企業の運営には、テクノロジー等についての深い知識とその分野で様々な経験を積んできたメンター(助言者)となりうる人材が不可欠です。また様々なリスクを乗り越えて上場にこぎつけるまで必要とされる、膨大な資金の供給が欠かせません。従ってスポンサーには資金量の大きさや会計、金融の知識のみならずテック業界等の先行き見極めの能力が問われます。残念ながらそのような銀行は米国にも多くはないと思われます。SVBの破綻は単なる地銀の行き詰まりを遥かに超える一大事として米国の光に影を投げかけています。
2023.02.09
異次元が生むもの
インフレによって物価が高騰しており、生活を守るためにはインフレ率を上回る賃金を確保する必要があると言われています。企業も賃上げには賛成の意向を示しているものの、一部の大企業を除いて実現はなかなか厳しいのが現実です。仕入れ物価も上昇しているなかで、人件費を引き上げれば赤字幅が拡大するだけという中小企業にとっては実現困難な要請であるというのが実感かもしれません。
賃上げの要請に答えるためには、提供する製品やサービスの価格を上げるというのが選択枝ではありますが、消費者にとっては一層の物価上昇となるわけで企業にとっては強い抵抗を受けるだけ。物価と賃金の堂々巡りとなり根本的解決にはなりません。
長年にわたって諸外国と比べて賃金水準が低いままであった日本。その理由は企業の生産性が低い為であると言われています。企業の生産性が上昇すれば問題は解決するということになります。どのようにすれば生産性は大きく上昇させられるのでしょうか。
生産性とは投資(工場設備等)に対してどれだけの成果が生み出されたか、その割合であると言えます。つまりアウトプット/インプットという式で表せます。この数値が高いほど生産性は高くなります。分子のアウトプットが大きく、分母のインプットが小さくできれば生産性は高くなります。
高い生産性を実現している国や業界では異次元の戦略を採っているケースが多くみられます。需要の見込める市場に妥当な価格の製品やサービスを提供するという一般的な方法ではなく目標を、高く売れる製品サービスを提供することに置くという異次元の戦略です。
例えばアップル。製品を高価格で提供するために何が必要かを判断基準としています。アパレル等の有名ブランド品も異次元の価格で売上を伸ばしています。高くとも買いたくなる製品の開発に最優先順位を置いているということです。
サービスの分野では世界を席巻しているグーグル、メタ(フェースブック)等がただで使えるプラットフォームを提供することで、億の単位のユーザーを獲得し、広告で稼ぐという異次元ビジネスモデルを作り出しました。
分母のインプットはどのように異次元となっているでしょうか。現在世界を席巻している企業の始まりは殆どが小さなベンチャー企業です。一人か二人の人材がガレージに泊まり込んで作り出した企業なので、コストはなきに等しいほどのものでしょう。
ただ、並みの企業との違いは世の中にないもの、大きな需要が見込める分野を見つけ出し、アイディアと開発力で世界中の人々が喜んで使えるような製品を作り上げたところにあると思われます。企業規模が大きくなっても技術の内製化によりコストを抑え、自社の強みを発揮できる分野にのみ投資を集中しています。
既に世界で圧倒的存在感を示している企業なので、参考にならないと考えられるかもしれませんが、会社を立ち上げたばかりのころ彼らが持っていたのは、異次元のアイディアと情熱、知識くらいのものだったと言っても過言ではないでしょう。
物価が上昇してくると、安く売ってくれる企業が消費者の味方と思えてきますが、企業が現状維持なら家計に回る賃金上昇は夢のまた夢。企業が目指すべきは異次元の生産性を何としてでも実現するアイディアと人材の確保にあると思われます。
賃上げの要請に答えるためには、提供する製品やサービスの価格を上げるというのが選択枝ではありますが、消費者にとっては一層の物価上昇となるわけで企業にとっては強い抵抗を受けるだけ。物価と賃金の堂々巡りとなり根本的解決にはなりません。
長年にわたって諸外国と比べて賃金水準が低いままであった日本。その理由は企業の生産性が低い為であると言われています。企業の生産性が上昇すれば問題は解決するということになります。どのようにすれば生産性は大きく上昇させられるのでしょうか。
生産性とは投資(工場設備等)に対してどれだけの成果が生み出されたか、その割合であると言えます。つまりアウトプット/インプットという式で表せます。この数値が高いほど生産性は高くなります。分子のアウトプットが大きく、分母のインプットが小さくできれば生産性は高くなります。
高い生産性を実現している国や業界では異次元の戦略を採っているケースが多くみられます。需要の見込める市場に妥当な価格の製品やサービスを提供するという一般的な方法ではなく目標を、高く売れる製品サービスを提供することに置くという異次元の戦略です。
例えばアップル。製品を高価格で提供するために何が必要かを判断基準としています。アパレル等の有名ブランド品も異次元の価格で売上を伸ばしています。高くとも買いたくなる製品の開発に最優先順位を置いているということです。
サービスの分野では世界を席巻しているグーグル、メタ(フェースブック)等がただで使えるプラットフォームを提供することで、億の単位のユーザーを獲得し、広告で稼ぐという異次元ビジネスモデルを作り出しました。
分母のインプットはどのように異次元となっているでしょうか。現在世界を席巻している企業の始まりは殆どが小さなベンチャー企業です。一人か二人の人材がガレージに泊まり込んで作り出した企業なので、コストはなきに等しいほどのものでしょう。
ただ、並みの企業との違いは世の中にないもの、大きな需要が見込める分野を見つけ出し、アイディアと開発力で世界中の人々が喜んで使えるような製品を作り上げたところにあると思われます。企業規模が大きくなっても技術の内製化によりコストを抑え、自社の強みを発揮できる分野にのみ投資を集中しています。
既に世界で圧倒的存在感を示している企業なので、参考にならないと考えられるかもしれませんが、会社を立ち上げたばかりのころ彼らが持っていたのは、異次元のアイディアと情熱、知識くらいのものだったと言っても過言ではないでしょう。
物価が上昇してくると、安く売ってくれる企業が消費者の味方と思えてきますが、企業が現状維持なら家計に回る賃金上昇は夢のまた夢。企業が目指すべきは異次元の生産性を何としてでも実現するアイディアと人材の確保にあると思われます。
2023.01.10
FIRE VS ディオゲネス
FIRE(Financial Independence RetirementEarly)は人が最終的に到達したいと切望するゴールでしょうか。使い切れないほどの金を持っていれば自由が手に入ると考え、働かなくとも好きなことをして暮らせるだけの金を稼ぐことこそユートピアと思い定め、その手段として投資があると考えるのでしょう。
確かに使い切れないほどの金を持っていれば、殆どの苦労や悩み、不安や心配から解放されるのは確かです。やりたいことは何でもできるし、やりたくないことはやらなくとも何の不都合もない。これが経済的自立(financialindependence)のメリットであり、このような自由を手に入れたいと願うのは人間の本性なのかもしれません。投資でこのような境遇を手に入れられるなら、食うための仕事にはとっととおさらばしてしまいたい(retirement early)と望むのも無理はないことかもしれません。
人は誰でも幸せになりたいと願っているので、金で幸せが手に入るのならその為の投資手法を身に着けようと必死になるのも非難されることではないでしょう。さらにその投資手法が仕事を通して手に入れることが出来るならこれこそFIREの到達点と言えるかもしれません。
一方、FIREとはかなり異なる人生を送った人もいます。古代ギリシャにディオゲネスという哲学者がいました。彼は物質的充足には興味がなく樽の中に暮らしていたそうです。ディオゲネスの名声を聞きつけたアレクサンダー大王がディオゲネスの所に赴き、自分の所で働けば何でも望を叶えてつかわそうと提案しました。ディオゲネスは住処である樽の中から「あんたがそこにいると陽があたらないのでどいてくれ。オレの望みはそれだけだ」と言ったと言われています。
ディオゲネスの目的は真理追究であり、他人から指図を受けることは目的達成の邪魔と考えたのでしょう。ぶれることなく目的を追求するために自由を選択した、ということではないでしょうか。
自由を求めるという共通項はありますが、FIREは自由が目的でありその手段が投資ということになります。どちらが良い、悪いとか高級、低級の比較をしたいわけではありません。問題はその人がどのような生き方をしたいのかにかかっているということ。そして与えられた「時間」を何のために使うのかがその人の価値観に繋がっているということです。
一つ気にかかるのはその価値観が、自分の利益の為だけに向いているのか否かということです。金も領土も能力もすべてを持ってマケドニアに君臨していたアレクサンダー大王は「余がもしアレクサンダーでなかったらディオゲネスでありたかった」と語ったといわれています。さすが大王、器量の大きさを感じずにはいられない逸話であります。
確かに使い切れないほどの金を持っていれば、殆どの苦労や悩み、不安や心配から解放されるのは確かです。やりたいことは何でもできるし、やりたくないことはやらなくとも何の不都合もない。これが経済的自立(financialindependence)のメリットであり、このような自由を手に入れたいと願うのは人間の本性なのかもしれません。投資でこのような境遇を手に入れられるなら、食うための仕事にはとっととおさらばしてしまいたい(retirement early)と望むのも無理はないことかもしれません。
人は誰でも幸せになりたいと願っているので、金で幸せが手に入るのならその為の投資手法を身に着けようと必死になるのも非難されることではないでしょう。さらにその投資手法が仕事を通して手に入れることが出来るならこれこそFIREの到達点と言えるかもしれません。
一方、FIREとはかなり異なる人生を送った人もいます。古代ギリシャにディオゲネスという哲学者がいました。彼は物質的充足には興味がなく樽の中に暮らしていたそうです。ディオゲネスの名声を聞きつけたアレクサンダー大王がディオゲネスの所に赴き、自分の所で働けば何でも望を叶えてつかわそうと提案しました。ディオゲネスは住処である樽の中から「あんたがそこにいると陽があたらないのでどいてくれ。オレの望みはそれだけだ」と言ったと言われています。
ディオゲネスの目的は真理追究であり、他人から指図を受けることは目的達成の邪魔と考えたのでしょう。ぶれることなく目的を追求するために自由を選択した、ということではないでしょうか。
自由を求めるという共通項はありますが、FIREは自由が目的でありその手段が投資ということになります。どちらが良い、悪いとか高級、低級の比較をしたいわけではありません。問題はその人がどのような生き方をしたいのかにかかっているということ。そして与えられた「時間」を何のために使うのかがその人の価値観に繋がっているということです。
一つ気にかかるのはその価値観が、自分の利益の為だけに向いているのか否かということです。金も領土も能力もすべてを持ってマケドニアに君臨していたアレクサンダー大王は「余がもしアレクサンダーでなかったらディオゲネスでありたかった」と語ったといわれています。さすが大王、器量の大きさを感じずにはいられない逸話であります。
2022.12.13
リスクを負うべきは誰か
住宅を借金して買った場合、住宅価格下落リスクは誰が負っているでしょうか。不動産は高額なので殆どの場合住宅ローンを組んで(借金して)購入します。問題は返済に行き詰まって住宅を売却せざるを得なくなり、借金額より低い価格でしか売れなかった場合、誰が差額を負担するのかというところにあります。
5000万円で買った物件を10年経って売却したら2000万円でしか売れなかったとします。この時点で借入金の残高が3000万円残っていたとすると、差額1000万円は住宅購入者が負担しなければなりません。住む家を失ったのにさらに1000万円の借金が残ったとなれば、次の仕事が直ぐに見つかりでもしなければ自己破産しか選択肢はなくなるでしょう。日本では住宅価格下落リスクは全額購入者が負うことになっています。
米国には物件価格が下がっても、借入金の返済は売却価格に限定される制度があります。3000万円の残債があっても2000万円返済すれば免責されるというもの。ノンリコースローン(non-recourse loan)と呼ばれ、貸し手側が原資の返済を融資対象の資産以外に求めないという融資方法です。債権者が債務者の人的責任を追及しないのでノンリコース(非遡及)と言われ、物件価格下落リスクを負うのは銀行などの貸し手となります。
しかし事の本質は貸し手がリスクを負担しないことにあるのでしょうか。10年保有した住宅価格が3000万円も下落してしまったところにあるのではないでしょうか。もし5000万円で買った物件が10年後も5000万円もしくはそれ以上で売却できるのであれば不動産にまつわる悲惨な状況はずっと少なくなるはずです。
我が国において中古物件価格は年数の経過とともに下落してゆくのが当然と思われていますが、米国の不動産は長期に保有しても購入価格より価格が上がるのが普通のようです。この違いは法定耐用年数や減価償却等、制度の考え方の違いに因るところが大きいと思われます。
例えば米国の木造建築は、27.5年で償却となっており、所有者が変わればその都度27.5年の償却が出来ることになっています。一方日本は22年経過すると4年で償却することになっているので、まだ十分に使用に耐える住宅であっても税務的には物件価値はゼロとみなされてしまうのです。税務上価値ゼロとなれば当然、市場における売買価格に跳ね返るでしょう。その結果10年で資産価値が3000万円も下落するリスクも、住宅の購入者が負っていることになります。
現在(2022.6末)日本の住宅ローン残高は220兆円を超え過去最大規模になっています。一方住宅の資産額は伸び悩み、直近の20年末は前年比で下落。米国もローンが急増し残高は6月末で12兆ドルを突破していますが、それ以上に住宅の資産額の伸び率が大きい、という統計が出ています。(2022.11.6日経新聞)
買った場所の土地代が上昇しない限り不動産価格は下がるなら、住宅物件には住むこと以外の資産価値はないことになります。日本の住宅所有者が負うリスクは、ローン金利の高低だけによるわけではないということです。
5000万円で買った物件を10年経って売却したら2000万円でしか売れなかったとします。この時点で借入金の残高が3000万円残っていたとすると、差額1000万円は住宅購入者が負担しなければなりません。住む家を失ったのにさらに1000万円の借金が残ったとなれば、次の仕事が直ぐに見つかりでもしなければ自己破産しか選択肢はなくなるでしょう。日本では住宅価格下落リスクは全額購入者が負うことになっています。
米国には物件価格が下がっても、借入金の返済は売却価格に限定される制度があります。3000万円の残債があっても2000万円返済すれば免責されるというもの。ノンリコースローン(non-recourse loan)と呼ばれ、貸し手側が原資の返済を融資対象の資産以外に求めないという融資方法です。債権者が債務者の人的責任を追及しないのでノンリコース(非遡及)と言われ、物件価格下落リスクを負うのは銀行などの貸し手となります。
しかし事の本質は貸し手がリスクを負担しないことにあるのでしょうか。10年保有した住宅価格が3000万円も下落してしまったところにあるのではないでしょうか。もし5000万円で買った物件が10年後も5000万円もしくはそれ以上で売却できるのであれば不動産にまつわる悲惨な状況はずっと少なくなるはずです。
我が国において中古物件価格は年数の経過とともに下落してゆくのが当然と思われていますが、米国の不動産は長期に保有しても購入価格より価格が上がるのが普通のようです。この違いは法定耐用年数や減価償却等、制度の考え方の違いに因るところが大きいと思われます。
例えば米国の木造建築は、27.5年で償却となっており、所有者が変わればその都度27.5年の償却が出来ることになっています。一方日本は22年経過すると4年で償却することになっているので、まだ十分に使用に耐える住宅であっても税務的には物件価値はゼロとみなされてしまうのです。税務上価値ゼロとなれば当然、市場における売買価格に跳ね返るでしょう。その結果10年で資産価値が3000万円も下落するリスクも、住宅の購入者が負っていることになります。
現在(2022.6末)日本の住宅ローン残高は220兆円を超え過去最大規模になっています。一方住宅の資産額は伸び悩み、直近の20年末は前年比で下落。米国もローンが急増し残高は6月末で12兆ドルを突破していますが、それ以上に住宅の資産額の伸び率が大きい、という統計が出ています。(2022.11.6日経新聞)
買った場所の土地代が上昇しない限り不動産価格は下がるなら、住宅物件には住むこと以外の資産価値はないことになります。日本の住宅所有者が負うリスクは、ローン金利の高低だけによるわけではないということです。
2022.11.11
ホームレスになった日
時々行く図書館で「今日ホームレスになった」という本を借りてきました。13人のサラリーマンがホームレスになった足跡を書いたものです。履歴も職種も地位も異なるサラリーマンにインタビューした内容をまとめてあります。それぞれ転落に至った経緯もその後の境遇も異なりますが、時期は示し合わせたように1997年~2003年でした。また殆どの人がまさか自分がホームレスになるとは思っていなかったという共通点もあります。
なぜ、この時期に集中してホームレスへの転落を余儀なくされたのでしょうか。1997~2003年とはどのような年であったのか、見てみましょう。(下記参照)
1997年:アジア通貨危機
1997年: 三洋証券、北海道拓殖銀行、山一証券破綻
1998年:ロシア国債デフォルト、LTCM破綻、長期信用銀行破綻
1999年:大手15行に7.5兆円の公的資金注入
2001.9: 同時多発テロ
2003.3: 米軍イラク侵攻
端的に言うと金融機関の連鎖破綻と、その前後に起きた異常事態が原因。資金の出し手が消滅して、企業の資金繰りが大幅悪化。決済に影響出て金融の機能不全に陥った(システミック・リスク)、という訳です。企業は倒産を回避するため人件費を大幅に削減せざるを得なくなりました。これがこの時期に集中して大リストラが行われた企業側の理由と言えるでしょう。
一方、リストラされた従業員は定期的収入が途絶え、社会情勢も悪化の一途をたどった為、次の仕事も見つからず預金を食いつぶすという状態となります。こうした状況をさらに加速させたのが借金。住宅ローンや、子供の教育費、バブル時の過大な借り入れ等が保有資産を急激に減らし、追い詰められて高金利金融から借りるなどして事態はさらに悪化するという道をたどった人も多数にのぼりました。
日本では過去、大規模な人員整理は行われてきませんでした。企業利益が減った場合、解雇の代わりに給与や賞与の抑制により雇用は守るという、会社と社員が痛みを分かち合うシステムが働いており、また法律も解雇しにくい法制度、裁判制度が実施されてきました。ところが、いよいよ会社が持たないということになったとき雇用維持の慣行が一気に崩れたのです。
これまで従業員の雇用は会社が守ってくれるという前提で働いてきたので、急に解雇という現実を突きつけられたことになります。リストラの洗礼を受けなかった従業員も自分の居場所を守る為に、同僚や先輩、後輩のリストラを強要する立場にまわされ、共に精神的にも大きなダメージを受けざるを得なかったものと思われます。
現在の状況をみていると、1997~2003に状況が似ているという悪い予感がします。しかもそれが世界レベルで発生しています。現在起きていることと当時の共通事象を、年代の順番に沿ってあげてみると(カッコ内に赤字で表示)以下のようになります。
1997年:アジア通貨危機(各国通貨価値下落)、
1997年: 三洋証券、北海道拓殖銀行、山一証券破綻(様々な金融資産を保有する金融機関の破綻リスク懸念)
1998年:ロシア国債デフォルト、LTCM破綻、長期信用銀行破綻
(中国巨大不動産会社の債券デフォルト)
1999年:大手15行に7.5兆円の公的資金注入 (コロナ対策巨額公的資金注入)
2001.9: 同時多発テロ (新型コロナ恐怖、行動制約)
2003.3: 米軍イラク侵攻 (ロシア、ウクライナ侵攻)
現在までのところリストラの直接原因となった金融機関の破綻は起きていません。しかし
世界の株、債券価値44兆ドル減、世界GDPの半分消失(2022.10.2日経新聞)というとて
つもなく大きな資産下落は、世界のどこかでシステミック・リスクを引き起こしてもおかし
くない状況にあります。
世界中でインフレが進み、急激な金利引き上げを余儀なくされているので早晩、景気後退に
突入します。来年あたりは経済のハードランディングを見ることになるかもしれません。
なぜ、この時期に集中してホームレスへの転落を余儀なくされたのでしょうか。1997~2003年とはどのような年であったのか、見てみましょう。(下記参照)
1997年:アジア通貨危機
1997年: 三洋証券、北海道拓殖銀行、山一証券破綻
1998年:ロシア国債デフォルト、LTCM破綻、長期信用銀行破綻
1999年:大手15行に7.5兆円の公的資金注入
2001.9: 同時多発テロ
2003.3: 米軍イラク侵攻
端的に言うと金融機関の連鎖破綻と、その前後に起きた異常事態が原因。資金の出し手が消滅して、企業の資金繰りが大幅悪化。決済に影響出て金融の機能不全に陥った(システミック・リスク)、という訳です。企業は倒産を回避するため人件費を大幅に削減せざるを得なくなりました。これがこの時期に集中して大リストラが行われた企業側の理由と言えるでしょう。
一方、リストラされた従業員は定期的収入が途絶え、社会情勢も悪化の一途をたどった為、次の仕事も見つからず預金を食いつぶすという状態となります。こうした状況をさらに加速させたのが借金。住宅ローンや、子供の教育費、バブル時の過大な借り入れ等が保有資産を急激に減らし、追い詰められて高金利金融から借りるなどして事態はさらに悪化するという道をたどった人も多数にのぼりました。
日本では過去、大規模な人員整理は行われてきませんでした。企業利益が減った場合、解雇の代わりに給与や賞与の抑制により雇用は守るという、会社と社員が痛みを分かち合うシステムが働いており、また法律も解雇しにくい法制度、裁判制度が実施されてきました。ところが、いよいよ会社が持たないということになったとき雇用維持の慣行が一気に崩れたのです。
これまで従業員の雇用は会社が守ってくれるという前提で働いてきたので、急に解雇という現実を突きつけられたことになります。リストラの洗礼を受けなかった従業員も自分の居場所を守る為に、同僚や先輩、後輩のリストラを強要する立場にまわされ、共に精神的にも大きなダメージを受けざるを得なかったものと思われます。
現在の状況をみていると、1997~2003に状況が似ているという悪い予感がします。しかもそれが世界レベルで発生しています。現在起きていることと当時の共通事象を、年代の順番に沿ってあげてみると(カッコ内に赤字で表示)以下のようになります。
1997年:アジア通貨危機(各国通貨価値下落)、
1997年: 三洋証券、北海道拓殖銀行、山一証券破綻(様々な金融資産を保有する金融機関の破綻リスク懸念)
1998年:ロシア国債デフォルト、LTCM破綻、長期信用銀行破綻
(中国巨大不動産会社の債券デフォルト)
1999年:大手15行に7.5兆円の公的資金注入 (コロナ対策巨額公的資金注入)
2001.9: 同時多発テロ (新型コロナ恐怖、行動制約)
2003.3: 米軍イラク侵攻 (ロシア、ウクライナ侵攻)
現在までのところリストラの直接原因となった金融機関の破綻は起きていません。しかし
世界の株、債券価値44兆ドル減、世界GDPの半分消失(2022.10.2日経新聞)というとて
つもなく大きな資産下落は、世界のどこかでシステミック・リスクを引き起こしてもおかし
くない状況にあります。
世界中でインフレが進み、急激な金利引き上げを余儀なくされているので早晩、景気後退に
突入します。来年あたりは経済のハードランディングを見ることになるかもしれません。
2022.10.07
株はどこまで下げるのか
出所 株式マーケットデータ
株式投資において、昨今のような下落が続く局面では、いつまで下げるのか、いつになったら底を打ったと考えられるのか、その見極めが投資のパフォーマンスを決めることになります。インフレでも景気後退でも儲けるのは難しくなりますが、では今後何を見ておけば株価底打ちの予測が可能なのでしょうか。
発表される経済指標は山ほどありますが、一つを選べと言われれば実質金利こそ、というべきでしょう。実質金利の上昇はリスク資産の価値を下げるからです。では米国の実質金利はどうなっていたでしょうか。上のグラフは、実質金利と米国の代表的株価指数S&P500の関係を示しています。実質金利がマイナス入りした2020.3月末以降、株価は真逆の上方に向けて急上昇を続けました。
一方、2022.1月、実質金利が上昇に転じるや、株価は真逆の下落方向に向かい始めています。直近の2022.4月末までは実質金利マイナスが続いていましたが、5月からプラスに転じ9月には1%を超え9月末には1.6%を付けるという急激な上昇となり、このところの株価大幅下げにつながりました。
実質金利を押し上げているもの、それは現状では長期利回りの上昇と考えられます。実質金利=10年債利回りー 予想インフレ率 10年債利回りは米国中央銀行が政策金利0.75%の引き締めを3回連続しており、FRBはインフレ抑制を最優先課題としているので利回り上昇は今後も続くと予想されます。
予想インフレ率は景気動向の指標です。利上げによる将来不安、中国のコロナ対策、ブロック経済化による商品需要の低下等によって景気は今後悪化(予想インフレ率は低下)していくでしょう。この数値の下落が終わり、上昇の局面に入らない限り、景気後退が終わったということにはなりません。
繰り返しますが、実質金利が上昇すると株価は下落するので、実質金利の上昇が止まらない限り株価は下げ止まらないはずです。上式が示すように、実質金利は10年債利回りと予想インフレ率の差で表されるので同数値の上昇が止まるためには、10年債利回り上昇が止まり、予想インフレ率が上昇を始める必要があります。最悪のシナリオは10年債利回り上昇が止まらず、予想インフレ率が低下し続けることであり、これはスタグフレーションを意味します。
株価はPER×EPSで表せますが、実質金利がこの2つの指標にどのような影響を及ぼすかを考えることにより今後の株価の方向を知ることが出来ます。PER(株価収益率)は企業の売上と利益が上昇すれば並行して上昇すると考えられるので、マクロ的にざっくり見ればGDPの上昇率に置き換えられると言えます。
世界のGDPはこのところ一貫して下落方向にあります。GDPを構成する要素の内、大部分を占める消費や投資は今後景気後退が進むとさらに下落せざるを得ません。インフレが政策金利の利上げで収まっていくとしても、利上げの影響による景気後退は避けようがないということでしょう。
EPS(一株利益)についてはどうでしょうか。インフレ時には企業の仕入れ原価が上昇するので、販売価格に転嫁出来なければEPSは下落します。これまでのところ世界的に企業物価指数は消費者物価指数を大幅に上回っているので、企業利益は縮小していくこと、すなわちEPSの下落を示唆しています。
PS X PERの観点からみると残念ながら世界の株価は今後も下落を続けざるを得ないということになります。いつになったら実質金利の上昇を抑え込むことが出来るのか、そこに株価の行く末がかかっているということです。
株式投資において、昨今のような下落が続く局面では、いつまで下げるのか、いつになったら底を打ったと考えられるのか、その見極めが投資のパフォーマンスを決めることになります。インフレでも景気後退でも儲けるのは難しくなりますが、では今後何を見ておけば株価底打ちの予測が可能なのでしょうか。
発表される経済指標は山ほどありますが、一つを選べと言われれば実質金利こそ、というべきでしょう。実質金利の上昇はリスク資産の価値を下げるからです。では米国の実質金利はどうなっていたでしょうか。上のグラフは、実質金利と米国の代表的株価指数S&P500の関係を示しています。実質金利がマイナス入りした2020.3月末以降、株価は真逆の上方に向けて急上昇を続けました。
一方、2022.1月、実質金利が上昇に転じるや、株価は真逆の下落方向に向かい始めています。直近の2022.4月末までは実質金利マイナスが続いていましたが、5月からプラスに転じ9月には1%を超え9月末には1.6%を付けるという急激な上昇となり、このところの株価大幅下げにつながりました。
実質金利を押し上げているもの、それは現状では長期利回りの上昇と考えられます。実質金利=10年債利回りー 予想インフレ率 10年債利回りは米国中央銀行が政策金利0.75%の引き締めを3回連続しており、FRBはインフレ抑制を最優先課題としているので利回り上昇は今後も続くと予想されます。
予想インフレ率は景気動向の指標です。利上げによる将来不安、中国のコロナ対策、ブロック経済化による商品需要の低下等によって景気は今後悪化(予想インフレ率は低下)していくでしょう。この数値の下落が終わり、上昇の局面に入らない限り、景気後退が終わったということにはなりません。
繰り返しますが、実質金利が上昇すると株価は下落するので、実質金利の上昇が止まらない限り株価は下げ止まらないはずです。上式が示すように、実質金利は10年債利回りと予想インフレ率の差で表されるので同数値の上昇が止まるためには、10年債利回り上昇が止まり、予想インフレ率が上昇を始める必要があります。最悪のシナリオは10年債利回り上昇が止まらず、予想インフレ率が低下し続けることであり、これはスタグフレーションを意味します。
株価はPER×EPSで表せますが、実質金利がこの2つの指標にどのような影響を及ぼすかを考えることにより今後の株価の方向を知ることが出来ます。PER(株価収益率)は企業の売上と利益が上昇すれば並行して上昇すると考えられるので、マクロ的にざっくり見ればGDPの上昇率に置き換えられると言えます。
世界のGDPはこのところ一貫して下落方向にあります。GDPを構成する要素の内、大部分を占める消費や投資は今後景気後退が進むとさらに下落せざるを得ません。インフレが政策金利の利上げで収まっていくとしても、利上げの影響による景気後退は避けようがないということでしょう。
EPS(一株利益)についてはどうでしょうか。インフレ時には企業の仕入れ原価が上昇するので、販売価格に転嫁出来なければEPSは下落します。これまでのところ世界的に企業物価指数は消費者物価指数を大幅に上回っているので、企業利益は縮小していくこと、すなわちEPSの下落を示唆しています。
PS X PERの観点からみると残念ながら世界の株価は今後も下落を続けざるを得ないということになります。いつになったら実質金利の上昇を抑え込むことが出来るのか、そこに株価の行く末がかかっているということです。
2022.09.07
異常変動の本質について
2003年Sarsが流行し、感染を避ける為飛行機で移動するビジネスマンが大幅に減少。結果、航空機に対する需要が大幅に落ち込み、使われなくなった飛行機はネバダの砂漠に放置されることとなりました。世界中の航空会社の飛行機が集まり夥しい数に上った為、ネバダ砂漠は飛行機の墓場と化しました。
飛行機がツインタワーに突っ込んだ2001年の同時多発テロ。この時にも航空会社はダメージを被りました。人々はおなじようなテロが起きることを恐れて移動手段として航空機を避けるようになったからであります。
今回コロナによって航空会社はさらに大きなダメージを受けました。またもや航空機の墓場が出現し、航空機ファイナンスリースも打撃を被ります。旅行やビジネスという需要が止まると、航空機は行き場を失い航空会社の収益も大幅減少、航空機を購入してリースとして航空会社に貸与しているリース会社も大きく影響を受けることになります。
多数の航空機が砂漠送りになると、世界経済は示し合わせたように大幅な下降局面を迎えます。今回のコロナ禍においては一部の国だけに留まらず、世界中の航空機が長期にわたって砂漠行きとなり過去とは比べ物にならない悪影響を世界経済に与えました。
今回は世界貿易面でも大変化が進行しつつあります。グローバリゼーションに支えられていた自由貿易が終わりを告げようとしているからです。自由貿易の下では、世界のどこからでも物資を調達出来、どこへでも売れるという経済効率が実現出来ます。この制度の下では企業も国家も自ら最適と判断した場所で経済活動が行えるという大きなメリットがあります。
ところが2022.2月以降、貿易はブロック経済に取って代わられつつあり、民主主義と権威主義によって貿易が分断され始めています。その結果モノの価格は上昇し世界中で発生しているインフレに拍車をかけています。
先日のジャクソンホールにおけるパウエル議長発言が株や円の連続暴落を引き起こしました。(一週間で世界の株式時価総額700兆円減少、円相場は4円近くの下落。)しかし議長発言はインフレ抑制を最優先し、その結果家計や企業にも痛みが及ぶということを明言したに過ぎません。
FRBは利上げを緩和するハズという市場の誤った期待が7月中旬以降の上昇を招き、今回の大幅下落に繋がった原因であったと言えるでしょう。ことの本質は実体経済がどれほど大きく長く影響を受けているかということであり、そのことこそが株や債券、為替の大幅な変動を引き起こしているのです。
インフレ抑制の為、次回9月の会合で再び0.75%の引き上げを行ったとすると3回連続の高政策金利引き上げとなります。これは過去に例のないことで、実現すればいかにこれまでと違った世界が出現しようとしているかの証しとなると言えるでしょう。ヒト、モノ、カネの激しい動きこそが異常変動の本質なのです。
飛行機がツインタワーに突っ込んだ2001年の同時多発テロ。この時にも航空会社はダメージを被りました。人々はおなじようなテロが起きることを恐れて移動手段として航空機を避けるようになったからであります。
今回コロナによって航空会社はさらに大きなダメージを受けました。またもや航空機の墓場が出現し、航空機ファイナンスリースも打撃を被ります。旅行やビジネスという需要が止まると、航空機は行き場を失い航空会社の収益も大幅減少、航空機を購入してリースとして航空会社に貸与しているリース会社も大きく影響を受けることになります。
多数の航空機が砂漠送りになると、世界経済は示し合わせたように大幅な下降局面を迎えます。今回のコロナ禍においては一部の国だけに留まらず、世界中の航空機が長期にわたって砂漠行きとなり過去とは比べ物にならない悪影響を世界経済に与えました。
今回は世界貿易面でも大変化が進行しつつあります。グローバリゼーションに支えられていた自由貿易が終わりを告げようとしているからです。自由貿易の下では、世界のどこからでも物資を調達出来、どこへでも売れるという経済効率が実現出来ます。この制度の下では企業も国家も自ら最適と判断した場所で経済活動が行えるという大きなメリットがあります。
ところが2022.2月以降、貿易はブロック経済に取って代わられつつあり、民主主義と権威主義によって貿易が分断され始めています。その結果モノの価格は上昇し世界中で発生しているインフレに拍車をかけています。
先日のジャクソンホールにおけるパウエル議長発言が株や円の連続暴落を引き起こしました。(一週間で世界の株式時価総額700兆円減少、円相場は4円近くの下落。)しかし議長発言はインフレ抑制を最優先し、その結果家計や企業にも痛みが及ぶということを明言したに過ぎません。
FRBは利上げを緩和するハズという市場の誤った期待が7月中旬以降の上昇を招き、今回の大幅下落に繋がった原因であったと言えるでしょう。ことの本質は実体経済がどれほど大きく長く影響を受けているかということであり、そのことこそが株や債券、為替の大幅な変動を引き起こしているのです。
インフレ抑制の為、次回9月の会合で再び0.75%の引き上げを行ったとすると3回連続の高政策金利引き上げとなります。これは過去に例のないことで、実現すればいかにこれまでと違った世界が出現しようとしているかの証しとなると言えるでしょう。ヒト、モノ、カネの激しい動きこそが異常変動の本質なのです。
2022.08.10
リセッション入り、ボラの出現
インフレにより酷い資産価格の暴落を本年前半経験した米国。そこから1ヶ月が過ぎた7月28日、日本時間21:30、米国GDPが2四半期連続マイナスであったことが判明するやドルが急激に下落を開始。3月中旬115円台であった円ドルレートは一時140円超えまで上昇を続けてきていましたが、この発表を機に一日2円のペースでなんと5営業日連続で下がり続けました。
リセッション(景気後退)確定ととらえたマーケットは、為替のみに止まらず債券相場においても同じように反応しました。(一時3.4%超えまで上昇していた10年債利回りが発表後5営業日連続下げ、一時2.55%割れ。)考えられるリスクがインフレよりもリセッションに移ったと解釈されたようです。
リセッション入りは長短金利の逆転現象(逆イールド)にも表れています。本来債券利回りは期間が長期になるほど高くなるのが道理ですが、現在はこれが大きく逆転しています。例えば本日(2022.8.10)現在、米国10年債利回りは2.79%ですが、2年物米国債は3.26%と逆転しています。
より精度が高いと言われる3ヶ月短期国債と10年国債の比較では、過去8回あったリセッションの全てで事前に利回り逆転が発生しており、1年程度の期間を経てリセッションに突入しいています。(本日現在、3ヶ月短期国債利回りは2.54%)
一方、米国株式市場においてはドルとは逆に3日連続で上昇に転じました。株式市場、債券市場はリセッションよりもインフレ後退への期待が勝ったようです。中央銀行は利上げのペースを落とす方向を期待し、景気後退はまだ先の話と判断したのかもしれません。
しかし、実質金利(10年債と期待インフレ率から導き出される)は株式にとってネガティブな方向を示しています。4月末まではマイナスが続いていましたが、5月以降プラスに転じ、プラス幅を広げてきているので株価には不利な状況となっています。
米国のみならず欧州各国等もインフレとリセッションのせめぎあいの時期に突入しており、これが様々な資産価格のボラティリティー(変動率)を高めています。今後インフレは終息してゆくのか加速するのか、景気後退はどの程度重大なものとなるのか等不確定要素が大きい為、おのずと資産価格の振れ幅は大きくなります。
このようなボラ(変動率上昇)の出現は先行きを見極めきれない投資家の迷いを象徴しているのでしょう。 日本は変動率においてそれほど大きな影響を受けていないように感じられますが、海外の情勢変化はタイムラグを伴って影響が及ぶことは避けられません。ちなみに、本日21:30、7月の米国消費者物価指数が発表されます。再びボラが発生するかもしれません。
リセッション(景気後退)確定ととらえたマーケットは、為替のみに止まらず債券相場においても同じように反応しました。(一時3.4%超えまで上昇していた10年債利回りが発表後5営業日連続下げ、一時2.55%割れ。)考えられるリスクがインフレよりもリセッションに移ったと解釈されたようです。
リセッション入りは長短金利の逆転現象(逆イールド)にも表れています。本来債券利回りは期間が長期になるほど高くなるのが道理ですが、現在はこれが大きく逆転しています。例えば本日(2022.8.10)現在、米国10年債利回りは2.79%ですが、2年物米国債は3.26%と逆転しています。
より精度が高いと言われる3ヶ月短期国債と10年国債の比較では、過去8回あったリセッションの全てで事前に利回り逆転が発生しており、1年程度の期間を経てリセッションに突入しいています。(本日現在、3ヶ月短期国債利回りは2.54%)
一方、米国株式市場においてはドルとは逆に3日連続で上昇に転じました。株式市場、債券市場はリセッションよりもインフレ後退への期待が勝ったようです。中央銀行は利上げのペースを落とす方向を期待し、景気後退はまだ先の話と判断したのかもしれません。
しかし、実質金利(10年債と期待インフレ率から導き出される)は株式にとってネガティブな方向を示しています。4月末まではマイナスが続いていましたが、5月以降プラスに転じ、プラス幅を広げてきているので株価には不利な状況となっています。
米国のみならず欧州各国等もインフレとリセッションのせめぎあいの時期に突入しており、これが様々な資産価格のボラティリティー(変動率)を高めています。今後インフレは終息してゆくのか加速するのか、景気後退はどの程度重大なものとなるのか等不確定要素が大きい為、おのずと資産価格の振れ幅は大きくなります。
このようなボラ(変動率上昇)の出現は先行きを見極めきれない投資家の迷いを象徴しているのでしょう。 日本は変動率においてそれほど大きな影響を受けていないように感じられますが、海外の情勢変化はタイムラグを伴って影響が及ぶことは避けられません。ちなみに、本日21:30、7月の米国消費者物価指数が発表されます。再びボラが発生するかもしれません。
2022.07.06
ぶりの消える日
ぶりは長いこと見なかった変動が発生したときに現れます。特に何年にもわたって発生しなかった歴史的異常事態時に多数のぶりが現れます。ぶりの出現は歴史が繰り返すことの証左でもあります。
中でも世界中を巻き込んで市場を荒らしまわっているぶりがインフレによるもの。米国のインフレ率の高さ(8.6%.2022.6現在)は40年ぶりです。40年前、オイルショックによりインフレ率は10%を超えており、当時FRBのボルカー議長は強烈な金利引き上げを行いました。
現在、パウエル議長もインフレを抑えるのが先決ということで、一挙に政策金利0.75%の利上げを決定しました。通常、利上げ幅は0.25%ずつというのが普通なので如何に現状のインフレリスクを深刻に受け止めているかがわかります。
市場においては、今年の前半期(1~6月)6か月で米国の代表的株価指数S&P500は23%下落し、この下げ幅はなんと52年ぶりとなっています。本年3~6月期は株、債券、原油からビットコインに至るまであらゆるリスク資産が歴史的乱高下に巻き込まれ、米国10年債利回り上昇1.6%は38年ぶり、22円の円安は24年ぶり、逆にドルの強さを表すドル指数は20年ぶりの高さです。
問題のインフレは供給制約から始まりました。コロナ、ロシア制裁への反撃による原油やガス、中国のロックダウンから始まった世界の貿易縮小などです。モノの価格は需要と供給で決まります。この深刻なインフレを抑える為には、供給を増やすか需要を減らすしか方法がありませんが、供給を増やす道筋は複雑で一筋縄ではいきません。
そこで需要を抑える為、まずは金利引き上げということになりますが、急激な引き上げは経済停滞を引き起こします。最近、市場ではリセッション(景気後退)のリスクが取りざたされており、資産価格の下落もリセッションを織り込み始めています。
インフレが収まらず、経済も後退というのは最悪のシナリオです。これを防ぐ方法は経済成長を犠牲にしてでもまずはインフレを抑えることなので、今後も政策金利の引き上げ継続は避けられないと思われます。
しかし困ったことに株、債券、為替など現在の乱高下がインフレによるものなのか、リセッションによるものなのか誰にも判らない状況になっています。直近のデータでは米国の住宅販売は対前年マイナス12%、個人消費も3.1%→1.8%へと大幅下落しているので不動産価格の下落が始まれば、リセッションも本格化が避けられなくなると思われます。
通常インフレに対抗するにはコモディティー指数の買いが有効です。実際、同指数は14年ぶりに29%の上昇を達成しました。しかしリセッションということになると同指数買いによる資産防衛の有効性は一挙に消滅してしまいます。
経済が大きく変動した時に現れる○○年ぶりという表現は、過去に例のない事象が起きた場合には出現しません。歴史的変動という言葉にとって代わられます。ぶりの消える日が近づいているのかもしれません。
中でも世界中を巻き込んで市場を荒らしまわっているぶりがインフレによるもの。米国のインフレ率の高さ(8.6%.2022.6現在)は40年ぶりです。40年前、オイルショックによりインフレ率は10%を超えており、当時FRBのボルカー議長は強烈な金利引き上げを行いました。
現在、パウエル議長もインフレを抑えるのが先決ということで、一挙に政策金利0.75%の利上げを決定しました。通常、利上げ幅は0.25%ずつというのが普通なので如何に現状のインフレリスクを深刻に受け止めているかがわかります。
市場においては、今年の前半期(1~6月)6か月で米国の代表的株価指数S&P500は23%下落し、この下げ幅はなんと52年ぶりとなっています。本年3~6月期は株、債券、原油からビットコインに至るまであらゆるリスク資産が歴史的乱高下に巻き込まれ、米国10年債利回り上昇1.6%は38年ぶり、22円の円安は24年ぶり、逆にドルの強さを表すドル指数は20年ぶりの高さです。
問題のインフレは供給制約から始まりました。コロナ、ロシア制裁への反撃による原油やガス、中国のロックダウンから始まった世界の貿易縮小などです。モノの価格は需要と供給で決まります。この深刻なインフレを抑える為には、供給を増やすか需要を減らすしか方法がありませんが、供給を増やす道筋は複雑で一筋縄ではいきません。
そこで需要を抑える為、まずは金利引き上げということになりますが、急激な引き上げは経済停滞を引き起こします。最近、市場ではリセッション(景気後退)のリスクが取りざたされており、資産価格の下落もリセッションを織り込み始めています。
インフレが収まらず、経済も後退というのは最悪のシナリオです。これを防ぐ方法は経済成長を犠牲にしてでもまずはインフレを抑えることなので、今後も政策金利の引き上げ継続は避けられないと思われます。
しかし困ったことに株、債券、為替など現在の乱高下がインフレによるものなのか、リセッションによるものなのか誰にも判らない状況になっています。直近のデータでは米国の住宅販売は対前年マイナス12%、個人消費も3.1%→1.8%へと大幅下落しているので不動産価格の下落が始まれば、リセッションも本格化が避けられなくなると思われます。
通常インフレに対抗するにはコモディティー指数の買いが有効です。実際、同指数は14年ぶりに29%の上昇を達成しました。しかしリセッションということになると同指数買いによる資産防衛の有効性は一挙に消滅してしまいます。
経済が大きく変動した時に現れる○○年ぶりという表現は、過去に例のない事象が起きた場合には出現しません。歴史的変動という言葉にとって代わられます。ぶりの消える日が近づいているのかもしれません。
2022.05.06
ミセスワタナベ再び?
円安ドル高が早いペースで進んでいます。3月に入って115円から130円近辺へと2か月でなんと15円の上昇。貿易とインフレを加味した実質実効為替レートに至っては過去最低の円安水準です。(同レートが低い時は、外貨が高いことを意味する。)
原因は米国の急激な消費者物価上昇。40年ぶりの高さです。インフレを抑えるためには米国金利をあげざるを得ず、日米の金利差がドル高を招いています。
実質実効為替レートの急激な低下は、過去にもありました。1995年4月、同レートは最高値151.1を付けましたが、その後2003年には110を切り、2008.年秋ごろまでは80~90まで下落しました。こうした状況下では、資産形成には外貨保有が有効。実際この期間、外貨建て投資信託の基準価格は上昇し、ミセスワタナベ(為替取引をする個人の代名詞)は為替で大儲け。2000~2006で4億の利益を得たようです。
2008年以降、実質実効為替レートは円高に転換しています。理由は同年9月のリーマンショック。世界がリスクを取らなくなり(risk off)当時安全度が高いとみなされていた円が買われた為です。ミセスワタナベはこの時期、儲けのチャンスを失ったばかりか、2007年には脱税が発覚して延滞税、重加算税など5億円を負担することになったと報じられました。
過去、世界を揺るがすような事態が起きると円高になるというのが常態化していました。Risk off時の円高もその一つ。これは円が安全資産と見なされていたからですが、その背景には長期に亘る経常収支黒字があります。ところが、日本の経常収支は42年ぶりの赤字に転じる可能性が取りざたされています。原油価格が急激に上昇している為です。経常収支が一転赤字ということになると円安は構造的なものとなりそうです。
自国の通貨が安くなるということは、長期的には国力の低下を意味するのでもろ手を上げて歓迎するようなものではありません。日本はただでも政府債務残高がGDPの250%以上と過剰なので、金利の上昇は日本売りにつながり財政を危険にさらす恐れがあります。
日銀が政策金利を抑えようとしている為、ドル高を加速させているという議論もありますが、日銀の目的はまさかミセスワタナベを儲けさせるためではないでしょう。金利上昇を抑制することで、住宅ローン金利上昇や、企業の借金膨張を防ぐという効果も期待できます。
円安ドル高が進むと、輸入に携わる中小企業には打撃となることは避けられません。対策として為替ヘッジや、ミセスワタナベの世界に踏み込むというのも一つの方法かもしれません。直近の円の実効為替レートは66近辺と過去最低水準にあります。同レートは簡単に言うと通貨の実力と言えるので下げ続けている限り、外貨保有が利益を生む局面にあるということです。ミセスワタナベは再び利益を積み上げているかもしれません。
原因は米国の急激な消費者物価上昇。40年ぶりの高さです。インフレを抑えるためには米国金利をあげざるを得ず、日米の金利差がドル高を招いています。
実質実効為替レートの急激な低下は、過去にもありました。1995年4月、同レートは最高値151.1を付けましたが、その後2003年には110を切り、2008.年秋ごろまでは80~90まで下落しました。こうした状況下では、資産形成には外貨保有が有効。実際この期間、外貨建て投資信託の基準価格は上昇し、ミセスワタナベ(為替取引をする個人の代名詞)は為替で大儲け。2000~2006で4億の利益を得たようです。
2008年以降、実質実効為替レートは円高に転換しています。理由は同年9月のリーマンショック。世界がリスクを取らなくなり(risk off)当時安全度が高いとみなされていた円が買われた為です。ミセスワタナベはこの時期、儲けのチャンスを失ったばかりか、2007年には脱税が発覚して延滞税、重加算税など5億円を負担することになったと報じられました。
過去、世界を揺るがすような事態が起きると円高になるというのが常態化していました。Risk off時の円高もその一つ。これは円が安全資産と見なされていたからですが、その背景には長期に亘る経常収支黒字があります。ところが、日本の経常収支は42年ぶりの赤字に転じる可能性が取りざたされています。原油価格が急激に上昇している為です。経常収支が一転赤字ということになると円安は構造的なものとなりそうです。
自国の通貨が安くなるということは、長期的には国力の低下を意味するのでもろ手を上げて歓迎するようなものではありません。日本はただでも政府債務残高がGDPの250%以上と過剰なので、金利の上昇は日本売りにつながり財政を危険にさらす恐れがあります。
日銀が政策金利を抑えようとしている為、ドル高を加速させているという議論もありますが、日銀の目的はまさかミセスワタナベを儲けさせるためではないでしょう。金利上昇を抑制することで、住宅ローン金利上昇や、企業の借金膨張を防ぐという効果も期待できます。
円安ドル高が進むと、輸入に携わる中小企業には打撃となることは避けられません。対策として為替ヘッジや、ミセスワタナベの世界に踏み込むというのも一つの方法かもしれません。直近の円の実効為替レートは66近辺と過去最低水準にあります。同レートは簡単に言うと通貨の実力と言えるので下げ続けている限り、外貨保有が利益を生む局面にあるということです。ミセスワタナベは再び利益を積み上げているかもしれません。
2022.04.11
インフレがバブル崩壊を加速する
コロナ対策で多量のマネーを市場に注ぎ込んだ世界の中央銀行は資産バブルを想定していたはずです。従って、市場に溢れかえったマネーを急激に吸い上げることには慎重に、というのが一貫した方針でした。バブルを潰せば実体経済に重大な影響が及ぶからです。その後コロナ感染で工場が停止し供給が低下するなどした為、想定外のインフレが発生するに及び、金利の引き上げを早めるとの方針に変更しました。
ところが再び想定外の事態発生。ロシアのウクライナに侵攻により、世界はロシアへの制裁強化を選択せざるを得なくなりました。第三次世界大戦を避けるため取られた手段は経済制裁。ロシアの原油やガスの輸出を止めることがインフレを昂進させる副作用があることは承知の上での制裁です。ウクライナは小麦等農産物の生産で世界の需要の相当部分を賄っていますが、ロシアが黒海を封鎖して海上輸送を止めるという反撃に出ています。こうした様々な作用の結果、世界中で物資が不足、インフレが各国で問題となってきました。すでにいくつかの国では物価上昇を嫌気した反政府運動が広がっていると報じられています。
通常インフレ対策は政策金利の引き上げにより行われます。過去にも原油等の価格上昇によるインフレを鎮静化するため、各国で実施された対策です。今回もインフレだけが問題であるなら、金利引き上げが妥当。ところが資産バブルが収束していない状況で起きてしまったインフレなので、問題はより深刻化します。
収まっていないばかりか目いっぱい膨張したままの状況故、この状況で急激に金利を上げれば株、債券、不動産等の下落、企業倒産、その結果引き起こされる景気後退など、相当なショックを世界経済に与えることになると思われます。しかし逆にこれまでと同じペースでの金利引き上げに終始すればインフレは加速してしまいます。
FRBはインフレとバブルの両方に対処しなければならない難しい問題に直面しています。最近のFRBコメントによると、インフレ対策を優先させるべく金利引き上げ、金融引き締め(QT)にも5月には着手する方向とあります。QTにより中央銀行がコロナ対策で大量に買い込んだ長期国債等を売却することになるので債券価格は下落、債券利回りは上昇し金利上昇につながります。これはバブル崩壊の後押しを意味します。
最近になって世界経済へのリスク要因がもう一つ加わりました。中国の経済後退です。コロナ再拡大で人流を止めている結果、国内需要が減少し世界貿易も縮小。中国の経済はロシアの比ではないほど巨大であり、日本との経済的つながりも大きい。不動産価格下落問題も依然として解消されていないようなので中国のみならず世界への悪影響が懸念されます。
これまで、上記にあげたような出来事が1つでもあれば世界は揺れ、市場は大きく反応してきました。今回のように複合的な危機の連鎖はどのような結末をもたらすのでしょうか。
過去のショックの原因が比較的透明度の高いものであったことと比較すると、これまでの延長線といった楽観的予測に基づく行動は控えるべきと思います。幸いコロナに関しては危機が回避され、世界がコロナ前の日常を取り戻しつつあります。このトレンドを可能な限り、広く、長く、深く継続させることが当面の取りうる数少ない対策の一つではないでしょうか。
日本は諸外国に比べコロナから経済への移行が遅れ、未だに回復過程に入っているとはいいがたい状況にあります。米国のインフレへの対策転換は当然日本にも大きな影響を及ぼすことでしょう。従ってドラスティックな規制緩和を進めなければまずい事態に陥ることが憂慮されます。海外との人の往来を過度に制約する対策は早急に改める等、社会経済活動の後押しを強力に押し進める局面に来ているのではないでしょうか。
ところが再び想定外の事態発生。ロシアのウクライナに侵攻により、世界はロシアへの制裁強化を選択せざるを得なくなりました。第三次世界大戦を避けるため取られた手段は経済制裁。ロシアの原油やガスの輸出を止めることがインフレを昂進させる副作用があることは承知の上での制裁です。ウクライナは小麦等農産物の生産で世界の需要の相当部分を賄っていますが、ロシアが黒海を封鎖して海上輸送を止めるという反撃に出ています。こうした様々な作用の結果、世界中で物資が不足、インフレが各国で問題となってきました。すでにいくつかの国では物価上昇を嫌気した反政府運動が広がっていると報じられています。
通常インフレ対策は政策金利の引き上げにより行われます。過去にも原油等の価格上昇によるインフレを鎮静化するため、各国で実施された対策です。今回もインフレだけが問題であるなら、金利引き上げが妥当。ところが資産バブルが収束していない状況で起きてしまったインフレなので、問題はより深刻化します。
収まっていないばかりか目いっぱい膨張したままの状況故、この状況で急激に金利を上げれば株、債券、不動産等の下落、企業倒産、その結果引き起こされる景気後退など、相当なショックを世界経済に与えることになると思われます。しかし逆にこれまでと同じペースでの金利引き上げに終始すればインフレは加速してしまいます。
FRBはインフレとバブルの両方に対処しなければならない難しい問題に直面しています。最近のFRBコメントによると、インフレ対策を優先させるべく金利引き上げ、金融引き締め(QT)にも5月には着手する方向とあります。QTにより中央銀行がコロナ対策で大量に買い込んだ長期国債等を売却することになるので債券価格は下落、債券利回りは上昇し金利上昇につながります。これはバブル崩壊の後押しを意味します。
最近になって世界経済へのリスク要因がもう一つ加わりました。中国の経済後退です。コロナ再拡大で人流を止めている結果、国内需要が減少し世界貿易も縮小。中国の経済はロシアの比ではないほど巨大であり、日本との経済的つながりも大きい。不動産価格下落問題も依然として解消されていないようなので中国のみならず世界への悪影響が懸念されます。
これまで、上記にあげたような出来事が1つでもあれば世界は揺れ、市場は大きく反応してきました。今回のように複合的な危機の連鎖はどのような結末をもたらすのでしょうか。
過去のショックの原因が比較的透明度の高いものであったことと比較すると、これまでの延長線といった楽観的予測に基づく行動は控えるべきと思います。幸いコロナに関しては危機が回避され、世界がコロナ前の日常を取り戻しつつあります。このトレンドを可能な限り、広く、長く、深く継続させることが当面の取りうる数少ない対策の一つではないでしょうか。
日本は諸外国に比べコロナから経済への移行が遅れ、未だに回復過程に入っているとはいいがたい状況にあります。米国のインフレへの対策転換は当然日本にも大きな影響を及ぼすことでしょう。従ってドラスティックな規制緩和を進めなければまずい事態に陥ることが憂慮されます。海外との人の往来を過度に制約する対策は早急に改める等、社会経済活動の後押しを強力に押し進める局面に来ているのではないでしょうか。
2022.03.09
ロシア兵糧攻めの帰結
歴史上幾多の戦いにおいて、流血を伴わず勝敗を決する方法として兵糧攻めが多く使われました。敵の城を取り囲み、立てこもる敵方の食料が尽きて降服するのを待つというものです。ロシアのウクライナ侵攻に際して、米欧日がロシアに対し、武力を行使せずどのように対処できるのか世界が見守ってきました。今回の国家間争いにおいて、兵糧に変えて同じような効果を果たしたのがカネであります。
過去の国家間の争い開始時には、物資の供給を止めるというのが常套手段でした。この方法だと効果が出るのに時間がかかり、武力をもって攻め込んだロシアからウクライナを守るには悠長すぎます。
今回、物資に変えて使われたのが、SWIFTからの排除と外貨準備金の凍結。前者は送金などの機能を止めることで経済制裁として働き、その結果ルーブル安が起こってインフレを誘発します。後者は中央銀行によるルーブルの買い支えを阻止することになるので、通貨下落が止まらなくなるという効果があります。
カネへの制裁に加えて、モノへの制裁も行われることになりました。ロシアへの貨物は欧州の税関でストップがかかり西欧の港からの物資搬入は実質的に困難となっています。米欧日諸国のとった今回の対応は過去に例を見ない強烈な効果を発揮するでしょうが、一方で返り血を浴びることも避けられません。原油やガス、穀物、鉱物などの価格上昇によるインフレ昂進、市場混乱による景気後退等を覚悟しなければならないでしょう。
しかし、そうした犠牲を払ってでもウクライナの主権を守ることを選択した世界の見識は、過去の争いが無駄ばかりではなかったことの証左といえるのではないでしょうか。
ただしこうした制裁は何の罪もない国民にとっては大変な迷惑です。ロシア国内には激しいインフレ、保有通貨の下落、経済の縮小、物資の不足、情報の途絶などを引き起こし、まともな生活を送ることが困難となります。当然のことながら、ウクライナの国民はさらに厳しい命への危機にさらされ続けます。何百万の人々を難民として受け入れているポーランド等の隣国も過剰な負担を耐えねばなりません。
世界経済には、コロナによる供給制約に加えて紛争による供給制約が覆いかぶさることになります。インフレのみならず金融資産下落を始めとする経済停滞リスクが加わるので、スタグフレーション(景気停滞と物価上昇の同時進行)がより現実味をおびてくるでしょう。その行く末は、紛争が早期に収束となるか否かにかかっています。
ロシアへの制裁に歩調を合わせた日本ですが、ウクライナ支援についてはどうでしょうか。西欧諸国とともに日本もウクライナからの難民受け入れ表明を期待したいところです。家族が国内にいるかどうかはこの際関係ないと思います。(もちろん家族がいる人々の受け入れは当然です。)
過去の国家間の争い開始時には、物資の供給を止めるというのが常套手段でした。この方法だと効果が出るのに時間がかかり、武力をもって攻め込んだロシアからウクライナを守るには悠長すぎます。
今回、物資に変えて使われたのが、SWIFTからの排除と外貨準備金の凍結。前者は送金などの機能を止めることで経済制裁として働き、その結果ルーブル安が起こってインフレを誘発します。後者は中央銀行によるルーブルの買い支えを阻止することになるので、通貨下落が止まらなくなるという効果があります。
カネへの制裁に加えて、モノへの制裁も行われることになりました。ロシアへの貨物は欧州の税関でストップがかかり西欧の港からの物資搬入は実質的に困難となっています。米欧日諸国のとった今回の対応は過去に例を見ない強烈な効果を発揮するでしょうが、一方で返り血を浴びることも避けられません。原油やガス、穀物、鉱物などの価格上昇によるインフレ昂進、市場混乱による景気後退等を覚悟しなければならないでしょう。
しかし、そうした犠牲を払ってでもウクライナの主権を守ることを選択した世界の見識は、過去の争いが無駄ばかりではなかったことの証左といえるのではないでしょうか。
ただしこうした制裁は何の罪もない国民にとっては大変な迷惑です。ロシア国内には激しいインフレ、保有通貨の下落、経済の縮小、物資の不足、情報の途絶などを引き起こし、まともな生活を送ることが困難となります。当然のことながら、ウクライナの国民はさらに厳しい命への危機にさらされ続けます。何百万の人々を難民として受け入れているポーランド等の隣国も過剰な負担を耐えねばなりません。
世界経済には、コロナによる供給制約に加えて紛争による供給制約が覆いかぶさることになります。インフレのみならず金融資産下落を始めとする経済停滞リスクが加わるので、スタグフレーション(景気停滞と物価上昇の同時進行)がより現実味をおびてくるでしょう。その行く末は、紛争が早期に収束となるか否かにかかっています。
ロシアへの制裁に歩調を合わせた日本ですが、ウクライナ支援についてはどうでしょうか。西欧諸国とともに日本もウクライナからの難民受け入れ表明を期待したいところです。家族が国内にいるかどうかはこの際関係ないと思います。(もちろん家族がいる人々の受け入れは当然です。)
2022.02.10
不気味な足音
1月の世界株価は連続して大幅に下落しました。米連邦準備制度理事会(FRB)議長パウエル氏の発言をきっかけとしたものですが、3月の利上げ、FRBの抱える9兆ドルもの資産縮小(QT)が視野に入ったことに市場が反応したものでしょう。幸いにもその後、少なからずの企業で増収益の決算発表が連続した為市場は落ち着きを取り戻しています。
ただインフレのペースは上昇しており、米国消費者物価指数は年率7%と40年ぶりの高い水準となりました。インフレが高まり中央銀行が金融引き締めに向かうと、金利の上昇を受けて株価収益率(PER)の高い銘柄は売られます。株価はPERと一株利益(EPS)の積なので、EPSが上昇しなければ(翌期利益が大きく増加する見込みがなければ)株価は下落せざるを得ないことになります。
EPSは二極化しており、特に非製造業は人流抑制の影響を受け続けています。いきなりコロナが消えてなくなりでもしない限り、多くの非製造業は株価の面でも厳しい評価を免れることは難しいと思われます。
3月の15.16日に予定されている連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが決定されれば、次は桁違いのマネーが流れ込んでいるFRB保有資産の縮小が視野に入ってくるとみられます。この意味するところは、これまで金利を引き下げ、国債等の債権を買い続けてきた中央銀行のスタンスが180度逆の方向に向かってゆくことであるので、そのインパクトは相当なものとなることが予想されます。欧州においてもイギリスの中央銀行が利上げに踏み切り、(2月3日)保有資産縮小も開始。欧州中央銀行(ECB)も引き締め方向に方針を転換しています。
過去に経験のない程に膨れ上がった、各国中央銀行による膨大な資産の縮小によりどのようなインパクトがあるのか未体験のゾーン故、不明ではありますが、株や不動産等の資産価格を支えていた土台が少なからず崩れてゆくことになるので何も起こらないということはあり得ないと言えるでしょう。
国内においては、コロナ対策として打ち出された無担保、無利子融資の終了期限が3月末に迫っています。同融資は国のみならず、金融機関も巻き込んだ対策なので期限終了となれば貸出は減り、回収も始まることになると思われます。借入に依存して持ちこたえてきた企業は、厳しい試練に直面することになるのではないでしょうか。
資産バブルを正当化してきたマイナスの実質金利がここに来て、大幅に上昇しています。(21年末の▲1.04→▲0.5%)1か月で0.5%の上昇率は思いの外早く、あたかもバブル崩壊が迫る足音に聞こえます。3月は潮目が変わった月として記憶されることになるかもしれません。
ただインフレのペースは上昇しており、米国消費者物価指数は年率7%と40年ぶりの高い水準となりました。インフレが高まり中央銀行が金融引き締めに向かうと、金利の上昇を受けて株価収益率(PER)の高い銘柄は売られます。株価はPERと一株利益(EPS)の積なので、EPSが上昇しなければ(翌期利益が大きく増加する見込みがなければ)株価は下落せざるを得ないことになります。
EPSは二極化しており、特に非製造業は人流抑制の影響を受け続けています。いきなりコロナが消えてなくなりでもしない限り、多くの非製造業は株価の面でも厳しい評価を免れることは難しいと思われます。
3月の15.16日に予定されている連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが決定されれば、次は桁違いのマネーが流れ込んでいるFRB保有資産の縮小が視野に入ってくるとみられます。この意味するところは、これまで金利を引き下げ、国債等の債権を買い続けてきた中央銀行のスタンスが180度逆の方向に向かってゆくことであるので、そのインパクトは相当なものとなることが予想されます。欧州においてもイギリスの中央銀行が利上げに踏み切り、(2月3日)保有資産縮小も開始。欧州中央銀行(ECB)も引き締め方向に方針を転換しています。
過去に経験のない程に膨れ上がった、各国中央銀行による膨大な資産の縮小によりどのようなインパクトがあるのか未体験のゾーン故、不明ではありますが、株や不動産等の資産価格を支えていた土台が少なからず崩れてゆくことになるので何も起こらないということはあり得ないと言えるでしょう。
国内においては、コロナ対策として打ち出された無担保、無利子融資の終了期限が3月末に迫っています。同融資は国のみならず、金融機関も巻き込んだ対策なので期限終了となれば貸出は減り、回収も始まることになると思われます。借入に依存して持ちこたえてきた企業は、厳しい試練に直面することになるのではないでしょうか。
資産バブルを正当化してきたマイナスの実質金利がここに来て、大幅に上昇しています。(21年末の▲1.04→▲0.5%)1か月で0.5%の上昇率は思いの外早く、あたかもバブル崩壊が迫る足音に聞こえます。3月は潮目が変わった月として記憶されることになるかもしれません。
2022.01.07
判断力とアンテナ
何かを決めなければならない時、事の本質を考えた上で情報を集めるでしょうか。それとも情報を集めた上で、該当しそうな情報を取捨選択して回答を探そうとするでしょうか。問題の本質がわかっているなら、前者のアプローチが正しい解に繋がるのでしょう。しかし、遭遇したことのない問題が発生した場合、本質を見極めるのは容易いことではありません。
例えば今回のコロナ禍に際して、「コロナ対策と経済のどちらを優先すべきか」という問題が常について回っており、感染状況や国によって判断は異なっていました。パンデミックのような状況は先を見通すのが難しい上に、科学的なエビデンスも限られています。出来るだけ安全な策をとろうとするなら、優先順位は「コロナ対策」ということになって、「経済」は後回しというのが日本の実情であったように思われます。
それが正しかったのか否かは判りません。立場や生活環境等によって様々な見方が混在していたというのが事実でしょう。ただ情報に関して言うなら、感染状況についての報道が圧倒的に多く、様々なメディアで毎日のように感染者数や専門家、知識人の意見が開陳されていました。是に対し、行動など規制に伴う経済への影響についての情報は、微々たるものでしかなかったように思います。
このような状況下では、個々人の意見や判断は情報の量に影響されざるを得ません。重要性における情報量や質のアンバランスは、過去においても極めて大きな問題を惹起していたことを示す実例があります。「失敗の本質」という本に詳しいのですが、第二次世界大戦で日本が連合国に負けた大きな理由の一つがレーダーの重要性に対する認識不足でした。高性能レーダーが無かったからではありません。日本には八木レーダーという素晴らしく性能の良いレーダーが存在したのです。ところが軍部はその重要性や有効性に気付いていなかったということです。
負けがこんできた日本は米国の捕虜を尋問。なぜ米国は日本の戦術を把握しているのかと捕虜を尋問しました。捕虜は”yagi radar”だと言ったところ、それはどんなものかと問われて驚いたとのこと。自国の優れた技術に気付かず使いもしなかったところに日本軍の致命的弱点があったわけですが、軍を指揮するトップの中に技術や情報の重要性や優先度を深く理解している者がいなかったことが敗因であるとされています。
国も個人も、精度高く、偏りのない情報を入手することの重要性を忘れてはならないことを示す逸話であります。向かうべき方向が判らなかったとしても、情報によって正しい判断に近づけるはず。判断力は誤りや偏りのない情報にアクセスできるアンテナを必要としているということです。
例えば今回のコロナ禍に際して、「コロナ対策と経済のどちらを優先すべきか」という問題が常について回っており、感染状況や国によって判断は異なっていました。パンデミックのような状況は先を見通すのが難しい上に、科学的なエビデンスも限られています。出来るだけ安全な策をとろうとするなら、優先順位は「コロナ対策」ということになって、「経済」は後回しというのが日本の実情であったように思われます。
それが正しかったのか否かは判りません。立場や生活環境等によって様々な見方が混在していたというのが事実でしょう。ただ情報に関して言うなら、感染状況についての報道が圧倒的に多く、様々なメディアで毎日のように感染者数や専門家、知識人の意見が開陳されていました。是に対し、行動など規制に伴う経済への影響についての情報は、微々たるものでしかなかったように思います。
このような状況下では、個々人の意見や判断は情報の量に影響されざるを得ません。重要性における情報量や質のアンバランスは、過去においても極めて大きな問題を惹起していたことを示す実例があります。「失敗の本質」という本に詳しいのですが、第二次世界大戦で日本が連合国に負けた大きな理由の一つがレーダーの重要性に対する認識不足でした。高性能レーダーが無かったからではありません。日本には八木レーダーという素晴らしく性能の良いレーダーが存在したのです。ところが軍部はその重要性や有効性に気付いていなかったということです。
負けがこんできた日本は米国の捕虜を尋問。なぜ米国は日本の戦術を把握しているのかと捕虜を尋問しました。捕虜は”yagi radar”だと言ったところ、それはどんなものかと問われて驚いたとのこと。自国の優れた技術に気付かず使いもしなかったところに日本軍の致命的弱点があったわけですが、軍を指揮するトップの中に技術や情報の重要性や優先度を深く理解している者がいなかったことが敗因であるとされています。
国も個人も、精度高く、偏りのない情報を入手することの重要性を忘れてはならないことを示す逸話であります。向かうべき方向が判らなかったとしても、情報によって正しい判断に近づけるはず。判断力は誤りや偏りのない情報にアクセスできるアンテナを必要としているということです。
2021.12.08
命を守った人たち
オミクロン株出現で、再びコロナに翻弄される日常に舞い戻らないとは言い切れません。この厄介なウイルスにどこまで対抗出来るのかという課題に対して、今のところ未だ答えが出ていません。ようやくコロナの恐怖から解放され、普通の生活に戻ることが出来ると期待していた矢先の新型コロナの出現。不安や落胆を感じている人も少なくないと思われます。
今後の世界がどのような方向に向かうのか、はっきりしたことは誰にもわからないと思いますが、初めてコロナが出現した後、世界はこれにどのように立ち向かってきたのでしょうか。良く分からないままに、そんなものかと受け止めてきた幾つかの「ナゼ」について資料を元に答えを探してみました。
その結果、今日に至るまで、壮絶なドラマが繰り広げられていたことを知りました。中でも感動したのはワクチン開発、製品化に携わってきた研究者の情熱と良心です。そうしたものがなかったら、我々はいまだに更に悲惨な状況におかれていたことでしょう。将来への示唆となるかもしれない出来事として今後の参考になれば幸いです。
① なぜ薬を1つも出したことのないベンチャー企業(ビオンテック/モデルナ)が効果抜群のワクチンを開発、提供できたのか。
・mRNA(メッセンジャーRNA:ウイルスのたんぱく質を作るもとになる、遺伝子情報)が医療を変える可能性のある重要な分野であると信じ、実用化に向けて30年近く前から研究を進めていた。
・カタリン・カリコー博士(ハンガリー出身女性、現ビオンテック上席副社長)はmRNAの研究のため、アメリカのペンシルバニア大学に赴任。開発には資金が必要だが、なかなか成果に結びつかず、当初大きな関心を示していた資金提供者達も次第に興味を失っていった。上司からも他の分野の研究に移るか、降格のどちらかを選択するよう言い渡される。そのような状況下にも拘わらず、mRNAは多くの人類を救済できるとの信念に基づき、降格を受け入れ研究を続けた。この信念と情熱がなければ、有効なワクチンがこんなにも早く作られ、世に出ていたかどうか疑問。
・モデルナもビオンテックも開発が失敗したら、経済的にも信用面でも大打撃を受けるというリスクを冒して進行中の開発案件を全て中止。コロナワクチンの開発、製造に全精力を投入することを決断した。
② ワクチンの開発に10年はかかると言われていたが、なぜ1年で世に出すことが出来たのか。
伝統的ワクチンは、対象となるウイルスを特定し、培養し、不活性化するといった開発プロセスを経る為長い時間がかかる。mRNAワクチンはそれを省けるばかりでなく化学合成出来るので量産化スピードも速い。(ワクチンとは、体に入ってきた悪いウイルスを免疫システムに事前に教える薬。そのため、従来は病原性を弱めたウイルスや、ウイルスを構成するたんぱく質を精製したものを使用。一方mRNAワクチンはウイルスたんぱく質そのものではなく、トゲ(スパイクたんぱく質)に的を絞りその設計図を体内に届け、自分でたんぱく質を作ってもらう仕組みをとる。)
・最初に武漢のコロナ患者の肺から採取した体液を調べ、ウイルスの遺伝子構造を解析した中国人、チャン教授がオーストラリア人の同僚に促されてそのデータを世界に向けて公開したこと。(2020.1月)そのおかげで世界中の専門家がワクチンの開発に一斉に取り掛かることが出来た。
・通常、ワクチンの製造は治験(人体に有効で、無害であることの検査)で問題がないことを確認出来て初めて始まる。コロナの影響は測り知れず、また全世界の人々の命に係わるものであったので、製薬会社と協力して治験と製造を同時並行で進めた。医薬品会社にとっては、巨大なリスクがあるが(治験に問題があった場合、製造してしまったワクチンや、製造工場が無駄になる。)米国政府がそのリスクを引き受けることを約束した。
③ なぜ、mRNAの開発に30年も要したのか。
・mRNAが免疫システムの過剰反応を引き起こすため、実験に使ったマウスはことごとく死に、初期の頃は死体の山が出来てしまった。途方に暮れていたカリコー博士が1つの研究論文に出会い、ここに示唆された方法を試してみた。mRNAは4つの構成成分で構成されるが、そのうちウリジンと呼ばれる物資が免疫の過剰反応を誘発することがある、という内容であった。そこでカリコー博士はウリジンをほぼ同一の代替物質に入れ替えたところ免疫攻撃の問題は解決された。
・ベンチャーキャピタルは成功しそうなベンチャー企業には大金を投じるが、治験段階への資金提供には消極的。製薬会社も多くの人に長期的に投与される薬でないと資金供給を渋る傾向。(「死の谷」と呼ばれる)公的部門も画期的研究の初期段階には積極的資金提供を行うが、研究実証の開発段階では支援が細る傾向。規模の小さなテックベンチャーが常に直面する財政上の障壁。
今回参考とした資料:Newsweek日本語版、厚生労働省ホームページ、日経新聞、FINANCIAL
TIMES,BUSINESS WARS(pod cast)等。特にBUSINESS WARSは大いに参考とさせてい
ただきました。
オミクロン対策にも有効と思われること。(以下は上記を踏まえた推測です)
・変異があっても、当該スパイクたんぱく質の設計図を解析ができれば既存ワクチンの有効性検証や新規ワクチン開発可
・mRNAは、4つの構成成分で構成される。アルファ株から変異したデルタ株に対してもmRNAは有効であった。
・コロナに対して世界中で知見とknow howが蓄積されている。(上記2社以外にもオックスフォード大学とアストラゼネカ、ビオンテックと組んだ製薬会社ファイザー、ジョンソン&ジョンソン、その他製薬会社もワクチンのみならず医薬品を開発しつつある。
・新たなワクチンを作る場合でも、既存施設の転用が可能で、時間をかけて新たな製造施設を一から作らなければならないという時間との戦いを回避できる。
今後の世界がどのような方向に向かうのか、はっきりしたことは誰にもわからないと思いますが、初めてコロナが出現した後、世界はこれにどのように立ち向かってきたのでしょうか。良く分からないままに、そんなものかと受け止めてきた幾つかの「ナゼ」について資料を元に答えを探してみました。
その結果、今日に至るまで、壮絶なドラマが繰り広げられていたことを知りました。中でも感動したのはワクチン開発、製品化に携わってきた研究者の情熱と良心です。そうしたものがなかったら、我々はいまだに更に悲惨な状況におかれていたことでしょう。将来への示唆となるかもしれない出来事として今後の参考になれば幸いです。
① なぜ薬を1つも出したことのないベンチャー企業(ビオンテック/モデルナ)が効果抜群のワクチンを開発、提供できたのか。
・mRNA(メッセンジャーRNA:ウイルスのたんぱく質を作るもとになる、遺伝子情報)が医療を変える可能性のある重要な分野であると信じ、実用化に向けて30年近く前から研究を進めていた。
・カタリン・カリコー博士(ハンガリー出身女性、現ビオンテック上席副社長)はmRNAの研究のため、アメリカのペンシルバニア大学に赴任。開発には資金が必要だが、なかなか成果に結びつかず、当初大きな関心を示していた資金提供者達も次第に興味を失っていった。上司からも他の分野の研究に移るか、降格のどちらかを選択するよう言い渡される。そのような状況下にも拘わらず、mRNAは多くの人類を救済できるとの信念に基づき、降格を受け入れ研究を続けた。この信念と情熱がなければ、有効なワクチンがこんなにも早く作られ、世に出ていたかどうか疑問。
・モデルナもビオンテックも開発が失敗したら、経済的にも信用面でも大打撃を受けるというリスクを冒して進行中の開発案件を全て中止。コロナワクチンの開発、製造に全精力を投入することを決断した。
② ワクチンの開発に10年はかかると言われていたが、なぜ1年で世に出すことが出来たのか。
伝統的ワクチンは、対象となるウイルスを特定し、培養し、不活性化するといった開発プロセスを経る為長い時間がかかる。mRNAワクチンはそれを省けるばかりでなく化学合成出来るので量産化スピードも速い。(ワクチンとは、体に入ってきた悪いウイルスを免疫システムに事前に教える薬。そのため、従来は病原性を弱めたウイルスや、ウイルスを構成するたんぱく質を精製したものを使用。一方mRNAワクチンはウイルスたんぱく質そのものではなく、トゲ(スパイクたんぱく質)に的を絞りその設計図を体内に届け、自分でたんぱく質を作ってもらう仕組みをとる。)
・最初に武漢のコロナ患者の肺から採取した体液を調べ、ウイルスの遺伝子構造を解析した中国人、チャン教授がオーストラリア人の同僚に促されてそのデータを世界に向けて公開したこと。(2020.1月)そのおかげで世界中の専門家がワクチンの開発に一斉に取り掛かることが出来た。
・通常、ワクチンの製造は治験(人体に有効で、無害であることの検査)で問題がないことを確認出来て初めて始まる。コロナの影響は測り知れず、また全世界の人々の命に係わるものであったので、製薬会社と協力して治験と製造を同時並行で進めた。医薬品会社にとっては、巨大なリスクがあるが(治験に問題があった場合、製造してしまったワクチンや、製造工場が無駄になる。)米国政府がそのリスクを引き受けることを約束した。
③ なぜ、mRNAの開発に30年も要したのか。
・mRNAが免疫システムの過剰反応を引き起こすため、実験に使ったマウスはことごとく死に、初期の頃は死体の山が出来てしまった。途方に暮れていたカリコー博士が1つの研究論文に出会い、ここに示唆された方法を試してみた。mRNAは4つの構成成分で構成されるが、そのうちウリジンと呼ばれる物資が免疫の過剰反応を誘発することがある、という内容であった。そこでカリコー博士はウリジンをほぼ同一の代替物質に入れ替えたところ免疫攻撃の問題は解決された。
・ベンチャーキャピタルは成功しそうなベンチャー企業には大金を投じるが、治験段階への資金提供には消極的。製薬会社も多くの人に長期的に投与される薬でないと資金供給を渋る傾向。(「死の谷」と呼ばれる)公的部門も画期的研究の初期段階には積極的資金提供を行うが、研究実証の開発段階では支援が細る傾向。規模の小さなテックベンチャーが常に直面する財政上の障壁。
今回参考とした資料:Newsweek日本語版、厚生労働省ホームページ、日経新聞、FINANCIAL
TIMES,BUSINESS WARS(pod cast)等。特にBUSINESS WARSは大いに参考とさせてい
ただきました。
オミクロン対策にも有効と思われること。(以下は上記を踏まえた推測です)
・変異があっても、当該スパイクたんぱく質の設計図を解析ができれば既存ワクチンの有効性検証や新規ワクチン開発可
・mRNAは、4つの構成成分で構成される。アルファ株から変異したデルタ株に対してもmRNAは有効であった。
・コロナに対して世界中で知見とknow howが蓄積されている。(上記2社以外にもオックスフォード大学とアストラゼネカ、ビオンテックと組んだ製薬会社ファイザー、ジョンソン&ジョンソン、その他製薬会社もワクチンのみならず医薬品を開発しつつある。
・新たなワクチンを作る場合でも、既存施設の転用が可能で、時間をかけて新たな製造施設を一から作らなければならないという時間との戦いを回避できる。
2021.11.09
インフレのちスタグフレーション?
久し振りに車に乗ってドライブと思い給油場所を探しました。スタンドの表示を見てガソリンはこんなに高かったかと驚愕。ハイオク/レギュラー/軽油がそれぞれ175/160/145円というのがどのスタンドもほぼ共通価格。少し前の価格と比べると、1ランク上がっている感じです。(ハイオク/レギュラー/軽油が160/145/130円だったような。)
原油価格が上昇しているので仕方のないことではありますが、最近はあらゆるものの価格が上昇し始めています。野菜、ガス、小麦、銅、半導体等。コロナからの経済回復が始まっているので、需要拡大が牽引する良いインフレなら理にかなっています。が、現状は供給不足により価格が上がる悪いインフレの側面が強くなっています。
供給不足の原因は、複合的です。コロナからの回復遅れによる新興国の生産低下、労働力不足による物資の輸送停滞、グリーンへの移行に伴う炭素エネルギーの供給低下等。コロナの影響が落ち着けば、実体経済は順調に元の世界に戻ってゆくだろうと期待していましたが、供給制約による価格上昇というのは意外でした。
景気が悪くなっているのに物価が上がるという現象はスタグフレーションと呼ばれ、1970年代オイルショックに見舞われた多くの先進国で起きています。こうなると金利の急上昇を政策金利で抑え込むことが困難となります。ただ、今のところ供給制約が解消すれば経済は回復してゆくと見込まれており、スタグフレーションは杞憂なのでしょう。
世界は新型コロナ対策で巨額の財政、金融対策を打ってきました。その結果、世界の債務残高はGDPの365%(2020年末.IIFデータ)に至る見通し。政府債務残高はGDP比98.9%、日本は同比率256.5%(2021年。IMF)となっています。
経済規模を超える政府債務残は市場に出回っているカネの量の大きさを表します。これが株を始めとする様々な資産価格を押し上げてきました。もし、なんらかの理由で物価が急激に上昇して政策金利を上げざるを得ない状況に立ち至った場合、膨大な債務の返済に支障をきたす企業や国が多く出てしまいます。
また、中国政府税収の50%超は不動産使用権の売却収入からと言われているので、不動産価格が下落すると経済低迷は避けられません。世界に波及すればスタグフレーションも現実化しそうです。インフレと共に、十分な注意を払いたいポイントです。
2021.10.05
不動産はなぜ怖いのか
不動産投資で利益を出す秘訣は不動産ブームになる前のタイミングで買い、ブームが終わる前に売ることです。当たり前じゃないか、と言われそうですが不動産には特有の特徴があります。単価がとび抜けて高いことです。従って大抵の場合、借入をしなければ買うことができません。
自己資本と借入金を合わせて物件を手に入れる訳ですが、一般的に自分の資金より借入額の方が大きくなります。これは、大きなレバレッジ(少ない資金で大きな額の取引をすること)をかけることと同義です。その上、長期に亘る利息の支払いがついて回ります。売却時の不動産価格が買い価格(支払い利息込み)以上になっていれば、小さな資金で大きく儲けたことになりますが、逆なら出資金は無くなったのに借入金だけが残るという悲惨な状況になります。
ブームが過熱すると加速度的に価格が上昇し、不動産を住居として購入しようと考えている人にとっても手の届かない所に価格が駆け上がる懸念が生まれます。真面目に働いていても家が持てないというのは政治的に大きな問題なので、政府は価格上昇を抑えにかかります。
過去にいくつかの国で行われたのは総量規制。不動産を買い付ける際に銀行が貸し付けるローン金額を一定の枠内に抑え込むものです。いわゆる不動産バブルつぶしの対策ですが、過去の日本で起きたことを見てもわかるように、無理やり需要を押し下げる政策は大きな問題を引き起こします。多額の借り入れをして手に入れた、多くの国民のわずかな資産価格が下がってゆくからです。
不動産価格が下がっても、借入金は減りません。買い手はまだ下がることを期待して中々現れません。売れるまでに時間もかかります。借入金には利息がついて増えてゆくので明るい未来は夢のまた夢。こうした状況が人間心理に与える影響は経済全体に及びます。日本が失われた20年を経験した原因の大きな一つと言えるでしょう。
現在世界にリスクとして認識され始めた中国不動産開発業者の恒大の資金繰り懸念。同社の負債総額は約33兆円ととてつもない大きさで、不動産開発業者にとっても大きな借入金がもたらすリスクは個人と同様です。規模の大きな企業の場合、倒産は社会に与える影響が大きい為、政府から手を差し伸べられることがあります。
しかしながら不動産バブルを政策理念上抑え込みたい習政権の意向を受け、同社への追加貸付には制限がかかっています。債券の利払いに支障をきたしはじめデフォルト(債務不履行)不可避と見られ、世界の株式市場も大きく動揺しました。今のところ事が一開発業者の倒産に限定されるのであれば、リーマンショックのような事態には至らないであろうとの予測が大勢を占めているように見受けられます。
しかしながら、上述のような不動産の特異性により一度破綻が起きると連鎖的に影響が拡大するのもまた事実。中国不動産そのものの価格下落が、世界金融バブル崩壊の端緒となることなく解決されることを切に願いたいと思います。
自己資本と借入金を合わせて物件を手に入れる訳ですが、一般的に自分の資金より借入額の方が大きくなります。これは、大きなレバレッジ(少ない資金で大きな額の取引をすること)をかけることと同義です。その上、長期に亘る利息の支払いがついて回ります。売却時の不動産価格が買い価格(支払い利息込み)以上になっていれば、小さな資金で大きく儲けたことになりますが、逆なら出資金は無くなったのに借入金だけが残るという悲惨な状況になります。
ブームが過熱すると加速度的に価格が上昇し、不動産を住居として購入しようと考えている人にとっても手の届かない所に価格が駆け上がる懸念が生まれます。真面目に働いていても家が持てないというのは政治的に大きな問題なので、政府は価格上昇を抑えにかかります。
過去にいくつかの国で行われたのは総量規制。不動産を買い付ける際に銀行が貸し付けるローン金額を一定の枠内に抑え込むものです。いわゆる不動産バブルつぶしの対策ですが、過去の日本で起きたことを見てもわかるように、無理やり需要を押し下げる政策は大きな問題を引き起こします。多額の借り入れをして手に入れた、多くの国民のわずかな資産価格が下がってゆくからです。
不動産価格が下がっても、借入金は減りません。買い手はまだ下がることを期待して中々現れません。売れるまでに時間もかかります。借入金には利息がついて増えてゆくので明るい未来は夢のまた夢。こうした状況が人間心理に与える影響は経済全体に及びます。日本が失われた20年を経験した原因の大きな一つと言えるでしょう。
現在世界にリスクとして認識され始めた中国不動産開発業者の恒大の資金繰り懸念。同社の負債総額は約33兆円ととてつもない大きさで、不動産開発業者にとっても大きな借入金がもたらすリスクは個人と同様です。規模の大きな企業の場合、倒産は社会に与える影響が大きい為、政府から手を差し伸べられることがあります。
しかしながら不動産バブルを政策理念上抑え込みたい習政権の意向を受け、同社への追加貸付には制限がかかっています。債券の利払いに支障をきたしはじめデフォルト(債務不履行)不可避と見られ、世界の株式市場も大きく動揺しました。今のところ事が一開発業者の倒産に限定されるのであれば、リーマンショックのような事態には至らないであろうとの予測が大勢を占めているように見受けられます。
しかしながら、上述のような不動産の特異性により一度破綻が起きると連鎖的に影響が拡大するのもまた事実。中国不動産そのものの価格下落が、世界金融バブル崩壊の端緒となることなく解決されることを切に願いたいと思います。
2021.09.07
医療崩壊は防げるか
首都圏における感染拡大が止まらず、コロナ感染者用の病床が不足しています。病床確保のため救急や保健所が連絡を入れても空きがないとして断られ、治療を受けられないままに亡くなるという正に災害時の様相を呈しています。
これは経済社会で普通にみられる需要と供給のミスマッチによるもの。早急に治療を受けなければならないという切迫した需要に対して、病床や医療スタッフの供給が追いつかないというものです。このミスマッチを解消するため国はコロナ病床を増やした病院に対して一床あたり1950万(上限)程度の補助金を支払うことにより不足を補うという対策を打ち出しました。
しかしながら、正当な理由(医師・看護師、物資の不足等)があれば国や自治体からの勧告、命令を受けないことになっています。(厚生省ガイドライン)国からの支援金を受け取りながら、コロナ対応に消極的な病院も存在しており、正当理由に当たる病院がどのくらいの数にのぼるのか国も自治体も把握できていないと報じられています。
需給がミスマッチとなった場合、経済界においては価格によって自然にこの差が埋まってゆきます。また最近ではダイナミックプライシングなど、定価を動かすことによってギャップを埋めることが可能となっています。例えば航空機などのように座席数が一定の場合、この数に対して需要が大きければ価格を上げ、少なければ下げるという方法です。
コロナ感染のような緊急を要する医療に対して上記のような需給調整を導入できれば、病床を提供した病院や医療スタッフにはより高い医療費や報酬が支払われます。(現状は定額の診療報酬や給付の引き上げという対策。費用対効果に難点)そうなると、強制やお願いをしなくとも医療スタッフの供給は増えてゆくと思われます。
現状ではコロナ患者に対応出来る体制を早急に作るのが第一優先なので、関係法規によってこうした仕組み導入が制約を受けているなら法律を変えることが優先事項。自治体からはロックダウンが出来るようにしてほしいという要望が出ていると報じられていますが、優先順位が違うのではないでしょうか。
このような変更を実施する場合、病床数やコロナ対応可能な医療関係者の数、空きキャパシティーなどの情報を瞬時的確に把握する必要が欠かせません。IOTやAIなどを駆使してネットで救急や保健所に提供し患者をすぐに搬送できる体制が必要です。(現状はG-MIS、
HER-SYSがありますが医療機関等による人手の入力が必要。緊急性や正確性に難点)
例えばコロナ病床や患者に装着したセンサーでデータ収集、分析を行い、症状の変化を瞬時に把握。病床の空き予測等に使用して、データが即時に医療現場や救急に伝達される等。又コロナ患者のCT画像診断にAIを使用してコロナ肺炎についての医師診断時間を大幅短縮するなどが考えられます。
患者のたらい回しや放置等あってはならないことを防ぐ為にも、デジタル技術を駆使できる体制が医療報酬改定とセットで実現される必要があります。幸いにも9月からはデジタル庁が始動開始となるので大いに期待したいところです。
現在医療に従事している方々は金の為に頑張っているわけではないと信じますが、命をかけている医療者が金銭的にも公平な保障がなされないなら、これも医療崩壊と言うべきではないでしょうか。
これは経済社会で普通にみられる需要と供給のミスマッチによるもの。早急に治療を受けなければならないという切迫した需要に対して、病床や医療スタッフの供給が追いつかないというものです。このミスマッチを解消するため国はコロナ病床を増やした病院に対して一床あたり1950万(上限)程度の補助金を支払うことにより不足を補うという対策を打ち出しました。
しかしながら、正当な理由(医師・看護師、物資の不足等)があれば国や自治体からの勧告、命令を受けないことになっています。(厚生省ガイドライン)国からの支援金を受け取りながら、コロナ対応に消極的な病院も存在しており、正当理由に当たる病院がどのくらいの数にのぼるのか国も自治体も把握できていないと報じられています。
需給がミスマッチとなった場合、経済界においては価格によって自然にこの差が埋まってゆきます。また最近ではダイナミックプライシングなど、定価を動かすことによってギャップを埋めることが可能となっています。例えば航空機などのように座席数が一定の場合、この数に対して需要が大きければ価格を上げ、少なければ下げるという方法です。
コロナ感染のような緊急を要する医療に対して上記のような需給調整を導入できれば、病床を提供した病院や医療スタッフにはより高い医療費や報酬が支払われます。(現状は定額の診療報酬や給付の引き上げという対策。費用対効果に難点)そうなると、強制やお願いをしなくとも医療スタッフの供給は増えてゆくと思われます。
現状ではコロナ患者に対応出来る体制を早急に作るのが第一優先なので、関係法規によってこうした仕組み導入が制約を受けているなら法律を変えることが優先事項。自治体からはロックダウンが出来るようにしてほしいという要望が出ていると報じられていますが、優先順位が違うのではないでしょうか。
このような変更を実施する場合、病床数やコロナ対応可能な医療関係者の数、空きキャパシティーなどの情報を瞬時的確に把握する必要が欠かせません。IOTやAIなどを駆使してネットで救急や保健所に提供し患者をすぐに搬送できる体制が必要です。(現状はG-MIS、
HER-SYSがありますが医療機関等による人手の入力が必要。緊急性や正確性に難点)
例えばコロナ病床や患者に装着したセンサーでデータ収集、分析を行い、症状の変化を瞬時に把握。病床の空き予測等に使用して、データが即時に医療現場や救急に伝達される等。又コロナ患者のCT画像診断にAIを使用してコロナ肺炎についての医師診断時間を大幅短縮するなどが考えられます。
患者のたらい回しや放置等あってはならないことを防ぐ為にも、デジタル技術を駆使できる体制が医療報酬改定とセットで実現される必要があります。幸いにも9月からはデジタル庁が始動開始となるので大いに期待したいところです。
現在医療に従事している方々は金の為に頑張っているわけではないと信じますが、命をかけている医療者が金銭的にも公平な保障がなされないなら、これも医療崩壊と言うべきではないでしょうか。
2021.08.09
無観客の意味
広大なオリンピック会場の観客席は空席のみ。無観客開催と決まったので当然のことではありますが、テレビを見ていて思ったのは、観客が一人もいないというのがなんと異常なことか、ということです。
今や、ライブ映像のネット配信が当たり前となっているので、開会式も競技場でやらずとも各々のパフォーマンスを編集して配信すれば足ります。競技場でやる意義は多くの人々が各国から集まり、会場で繰り広げられるパフォーマンスに感動して拍手や声援を送る、その熱気を共有するところにあるのだと思います。
競技場にいる世界中の人々が発する熱い思いが、テレビやパブリック・ビューイングの画面で伝わり4年に一度の世界を巻き込む感動となるはずでした。無観客というのはこうした圧倒的熱量の欠落です。多くの観客が見守る中、競技をするアスリート達も観客の視線、応援を背に受けて、これまでの努力に基づく成果以上の奇跡ともいうべき力を発揮する場でもあったのではないでしょうか。
オリンピックというのは各国内での激しい競争を勝ち抜いてきたトップ・スリート達が、さらにそれぞれの国の威信をかけて世界一を決める場です。観客はその立会人として自分たちの国や選手にありったけのエールを送ることが許されます。そこで勝つにしろ、残念ながら敗れるにしろ、全力で戦った選手と共に心からの感動を分け合うことの出来る稀有な場所なのです。
コロナ感染拡大防止とオリンピック開催を両立させた結果、本来のオリンピック精神や深い感動が失われ、一人も観客のいない客席は「コロナに打ち勝つことの出来なかった人類」の象徴となってしまったように感じられました。
感染拡大防止を優先するのか、予定通りのオリンピック開催にこだわるのか、このような世論を二分するような二律背反は過去の歴史にも何度も起こっていますが、その都度世論はまとまらず、どうすればよかったのかの結論も出ていません。今回も急激な感染拡大により緊急事態宣言が発出される中でオリンピックを開催しながら、ステイホーム、酒の提供禁止という理解に苦しむ手段もとられています。
感染が爆発的に増えているのは人流が抑制されないからということですが、抑制されないのは緊急事態宣言に対する慣れや疲ればかりなのでしょうか。無観客にしてでもオリンピックはやるのに外出は控え外では飲酒も禁止という措置に納得がいかないというだけのことでしょう。公平、公正と感じられない命令や依頼には効果がないのです。
過去に起きた世論の分断は過去に例のない出来事に端を発しており、従って大多数の世論が納得するような処方箋も示されない中で、政治的に解決を迫られるという困難が伴っています。決断が正しかったのか誤っていたのかは歴史の判断を待たなければなりませんが、少なくとも、一部の利益のため他の犠牲を看過して下された決定は国力の低下を免れないというのが教訓となっていると思われます。
今や、ライブ映像のネット配信が当たり前となっているので、開会式も競技場でやらずとも各々のパフォーマンスを編集して配信すれば足ります。競技場でやる意義は多くの人々が各国から集まり、会場で繰り広げられるパフォーマンスに感動して拍手や声援を送る、その熱気を共有するところにあるのだと思います。
競技場にいる世界中の人々が発する熱い思いが、テレビやパブリック・ビューイングの画面で伝わり4年に一度の世界を巻き込む感動となるはずでした。無観客というのはこうした圧倒的熱量の欠落です。多くの観客が見守る中、競技をするアスリート達も観客の視線、応援を背に受けて、これまでの努力に基づく成果以上の奇跡ともいうべき力を発揮する場でもあったのではないでしょうか。
オリンピックというのは各国内での激しい競争を勝ち抜いてきたトップ・スリート達が、さらにそれぞれの国の威信をかけて世界一を決める場です。観客はその立会人として自分たちの国や選手にありったけのエールを送ることが許されます。そこで勝つにしろ、残念ながら敗れるにしろ、全力で戦った選手と共に心からの感動を分け合うことの出来る稀有な場所なのです。
コロナ感染拡大防止とオリンピック開催を両立させた結果、本来のオリンピック精神や深い感動が失われ、一人も観客のいない客席は「コロナに打ち勝つことの出来なかった人類」の象徴となってしまったように感じられました。
感染拡大防止を優先するのか、予定通りのオリンピック開催にこだわるのか、このような世論を二分するような二律背反は過去の歴史にも何度も起こっていますが、その都度世論はまとまらず、どうすればよかったのかの結論も出ていません。今回も急激な感染拡大により緊急事態宣言が発出される中でオリンピックを開催しながら、ステイホーム、酒の提供禁止という理解に苦しむ手段もとられています。
感染が爆発的に増えているのは人流が抑制されないからということですが、抑制されないのは緊急事態宣言に対する慣れや疲ればかりなのでしょうか。無観客にしてでもオリンピックはやるのに外出は控え外では飲酒も禁止という措置に納得がいかないというだけのことでしょう。公平、公正と感じられない命令や依頼には効果がないのです。
過去に起きた世論の分断は過去に例のない出来事に端を発しており、従って大多数の世論が納得するような処方箋も示されない中で、政治的に解決を迫られるという困難が伴っています。決断が正しかったのか誤っていたのかは歴史の判断を待たなければなりませんが、少なくとも、一部の利益のため他の犠牲を看過して下された決定は国力の低下を免れないというのが教訓となっていると思われます。
2021.07.07
形なきものの価値
株価は市場がつけた会社の価値ですが、多くの場合会社の資産価値(純資産価格)を上回る価格がついています。理由は、数字に表された貸借対照表上の価格以上の価値があると投資家が考えているからです。
形なきものは無形資産と呼ばれています。具体的には経営陣や従業員の質/研究開発等により生み出された知的財産/優れた品質やデザインの製品を産み続ける開発力/長い時間をかけて育まれた評判等により成り立っています。目には見えないこれらの組み合わせが、会社の価値を決め、将来の成長を保証しているといっても過言ではありません。
無形資産の代表的なものとしてブランドがあります。例えばエルメスのケリーバッグなどは定価だと100万〜200万が普通のようで、原材料の革がどんなに高級だとしても定価は原材料費によって正当化できる価格を超えています。何が定価の妥当性を保証しているのでしょうか。
ブランドを保ち続けるための大きなコスト。すなわち様々な媒体を使った宣伝広告費、ブランド名に恥じない品質を保持するための技術料、世界の一等地に旗艦店を出店するための地代、ブランドの背景となる人物や歴史などに裏打ちされたストーリー作りの妙等です。
表参道から原宿方面へ向かう通りの両側には有名ブランド店が軒を連ねています。この辺りは一等地なので地代も相当高額と思われますが、店内を覗いてみても人影はまばら。世の中の仕組みが良くわかっていなかった若かりし頃には、こんな集客でよく店が成り立つものだと不思議に思ったものでした。イメージを上げて、価格を高く保つことで所有者のプライドをくすぐり収益力に繋がるというビジネスモデルは、人間の心理に働きかけるものの典型です。
社会のデジタル化が進むに連れて企業が提供する商品も無形化が進んでいます。知識やノウハウへのアクセスを実現し(Google)多くの人との密接なつながりを提供する(Facebook やTwitter)写真で存在をアピールし(Instagram)セルフ・プロモーション(自己PR)を手軽に行う(YouTube等)こうした多くのサービスは人間の認知欲求(人から認められたいという欲求)を満たすツールとなっており、ブランドと同じように人間心理を巧みにとらえた無形のサービスを提供しています。人間の精神的欲求には限度がないに等しいので、無形資産を利用したビジネスは将来ますます大きな価値を生み出してゆくことでしょう。
生み出された価値は利益に形を変えるので、税金が発生します。これまで法人税は企業や店舗等のある場所をベースに課税されてきました。ところが上記のような企業が提供しているものは形のないサービスです。ネットを通じて世界中に提供されているため莫大な利益を産んでいるにもかかわらず従来の物理的基準ではとらえきれなくなりました。そこで課税基準を消費者のいる場所や地域に変更するような国際的合意が形成されつつあります。税の世界も無形資産を見過ごすことが出来なくなってきています。
形ある資産(純資産)の何倍の値段(株価)がついているかは、PBRという指標で表されています。また会社の生み出す利益が純資産の何パーセントにあたるかはROEで表され、ROEとPBRは正比例の関係にあります。但しROEが一定水準(一般的には8%)以下だとPBRは1で固定されてしまいます。形なきもの(無形資産)が利益上昇に貢献し、会社の価値(株価P)を引き上げるということです。
形なきものは無形資産と呼ばれています。具体的には経営陣や従業員の質/研究開発等により生み出された知的財産/優れた品質やデザインの製品を産み続ける開発力/長い時間をかけて育まれた評判等により成り立っています。目には見えないこれらの組み合わせが、会社の価値を決め、将来の成長を保証しているといっても過言ではありません。
無形資産の代表的なものとしてブランドがあります。例えばエルメスのケリーバッグなどは定価だと100万〜200万が普通のようで、原材料の革がどんなに高級だとしても定価は原材料費によって正当化できる価格を超えています。何が定価の妥当性を保証しているのでしょうか。
ブランドを保ち続けるための大きなコスト。すなわち様々な媒体を使った宣伝広告費、ブランド名に恥じない品質を保持するための技術料、世界の一等地に旗艦店を出店するための地代、ブランドの背景となる人物や歴史などに裏打ちされたストーリー作りの妙等です。
表参道から原宿方面へ向かう通りの両側には有名ブランド店が軒を連ねています。この辺りは一等地なので地代も相当高額と思われますが、店内を覗いてみても人影はまばら。世の中の仕組みが良くわかっていなかった若かりし頃には、こんな集客でよく店が成り立つものだと不思議に思ったものでした。イメージを上げて、価格を高く保つことで所有者のプライドをくすぐり収益力に繋がるというビジネスモデルは、人間の心理に働きかけるものの典型です。
社会のデジタル化が進むに連れて企業が提供する商品も無形化が進んでいます。知識やノウハウへのアクセスを実現し(Google)多くの人との密接なつながりを提供する(Facebook やTwitter)写真で存在をアピールし(Instagram)セルフ・プロモーション(自己PR)を手軽に行う(YouTube等)こうした多くのサービスは人間の認知欲求(人から認められたいという欲求)を満たすツールとなっており、ブランドと同じように人間心理を巧みにとらえた無形のサービスを提供しています。人間の精神的欲求には限度がないに等しいので、無形資産を利用したビジネスは将来ますます大きな価値を生み出してゆくことでしょう。
生み出された価値は利益に形を変えるので、税金が発生します。これまで法人税は企業や店舗等のある場所をベースに課税されてきました。ところが上記のような企業が提供しているものは形のないサービスです。ネットを通じて世界中に提供されているため莫大な利益を産んでいるにもかかわらず従来の物理的基準ではとらえきれなくなりました。そこで課税基準を消費者のいる場所や地域に変更するような国際的合意が形成されつつあります。税の世界も無形資産を見過ごすことが出来なくなってきています。
形ある資産(純資産)の何倍の値段(株価)がついているかは、PBRという指標で表されています。また会社の生み出す利益が純資産の何パーセントにあたるかはROEで表され、ROEとPBRは正比例の関係にあります。但しROEが一定水準(一般的には8%)以下だとPBRは1で固定されてしまいます。形なきもの(無形資産)が利益上昇に貢献し、会社の価値(株価P)を引き上げるということです。
2021.06.07
在庫の過剰は損のもと?
過剰に在庫を持つと、原価率が高くなり利益を圧迫するので適正在庫を心がけなければなりません。一方、在庫が少なすぎると売れる機会を逃してしまい得られたはずの利益を失います。最適な在庫量は、自社の製品に対する社会からのニーズがどのくらいあるのかを的確に判断できるかにかかっています。
これは「言うは易く行うは難し」の典型のようなもので、各社とも試行錯誤を繰り返しています。最近はAIが需要予測に有効との認識に基づき、過去のビッグデータを分析することで最適在庫を算出する企業が増えてきているようです。
AIに頼らずとも適正在庫を保ちコストを的確にコントロールしてきた企業として、トヨタ自動車が挙げられます。「カンバン方式」とよばれ、生産ラインである部品が不足しそうなら看板に表示してメーカーから都度供給してもらうことで、部品在庫を持たずに生産を円滑化する方法として広く海外でも認知されています。
ところが最近になって、適正在庫を追求することが生産の制約となる状況が発生し始めました。自動車産業界を大きく揺さぶっている半導体の世界的不足です。社会の半導体に対する需要はデータセンターや携帯電話等をはじめとする高度な半導体需要において増加の一歩を辿ってきました。台湾のTSMC等、半導体製造企業はフル活動に近い稼働を続けてきましたが利益率の高い高性能半導体の製造を優先させてきたため、自動車用半導体が後回しとなり供給が制約される状況となっています。
半導体の生産は不足しているからすぐに増やすということは容易でなく、需要に追いつくまでには少なくとも2〜3年くらいのタイムラグが出てしまようです。新車の生産が制約された結果、なんと中古車価格が高騰するという事態が発生しました。需要予測にAIを使うというトレンドが起きている中、AIを動かすに必要とされる半導体の需要予測が出来なかったという皮肉な現象の結果です。
コロナワクチンの普及に伴って、様々な分野で需要が一挙に拡大しそうな局面に来ています。一方、供給はすぐに追いつくことが出来ず不足が生じるという事態が今後も増えてくると思われます。在庫不足対策として需要予測が喫緊の課題となりますが、ビッグデータがあって初めて力を発揮するAIに将来の予測は可能でしょうか。過去に例のない今回のような事態には人間の判断力でAIの不足を補うしかないのかもしれません。
世界の経済が正常化する局面においては、在庫の過剰よりも不足が損失につながると腹を括り、十分過ぎるほどの供給量を確保することがひいては利益につながると思われます。
これは「言うは易く行うは難し」の典型のようなもので、各社とも試行錯誤を繰り返しています。最近はAIが需要予測に有効との認識に基づき、過去のビッグデータを分析することで最適在庫を算出する企業が増えてきているようです。
AIに頼らずとも適正在庫を保ちコストを的確にコントロールしてきた企業として、トヨタ自動車が挙げられます。「カンバン方式」とよばれ、生産ラインである部品が不足しそうなら看板に表示してメーカーから都度供給してもらうことで、部品在庫を持たずに生産を円滑化する方法として広く海外でも認知されています。
ところが最近になって、適正在庫を追求することが生産の制約となる状況が発生し始めました。自動車産業界を大きく揺さぶっている半導体の世界的不足です。社会の半導体に対する需要はデータセンターや携帯電話等をはじめとする高度な半導体需要において増加の一歩を辿ってきました。台湾のTSMC等、半導体製造企業はフル活動に近い稼働を続けてきましたが利益率の高い高性能半導体の製造を優先させてきたため、自動車用半導体が後回しとなり供給が制約される状況となっています。
半導体の生産は不足しているからすぐに増やすということは容易でなく、需要に追いつくまでには少なくとも2〜3年くらいのタイムラグが出てしまようです。新車の生産が制約された結果、なんと中古車価格が高騰するという事態が発生しました。需要予測にAIを使うというトレンドが起きている中、AIを動かすに必要とされる半導体の需要予測が出来なかったという皮肉な現象の結果です。
コロナワクチンの普及に伴って、様々な分野で需要が一挙に拡大しそうな局面に来ています。一方、供給はすぐに追いつくことが出来ず不足が生じるという事態が今後も増えてくると思われます。在庫不足対策として需要予測が喫緊の課題となりますが、ビッグデータがあって初めて力を発揮するAIに将来の予測は可能でしょうか。過去に例のない今回のような事態には人間の判断力でAIの不足を補うしかないのかもしれません。
世界の経済が正常化する局面においては、在庫の過剰よりも不足が損失につながると腹を括り、十分過ぎるほどの供給量を確保することがひいては利益につながると思われます。
2021.04.06
銅は金より尊し
今年に入って1オンス1,900ドルであった金の価格が1700ドル近辺へと大きく下がっています。一方、銅などの金属や原油価格は上昇の一途。特に銅の価格は約10年ぶりの高騰局面にあります。ワクチン普及により新型コロナの抑え込みに期待がかかり、景気回復への期待がモノの値段を押し上げているようです。
経済が上向いて金利が上昇する場合、これは良いインフレと言われます。経済上昇は企業収益を押し上げ、労働者への賃金増加につながります。余裕の生まれた家計は消費を増やし、これが再び企業収益を押し上げるという良い循環を産むからです。
一方、このところ米国の長期金利が急上昇してきました。(10年もの国債利回りは1年前0.6%程度でしたが、現在は1.7%前後の水準です。)長期金利=実質金利+予想物価上昇率と表せるので、長期金利の上昇は実質金利と予想物価率の和の上昇結果ということができます。
ここで、予想物価上昇率は良いインフレと言えるのでこの上昇だけが起きているなら問題はありません。ところが実質金利が上昇してその上がり方のほうが大きいということになると穏やかではありません。これまでのところ、実質金利は0を大幅に下回る水準にありこれが世界的株高や金価格の上昇を演出してきたからです。
実質金利がプラスになると金利の付かない「金」は売られることになります。実質金利マイナスは金融資産価格を押し上げる効果があるので、株がここまでは上昇してきたのも理にかなった動きといえるのでしょう。実質金利は上昇してきてはいますが、現時点ではまだマイナスです。マイナスが続いている限り株価には強い味方となり得ますが、プラスに転じる気配が見えてきた頃には注意が必要です。
世界の株式時価総額は106兆ドルとなり(20213末)過去最高を更新、過去1年で約60%上昇。一方、世界の名目GDPは91兆ドル(21年見通し IMF)で世界株式時価総額はGDPの117%です。(以上日経新聞)このパーセンテージはバッフェット指標と呼ばれ、100%を超えると株式価格は要注意水準と言われています。バブルが崩壊しないためには分母のGDPが大きくならなければなりません。
その為にはワクチンが効果を上げ、移動の制約が解除されて消費が大きく拡大すること、及び新たな科学的進歩に向けて企業が設備投資に動くことが鍵となります。経済拡大が原材料への需要を押し上げ、経済成長への良いインフレに導いてくれるなら銅は金より尊しと言えるのではないでしょうか。
経済が上向いて金利が上昇する場合、これは良いインフレと言われます。経済上昇は企業収益を押し上げ、労働者への賃金増加につながります。余裕の生まれた家計は消費を増やし、これが再び企業収益を押し上げるという良い循環を産むからです。
一方、このところ米国の長期金利が急上昇してきました。(10年もの国債利回りは1年前0.6%程度でしたが、現在は1.7%前後の水準です。)長期金利=実質金利+予想物価上昇率と表せるので、長期金利の上昇は実質金利と予想物価率の和の上昇結果ということができます。
ここで、予想物価上昇率は良いインフレと言えるのでこの上昇だけが起きているなら問題はありません。ところが実質金利が上昇してその上がり方のほうが大きいということになると穏やかではありません。これまでのところ、実質金利は0を大幅に下回る水準にありこれが世界的株高や金価格の上昇を演出してきたからです。
実質金利がプラスになると金利の付かない「金」は売られることになります。実質金利マイナスは金融資産価格を押し上げる効果があるので、株がここまでは上昇してきたのも理にかなった動きといえるのでしょう。実質金利は上昇してきてはいますが、現時点ではまだマイナスです。マイナスが続いている限り株価には強い味方となり得ますが、プラスに転じる気配が見えてきた頃には注意が必要です。
世界の株式時価総額は106兆ドルとなり(20213末)過去最高を更新、過去1年で約60%上昇。一方、世界の名目GDPは91兆ドル(21年見通し IMF)で世界株式時価総額はGDPの117%です。(以上日経新聞)このパーセンテージはバッフェット指標と呼ばれ、100%を超えると株式価格は要注意水準と言われています。バブルが崩壊しないためには分母のGDPが大きくならなければなりません。
その為にはワクチンが効果を上げ、移動の制約が解除されて消費が大きく拡大すること、及び新たな科学的進歩に向けて企業が設備投資に動くことが鍵となります。経済拡大が原材料への需要を押し上げ、経済成長への良いインフレに導いてくれるなら銅は金より尊しと言えるのではないでしょうか。
2021.03.09
カードを飲み込むATM
6年前のことです。フランスのニースに夕方到着してユーロを手元に持っておくべく、デパートの一階にあるフランスの某銀行ATMで金を引き出そうとしました。世界中で使える英系のカードを入れ180ユーロをどのような札の組み合わせで引き出すかというボタンを押すも、何か文字が出たまま、札が出てきません。おまけにカードも飲み込まれたまま。すべてのボタンを押してもATMはウンともスンともいわないのでした。
通りかかった親子に事情を話すと、連絡先と書いてあるところに電話してくれたりしたものの、つながりません。親子には英語が通じず、小生のフランス語レベルは小学生以下です。
小生の後にATMで金を下ろしに来た年配の女性は自分のカードで引き出せたようなので、事情を話すと近くにある某銀行の場所を教えてくれ、紙にフランス語で事情を書いてくれるなど、ものすごく親切でした。後になって、飲み込まれたカードは銀行で保管されるということが分かったのですが、そんなことはツユ知らず、誰かの手に渡ってしまったらと思うと気が気ではありません。
やがてデパートのセキュリティー係を捕まえて事情を話し、デパートの受付が銀行に電話。結果、本日銀行は休みなので明日行ってみるようにとのこと。すったもんだの挙句3〜4時間その場にクギ付けとなっていたのでした。
救いはニースの人は皆とても親切だったこと。一般的にフランス人は個人主義で人に冷たいと言われていますがそんなことは全くなく、困っている人を助けようという気持ちは全員共通のものでした。日本で外国人が困っていたら、ここまで親切にしてあげられるでしょうか。
翌日、銀行は休みでも場所だけは確認しておこうと教えられた場所へ。1人行員がおり、説明によるとカードは一週間に一度本店に集められ、そこでしか受け取れないとのこと。本店はプロムナード・デ・ザングレという海岸道路の一本内側にあるとのこと。その場所へ赴き某銀行のベルを鳴らしてみましたが誰も出てきません。
ラッキーなことに某銀行の隣に飲み込まれたカードの発行英系銀行が並んでおり、行ってみると3名勤務中。事情を話したところカードは他行のことなので何ともならないが、現金は用立てることができるということで、セキュリティー上の様々な手続きを経て200ユーロを受け取ることができました。
カードが戻ってくると言われていた、4日後再び某銀行へ。ところがなんとカードは戻ってきておらず、あと1~2週間かかると言われ、危うく日本語で啖呵をきりそうになりました。これまで約8時間余りの時間を費やしたのです。そして明日が帰国予定日。マネージャーの男が言うにはカード発行銀行に行ってopposition(suspend。差し止め)の手続きをとり、その後の手続きは同行でやるようにとのこと。英雄ナポレオンを産んだこの国の銀行の辞書には「不可能の文字」しかないのか、と思い切りイヤミを言ってやりました。
みずほ銀行のATMで飲み込まれたカードが戻ってこず、様々なトラブルが重なって頭取が謝罪するという事態に至りました。その場から動くこともできず途方に暮れた預金者には同情を禁じ得ません。同時に日本の銀行でもこのような不始末がおきたことはまことに残念。原因はよくわかりませんが、どこの国でも起きることのようなので参考のためブログにしておきます。
通りかかった親子に事情を話すと、連絡先と書いてあるところに電話してくれたりしたものの、つながりません。親子には英語が通じず、小生のフランス語レベルは小学生以下です。
小生の後にATMで金を下ろしに来た年配の女性は自分のカードで引き出せたようなので、事情を話すと近くにある某銀行の場所を教えてくれ、紙にフランス語で事情を書いてくれるなど、ものすごく親切でした。後になって、飲み込まれたカードは銀行で保管されるということが分かったのですが、そんなことはツユ知らず、誰かの手に渡ってしまったらと思うと気が気ではありません。
やがてデパートのセキュリティー係を捕まえて事情を話し、デパートの受付が銀行に電話。結果、本日銀行は休みなので明日行ってみるようにとのこと。すったもんだの挙句3〜4時間その場にクギ付けとなっていたのでした。
救いはニースの人は皆とても親切だったこと。一般的にフランス人は個人主義で人に冷たいと言われていますがそんなことは全くなく、困っている人を助けようという気持ちは全員共通のものでした。日本で外国人が困っていたら、ここまで親切にしてあげられるでしょうか。
翌日、銀行は休みでも場所だけは確認しておこうと教えられた場所へ。1人行員がおり、説明によるとカードは一週間に一度本店に集められ、そこでしか受け取れないとのこと。本店はプロムナード・デ・ザングレという海岸道路の一本内側にあるとのこと。その場所へ赴き某銀行のベルを鳴らしてみましたが誰も出てきません。
ラッキーなことに某銀行の隣に飲み込まれたカードの発行英系銀行が並んでおり、行ってみると3名勤務中。事情を話したところカードは他行のことなので何ともならないが、現金は用立てることができるということで、セキュリティー上の様々な手続きを経て200ユーロを受け取ることができました。
カードが戻ってくると言われていた、4日後再び某銀行へ。ところがなんとカードは戻ってきておらず、あと1~2週間かかると言われ、危うく日本語で啖呵をきりそうになりました。これまで約8時間余りの時間を費やしたのです。そして明日が帰国予定日。マネージャーの男が言うにはカード発行銀行に行ってopposition(suspend。差し止め)の手続きをとり、その後の手続きは同行でやるようにとのこと。英雄ナポレオンを産んだこの国の銀行の辞書には「不可能の文字」しかないのか、と思い切りイヤミを言ってやりました。
みずほ銀行のATMで飲み込まれたカードが戻ってこず、様々なトラブルが重なって頭取が謝罪するという事態に至りました。その場から動くこともできず途方に暮れた預金者には同情を禁じ得ません。同時に日本の銀行でもこのような不始末がおきたことはまことに残念。原因はよくわかりませんが、どこの国でも起きることのようなので参考のためブログにしておきます。
2021.01.24
ピンクエレファント
現在進行中の新型コロナショックは、過去の世界大恐慌に勝るとも劣らない経済的損失を世界に与えていますが、当時の惨状と比較すると、悲劇的度合いは随分と穏やかなもので済んでいると感じられます。何がこの差を産んでいるのでしょうか。
当時との一番の違いは株価。大恐慌の折、ニューヨークダウは大暴落となり、殆どの財産を失って路頭に迷う人々が続出しました。先行きを悲観して自ら命を絶つ人もあとを絶たなかったようです。これにひきかえ現在、世界の株価は暴落どころか暴騰しています。株価だけをみるならユーフォリアの体をなしておりこのような状態のとき、世界は明るく見えてきます。しかし、株の時価総額が実体経済を上回るというのは明らかにバブルです。
現在と大恐慌当時の金融環境で一番の大きな違いは何でしょうか。それは市場に出ているカネの量です。大恐慌当時、金本位性がとられており、刷ることのできるカネの量は保有する「金」の量に厳しく制限されていました。その後しばらくたってこの制度は廃止され、刷ることの出来る紙幣の量が物理的に制限されることは無くなりました。
これに代わってカネの流通量を決めているのは、中央銀行(金融)と政府(財政)。そのかじ取りの加減によって経済の過熱を抑えたり、落ち込む景気の下支えをしたりしています。コロナ下にあっては経済が落ち込むので両者が手を携えて恐慌のような状態にならないよう必死の努力を続けています。このような状況下、カネの流通量を減らせば大恐慌の二の舞となることでしょう。
ところでその手綱さばきが効かなかったり裏目に出たりして、市場が大きく揺れ経済が落ち込むというショックを我々は何度か経験してきました。そして何故かそのような事態には動物の名前がつけられています。黒い白鳥とか、灰色のサイ等。黒い白鳥はめったに起こらないが、起きたときには壊滅的被害をもたらす出来事のこと。予測できない金融危機や自然災害について使われています。
灰色のサイは、高い確率で存在し、大きな問題を引き起こすにもかかわらず軽視されがちな問題を指します。サイは灰色が普通で、普段はおとなしい。しかし、暴走し始めると誰も手を付けられなくなることからのネーミングです。今回の新型コロナのような不思議な現象はどのような動物があてはめられるでしょうか。
ピンクの像。。 アルコールや麻薬などによって起きる幻覚症状の婉曲表現。金融も財政も「出来ることは何でもする」という手段に出ているのに需要は激しく落ち込むという、普通ではあり得ない幻覚のような現象です。
政策的にバブルを起こしてでもしてでも実体経済を支えるしかない、原因がどこにあるか明らかなのに経済的には合理的な手が打てない、世界的に厳しい移動制限が一年以上も続く。人類がこれまでに経験したことのない不思議な世界出現です。
嫌なことを、酔ってでも忘れようとするようなもので長期に亘って続くなら副作用は甚大なものとなることでしょう。人の移動を妨げているピンクエレファントには、壊滅的な事態となる前に早く夢の彼方へ消え去ってもらいたいものです。
注:ピンクの像というネーミングは、筆者の妄想に基づくものですので悪しからず。なお、ピンクの像は現実には存在しないそうです。
当時との一番の違いは株価。大恐慌の折、ニューヨークダウは大暴落となり、殆どの財産を失って路頭に迷う人々が続出しました。先行きを悲観して自ら命を絶つ人もあとを絶たなかったようです。これにひきかえ現在、世界の株価は暴落どころか暴騰しています。株価だけをみるならユーフォリアの体をなしておりこのような状態のとき、世界は明るく見えてきます。しかし、株の時価総額が実体経済を上回るというのは明らかにバブルです。
現在と大恐慌当時の金融環境で一番の大きな違いは何でしょうか。それは市場に出ているカネの量です。大恐慌当時、金本位性がとられており、刷ることのできるカネの量は保有する「金」の量に厳しく制限されていました。その後しばらくたってこの制度は廃止され、刷ることの出来る紙幣の量が物理的に制限されることは無くなりました。
これに代わってカネの流通量を決めているのは、中央銀行(金融)と政府(財政)。そのかじ取りの加減によって経済の過熱を抑えたり、落ち込む景気の下支えをしたりしています。コロナ下にあっては経済が落ち込むので両者が手を携えて恐慌のような状態にならないよう必死の努力を続けています。このような状況下、カネの流通量を減らせば大恐慌の二の舞となることでしょう。
ところでその手綱さばきが効かなかったり裏目に出たりして、市場が大きく揺れ経済が落ち込むというショックを我々は何度か経験してきました。そして何故かそのような事態には動物の名前がつけられています。黒い白鳥とか、灰色のサイ等。黒い白鳥はめったに起こらないが、起きたときには壊滅的被害をもたらす出来事のこと。予測できない金融危機や自然災害について使われています。
灰色のサイは、高い確率で存在し、大きな問題を引き起こすにもかかわらず軽視されがちな問題を指します。サイは灰色が普通で、普段はおとなしい。しかし、暴走し始めると誰も手を付けられなくなることからのネーミングです。今回の新型コロナのような不思議な現象はどのような動物があてはめられるでしょうか。
ピンクの像。。 アルコールや麻薬などによって起きる幻覚症状の婉曲表現。金融も財政も「出来ることは何でもする」という手段に出ているのに需要は激しく落ち込むという、普通ではあり得ない幻覚のような現象です。
政策的にバブルを起こしてでもしてでも実体経済を支えるしかない、原因がどこにあるか明らかなのに経済的には合理的な手が打てない、世界的に厳しい移動制限が一年以上も続く。人類がこれまでに経験したことのない不思議な世界出現です。
嫌なことを、酔ってでも忘れようとするようなもので長期に亘って続くなら副作用は甚大なものとなることでしょう。人の移動を妨げているピンクエレファントには、壊滅的な事態となる前に早く夢の彼方へ消え去ってもらいたいものです。
注:ピンクの像というネーミングは、筆者の妄想に基づくものですので悪しからず。なお、ピンクの像は現実には存在しないそうです。
2020.12.08
何が問題なのか。
プリンストン大学のアティフ・ミアン教授によると、最上位1%の富裕層の所得が所得合計に占める割合は15%。また、アマゾンCEOのジェフ・べゾス氏が自分の資産(1450憶ドル)を年5%で運用すると、資産を一銭も減らさずに毎日2000万ドル(21億円)を使うことが可能で、この額は中位個人所得の21万倍に相当するそうです。
大きすぎる経済格差は開いていく一方なので、社会に歪をためこむことになり自由主義などの価値観を覆すことにもなりかねません。人は何とかして資産を築こうと必死に働き、一攫千金を夢見て富裕者への近道を探すことに躍起となるわけで、書店の棚には夢みる人々への指南書や富豪の本が所せましと並んでいます。
格差を是正する方法として税率や課税資産の検討、所得配分による経済的底上げ、医療費の負担軽減策、社会人教育の実現などが考えられますが、もっぱら国の施策に依存することになってしまいます。
ベゾス氏は自力でビジネスを立ち上げ、様々な障害を乗り越えて世界に冠たるアマゾンを築いたわけで、莫大な資産を保有していることに文句を言う人はいないでしょう。また多くの人が、何とかして富裕層の仲間入りをしたいと思うことも非難されるようなことでもないと思います。
富を築く方法についての障害はどこにあるのでしょうか。一般的に社会で言われていることには誤解があるように思います。上記べゾス氏の例に戻ると21万倍もの差が生まれた理由は①1,450億ドルという保有資産②5%の運用利回りです。社会の大多数の認識では①の保有資産が少ないことこそが問題の本質ということになっていないでしょうか。
保有資産の大きさは、起業して大成功をおさめる、宝くじに当たる、などいくつか考えられますが、大金持ちの家に生まれるというのが現実的です。残念ながら生まれる前から決まっていることが殆どです。
誰にでもチャレンジ可能な方法はないでしょうか。べゾス氏の例で挙げた②の運用利回り。ある程度の利回りを出せれば①が少なくとも差は埋められます。一日、21億円はスケールが大きすぎるので、一日2万円入ってくる方法を考えてみましょう。上記の例にならって「資産を一銭も減らさずに」という条件を付けます。
上記の5%は年間の利回りなので一日2万円を年収ベースにすると、2万X365=730万。
いくらの資産があれば永久に毎年730万を手にすることが出来るか、という問い置き換えます。計算は簡単、5%で運用出来るなら730÷0.05=1憶4600万となります。(この計算の正しさは無限等比級数和の公式で証明可。)
現在は預金なら1%でも厳しいのですが、1%で運用出来たとすると、必要額は730÷0.01=7億3000万。もうこの時点で諦めが先に立ち、やはり宝くじか、となります。しかし、もしウオーレン・バフェットのように毎年20%で運用出来るなら必要額は730÷0.2=3650万と一挙により現実的な数字になります。
誰でもバフェットのような実績があげられれば苦労はしないわけですが、ここで言いたいのは保有資産の差を嘆くより自助努力を続けることで格差を埋めていくことができるということです。いくらの資産を持っているかのみ関心を抱く先にあるのは不毛の荒野です。
こつこつと仕事をするのは尊いが、投資で儲けるのは邪道、という考えも未だ社会の常識となっているような気がします。投資にはリスクもつきもので、何にいつ投資をし、損失をどのようにコントロールするか、など課題があり運用力をつけるのは易しいことではありません。しかし資産格差を乗り越える為の具体的方法をとして、真剣に取り組む価値のある分野と言えるのではないでしょうか。
大きすぎる経済格差は開いていく一方なので、社会に歪をためこむことになり自由主義などの価値観を覆すことにもなりかねません。人は何とかして資産を築こうと必死に働き、一攫千金を夢見て富裕者への近道を探すことに躍起となるわけで、書店の棚には夢みる人々への指南書や富豪の本が所せましと並んでいます。
格差を是正する方法として税率や課税資産の検討、所得配分による経済的底上げ、医療費の負担軽減策、社会人教育の実現などが考えられますが、もっぱら国の施策に依存することになってしまいます。
ベゾス氏は自力でビジネスを立ち上げ、様々な障害を乗り越えて世界に冠たるアマゾンを築いたわけで、莫大な資産を保有していることに文句を言う人はいないでしょう。また多くの人が、何とかして富裕層の仲間入りをしたいと思うことも非難されるようなことでもないと思います。
富を築く方法についての障害はどこにあるのでしょうか。一般的に社会で言われていることには誤解があるように思います。上記べゾス氏の例に戻ると21万倍もの差が生まれた理由は①1,450億ドルという保有資産②5%の運用利回りです。社会の大多数の認識では①の保有資産が少ないことこそが問題の本質ということになっていないでしょうか。
保有資産の大きさは、起業して大成功をおさめる、宝くじに当たる、などいくつか考えられますが、大金持ちの家に生まれるというのが現実的です。残念ながら生まれる前から決まっていることが殆どです。
誰にでもチャレンジ可能な方法はないでしょうか。べゾス氏の例で挙げた②の運用利回り。ある程度の利回りを出せれば①が少なくとも差は埋められます。一日、21億円はスケールが大きすぎるので、一日2万円入ってくる方法を考えてみましょう。上記の例にならって「資産を一銭も減らさずに」という条件を付けます。
上記の5%は年間の利回りなので一日2万円を年収ベースにすると、2万X365=730万。
いくらの資産があれば永久に毎年730万を手にすることが出来るか、という問い置き換えます。計算は簡単、5%で運用出来るなら730÷0.05=1憶4600万となります。(この計算の正しさは無限等比級数和の公式で証明可。)
現在は預金なら1%でも厳しいのですが、1%で運用出来たとすると、必要額は730÷0.01=7億3000万。もうこの時点で諦めが先に立ち、やはり宝くじか、となります。しかし、もしウオーレン・バフェットのように毎年20%で運用出来るなら必要額は730÷0.2=3650万と一挙により現実的な数字になります。
誰でもバフェットのような実績があげられれば苦労はしないわけですが、ここで言いたいのは保有資産の差を嘆くより自助努力を続けることで格差を埋めていくことができるということです。いくらの資産を持っているかのみ関心を抱く先にあるのは不毛の荒野です。
こつこつと仕事をするのは尊いが、投資で儲けるのは邪道、という考えも未だ社会の常識となっているような気がします。投資にはリスクもつきもので、何にいつ投資をし、損失をどのようにコントロールするか、など課題があり運用力をつけるのは易しいことではありません。しかし資産格差を乗り越える為の具体的方法をとして、真剣に取り組む価値のある分野と言えるのではないでしょうか。
2020.10.08
Go To 変革キャンペーン
旅行に割安に行けるということで旅に出る人が増えています。宿泊者が蒸発してしまい、一体どうなることかと頭を抱えてきたホテルや旅館もこのキャンペーンのおかげで息を吹き返してきました。 旅行者にも宿泊所にもメリットのある優れた施策であると思います。
ところで、キャンペーンが終わった後も旅行や宿泊関連企業がビジネスを継続していくにはどうしたらよいでしょうか。コロナの影響で大きく変わってきた社会の在り方を今こそ活かし、ピンチをチャンスに変えるタイミングが来ているように思います。
Key wordは平準化です。我が国のホテル、旅館業界においては旅行も宿泊も休日、祝日に集中してしまう為、休祝日こそ利益がでるものの平日はほとんど閑古鳥が鳴いており儲からないというのが一般的な姿。一方、旅行者、宿泊者は混雑しているのに割高な料金を負担することになり、また密を避ける為のソーシャル・ディスタンスもままならずということになります。そこで平準化です。
平日でも多くの人々が訪れ、空室がコンスタントに埋まっているというのが平準化後の姿。
これを実現出来そうなのがワーケーションです。コロナの影響でテレワークせざるを得なくなった企業。どこにいても仕事は出来ることが分かってきたので、働き方改革を取り入れようという国や企業のコンセンサスが出来上がりつつあります。リゾート地に滞在して仕事をしても良い、というのがワーケーション。働く人も自分の都合でいつ、どこで働くかを決めることが可能になるので労働時間の平準化が実現します。
旅行業界と一般企業及び従業員、その双方にメリットが生まれるはずですが、双方に課題もあります。ホテルや旅館は仕事に適した環境の部屋や設備を用意する必要があります。企業は従業員がさぼっているのではないかといった疑念に捕らわれないよう、仕事や評価の制度を整える必要もあるでしょう。具体的には「ジョブ型」雇用制度の導入などとなるでしょうか。これは、職務ごとにジョブ・ディスクリプション(職務記述書)を作ってこれに基づき仕事の成果と評価を明確にするというものです。
ワーケーションが地に足の着いたものとなる為にはホテル、旅館と企業が、日本中(さらには世界中)どこでもこの制度が利用できるよう、需要と供給(企業のワーケーション導入とホテルなどによる場所提供)のマッチングがスムーズに行われる仕組みを作ることが望まれます。
日本は長いこと労働生産性が低いと指摘されてきました。(日本の時間当たりの労働生産性はOECD加盟国36ヵ国中21位)長い時間会社にいれば、仕事をしたような気分になり、会社も長時間労働を当然のことと受け止めてきた環境にあっては、生産性が低くなるのは当然です。大切な自分の時間を有効に使える「平準化」と「ジョブ型」雇用制度への移行。長年変えることのできなかった、会社中心の社会を変革するチャンス到来です。
ところで、キャンペーンが終わった後も旅行や宿泊関連企業がビジネスを継続していくにはどうしたらよいでしょうか。コロナの影響で大きく変わってきた社会の在り方を今こそ活かし、ピンチをチャンスに変えるタイミングが来ているように思います。
Key wordは平準化です。我が国のホテル、旅館業界においては旅行も宿泊も休日、祝日に集中してしまう為、休祝日こそ利益がでるものの平日はほとんど閑古鳥が鳴いており儲からないというのが一般的な姿。一方、旅行者、宿泊者は混雑しているのに割高な料金を負担することになり、また密を避ける為のソーシャル・ディスタンスもままならずということになります。そこで平準化です。
平日でも多くの人々が訪れ、空室がコンスタントに埋まっているというのが平準化後の姿。
これを実現出来そうなのがワーケーションです。コロナの影響でテレワークせざるを得なくなった企業。どこにいても仕事は出来ることが分かってきたので、働き方改革を取り入れようという国や企業のコンセンサスが出来上がりつつあります。リゾート地に滞在して仕事をしても良い、というのがワーケーション。働く人も自分の都合でいつ、どこで働くかを決めることが可能になるので労働時間の平準化が実現します。
旅行業界と一般企業及び従業員、その双方にメリットが生まれるはずですが、双方に課題もあります。ホテルや旅館は仕事に適した環境の部屋や設備を用意する必要があります。企業は従業員がさぼっているのではないかといった疑念に捕らわれないよう、仕事や評価の制度を整える必要もあるでしょう。具体的には「ジョブ型」雇用制度の導入などとなるでしょうか。これは、職務ごとにジョブ・ディスクリプション(職務記述書)を作ってこれに基づき仕事の成果と評価を明確にするというものです。
ワーケーションが地に足の着いたものとなる為にはホテル、旅館と企業が、日本中(さらには世界中)どこでもこの制度が利用できるよう、需要と供給(企業のワーケーション導入とホテルなどによる場所提供)のマッチングがスムーズに行われる仕組みを作ることが望まれます。
日本は長いこと労働生産性が低いと指摘されてきました。(日本の時間当たりの労働生産性はOECD加盟国36ヵ国中21位)長い時間会社にいれば、仕事をしたような気分になり、会社も長時間労働を当然のことと受け止めてきた環境にあっては、生産性が低くなるのは当然です。大切な自分の時間を有効に使える「平準化」と「ジョブ型」雇用制度への移行。長年変えることのできなかった、会社中心の社会を変革するチャンス到来です。
2020.09.11
バッフェット氏が日本人でないワケ
以前このようなタイトルでセミナーを行ったことがあります。もしバフェット氏が日本人で、日本市場でのみ投資活動を行っていたとしたら、あれほどの素晴らしいパフォーマンスをあげることが出来ただろうかという内容の問いかけでした。当時日本株は長期に亘って右肩下がりを続けており米国株と対照的になっていました。失われた20年といわれた時代です。この問いかけの結論は、国の経済が成長を続けることが出来なければ、バフェット氏であっても思うような成果をあげることは出来ないというものです。20年に亘るGDP推移(アベノミクス前まで)を日米で比較すると一目瞭然です。
今回のブログも同じタイトルですが、問いかけ内容は異なります。このところ何度か報じられているようにウオーレン・バッフェットが日本の商社株5銘柄を5%取得していたことが明らかになりました。ナゼこのタイミングでこれまで買ったこともなかった日本株を買ったのか、そしてナゼ商社株なのかということについてです。
新聞やネットなどで伝えられているところでは日本株は米国株に比べて割安である。そして商社は鉱山などの資源への投資が多く、バフェット氏の投資先との親和性が高いというものでした。投資家はどんな銘柄にナゼ投資するのかを発表する義務はありません。また本当のことを言う必要も無いので、本心がどこにあるかは分かりません。
殆どの日本人投資家は商社株を投資対象とは考えていなかったと思われます。コロナの影響で株価が大きく調整した銘柄は多数あり、商社株もその中の1つというくらいの位置付けではなかったでしょうか。商社株の特徴の1つとして予想配当利回りが高いということが挙げられます。バフェット氏の買った5銘柄も3~5%程度配当利回りがあり、買いに動いた時期はもっと前のより安い時であったはずなので、高い配当利回りが確保できることは間違いないと思われます。しかし商社は多くのリスク資産を抱えておりその資産価格評価下落によって多額の償却損が発生するという現実もあるので、積極的に買い進めるには二の足を踏むというのが日本人のスタンスではないでしょうか。
それでは米国人であるバッフェット氏にとって、日本株をポートフォリオに入れると判断した誘因は何でしょうか。ドル価値の低下に対するリスクヘッジではないでしょうか。米国はコロナ対策に巨額の財政出動をしており連邦債務は26兆ドル、GDP比126%と二次大戦直後を上回る過去最悪の水準まで膨張と報じられています。今後も失業や経済停滞を避けるため追加的財政支出は避けられないことでしょう。多額の債務は発行される米国債によってファイナンスされているので、膨大な債券の利払い抑制のためにも金融緩和を続けざるを得ません。金融緩和の継続はドル価値の減価に繋がります。米ドルの価値下落が起きる可能性が高いと考えるなら米国株への集中投資はリスクとなります。一方、株価が割安であることに加えドル安円高が実現するなら日本株からのリターンはさらに期待できることになります。
今回のコロナショックにおいてもバフェット氏がどのような銘柄に投資するのか、多くの投資家が関心をもって見守っていました。驚いたのは、最初に買いを入れたのが米国の航空機株だったことでした。いくらバフェット氏が買ったからといってこの状況下、追随して買う気にはなれないセクターです。しかし二か月もしないうちに保有していた全ての航空機株を売却するという方向に転じました。誤ったと思ったら機敏に動き、正直にそれを伝えるという誠実さは健在でした。
その後暫くして、金鉱山の株への投資が伝わってきました。これまで金については、金利を生まないということを理由に一貫して金保有に否定的であったことから推測するに、コロナ影響下における投資はこれまでの延長線上にはないと判断したのかもしれません。
金鉱山株を買ったのも、ドル価値が下落するリスクを避ける為と考えると納得がゆきます。
コロナ感染の拡大で「世界は変わる」としているバフェット氏。しかしどんなに世界が変わろうとも間違いなく変わらないことがあります。それはバフェット氏がアメリカ人でなくなることはないということ。「バフェット氏が日本人でないわけ」に対する究極の回答でした。
今回のブログも同じタイトルですが、問いかけ内容は異なります。このところ何度か報じられているようにウオーレン・バッフェットが日本の商社株5銘柄を5%取得していたことが明らかになりました。ナゼこのタイミングでこれまで買ったこともなかった日本株を買ったのか、そしてナゼ商社株なのかということについてです。
新聞やネットなどで伝えられているところでは日本株は米国株に比べて割安である。そして商社は鉱山などの資源への投資が多く、バフェット氏の投資先との親和性が高いというものでした。投資家はどんな銘柄にナゼ投資するのかを発表する義務はありません。また本当のことを言う必要も無いので、本心がどこにあるかは分かりません。
殆どの日本人投資家は商社株を投資対象とは考えていなかったと思われます。コロナの影響で株価が大きく調整した銘柄は多数あり、商社株もその中の1つというくらいの位置付けではなかったでしょうか。商社株の特徴の1つとして予想配当利回りが高いということが挙げられます。バフェット氏の買った5銘柄も3~5%程度配当利回りがあり、買いに動いた時期はもっと前のより安い時であったはずなので、高い配当利回りが確保できることは間違いないと思われます。しかし商社は多くのリスク資産を抱えておりその資産価格評価下落によって多額の償却損が発生するという現実もあるので、積極的に買い進めるには二の足を踏むというのが日本人のスタンスではないでしょうか。
それでは米国人であるバッフェット氏にとって、日本株をポートフォリオに入れると判断した誘因は何でしょうか。ドル価値の低下に対するリスクヘッジではないでしょうか。米国はコロナ対策に巨額の財政出動をしており連邦債務は26兆ドル、GDP比126%と二次大戦直後を上回る過去最悪の水準まで膨張と報じられています。今後も失業や経済停滞を避けるため追加的財政支出は避けられないことでしょう。多額の債務は発行される米国債によってファイナンスされているので、膨大な債券の利払い抑制のためにも金融緩和を続けざるを得ません。金融緩和の継続はドル価値の減価に繋がります。米ドルの価値下落が起きる可能性が高いと考えるなら米国株への集中投資はリスクとなります。一方、株価が割安であることに加えドル安円高が実現するなら日本株からのリターンはさらに期待できることになります。
今回のコロナショックにおいてもバフェット氏がどのような銘柄に投資するのか、多くの投資家が関心をもって見守っていました。驚いたのは、最初に買いを入れたのが米国の航空機株だったことでした。いくらバフェット氏が買ったからといってこの状況下、追随して買う気にはなれないセクターです。しかし二か月もしないうちに保有していた全ての航空機株を売却するという方向に転じました。誤ったと思ったら機敏に動き、正直にそれを伝えるという誠実さは健在でした。
その後暫くして、金鉱山の株への投資が伝わってきました。これまで金については、金利を生まないということを理由に一貫して金保有に否定的であったことから推測するに、コロナ影響下における投資はこれまでの延長線上にはないと判断したのかもしれません。
金鉱山株を買ったのも、ドル価値が下落するリスクを避ける為と考えると納得がゆきます。
コロナ感染の拡大で「世界は変わる」としているバフェット氏。しかしどんなに世界が変わろうとも間違いなく変わらないことがあります。それはバフェット氏がアメリカ人でなくなることはないということ。「バフェット氏が日本人でないわけ」に対する究極の回答でした。
2020.08.07
幸せの測り方
ヒト同士の接触を避けるためソーシャル・ディスタンスが世界の常識となっています。挨拶のプロトコールとしての握手、ハグやキスですらその代わりに肘と肘を合わせるという味気ないものに変わってしまいました。ヒトの幸せホルモンであるオキシトシンは手を握ったり抱擁しあったりすることで分泌されるものとされています。ソーシャル・ディスタンスによりオキシトシンの分泌は抑制され、世界の人々の幸せは少なからず奪われているものと思われます。
幸せは「快」の程度によって左右されるともいえます。「快」を司るのは脳から分泌されるドーパミンとかエンドルフィンと言われておりこの脳内物質が受容体に受け止められたときに人は快感を覚えるようにできているようです。
何によって「快」を感じるかはヒトによって個体差がありますが、精神的な充足や達成感、他人からの認知やふれ合いなどでもこの脳内物質は分泌されます。様々な社会的刺激を「快」と認識して分泌量が決まってゆくとすれば、社会性が制限されるソーシャル・ディスタンスは快感も制限しているということになるでしょう。
一方、出社しなくても仕事は出来るということが判明したため、ワーケーション(バケーションを楽しみながら仕事もするというスタイル)を実行する人々もでてきています。気持ちのよい環境で気持ちよく効率的に仕事が出来るということになれば、脳内には喜び物質が溢れ出てくるという効能もあることでしょう。しかしどのように評価されるか不安、などマイナスの側面もあるようです。
ヒトは幸せを感じていると免疫機能が高まり病気にもかかりにくくなり、逆にストレスが溜まると免疫機能が低下します。ソーシャル・ディススタンスや自粛は短期的には命を守るかもしれませんが、長期的には健康を阻害する要素のほうが大きそうです
コロナの影響でヒトの幸せがどのくらい減っているのかを測定することが出来るかもしれません。オキシトシンとドーパミン、エンドルフィンの総量を測定して(そんなことができるのかどうかわかりませんが)ソーシャル・ディスタンスの程度や頻度によってそれらがどのように変化するか関係づけてみるのです。人類の幸せの為に何かをする、とかいうと気恥ずかしくなりますが、科学的データでそれが可能ならやってみる価値はあるのではないでしょうか。
以前、幸福をGDPで語るのはもうやめようという提案がありました。では何で測るのかについては語られていなかったように思います。幸か不幸かコロナのおかげでそういう測定も不可能ではない環境が出来てしまったので、我こそはと思わん方はやってみてはいかがでしょうか。ことは人類全体の幸せにつながることなのでもしかするとノーベル賞も夢ではないかもしれませんよ。
幸せは「快」の程度によって左右されるともいえます。「快」を司るのは脳から分泌されるドーパミンとかエンドルフィンと言われておりこの脳内物質が受容体に受け止められたときに人は快感を覚えるようにできているようです。
何によって「快」を感じるかはヒトによって個体差がありますが、精神的な充足や達成感、他人からの認知やふれ合いなどでもこの脳内物質は分泌されます。様々な社会的刺激を「快」と認識して分泌量が決まってゆくとすれば、社会性が制限されるソーシャル・ディスタンスは快感も制限しているということになるでしょう。
一方、出社しなくても仕事は出来るということが判明したため、ワーケーション(バケーションを楽しみながら仕事もするというスタイル)を実行する人々もでてきています。気持ちのよい環境で気持ちよく効率的に仕事が出来るということになれば、脳内には喜び物質が溢れ出てくるという効能もあることでしょう。しかしどのように評価されるか不安、などマイナスの側面もあるようです。
ヒトは幸せを感じていると免疫機能が高まり病気にもかかりにくくなり、逆にストレスが溜まると免疫機能が低下します。ソーシャル・ディススタンスや自粛は短期的には命を守るかもしれませんが、長期的には健康を阻害する要素のほうが大きそうです
コロナの影響でヒトの幸せがどのくらい減っているのかを測定することが出来るかもしれません。オキシトシンとドーパミン、エンドルフィンの総量を測定して(そんなことができるのかどうかわかりませんが)ソーシャル・ディスタンスの程度や頻度によってそれらがどのように変化するか関係づけてみるのです。人類の幸せの為に何かをする、とかいうと気恥ずかしくなりますが、科学的データでそれが可能ならやってみる価値はあるのではないでしょうか。
以前、幸福をGDPで語るのはもうやめようという提案がありました。では何で測るのかについては語られていなかったように思います。幸か不幸かコロナのおかげでそういう測定も不可能ではない環境が出来てしまったので、我こそはと思わん方はやってみてはいかがでしょうか。ことは人類全体の幸せにつながることなのでもしかするとノーベル賞も夢ではないかもしれませんよ。
2020.07.12
ドリアン・グレイの肖像
舞台はロンドンのサロンと阿片窟。美貌の青年モデル、ドリアンは快楽主義者ヘンリー卿の感化で背徳の生活を享楽するが、彼の重ねる罪悪はすべてその肖像画に現われ、いつしか絵の中の容貌は醜く変り果てていく。慚愧と焦燥に耐えかねた彼は、自分の肖像にナイフを突き刺した……。
快楽主義を実践し、堕落と悪行の末に破滅する美青年とその画像との二重生活が奏でる、耽美と異端の一大交響楽。(新潮文庫掲載のあらすじより)
株式市場と実体経済の乖離とこの物語は一脈通ずるところがあります。株式市場をドリアンその人、実体経済を肖像としてみましょう。コロナ感染により実体経済は悲惨な状態になっています。一方株式市場はまるで何もなかったかのような快調ぶり。経済の下落や不安はすべて肖像画(現実世界)にのみ現れており、株式市場は美貌のドリアンのごとしです。
オスカー・ワイルドのこの小説は実物と肖像の乖離を物語とし、それがどのような結末を迎えるかが描かれています。時の経過と共に修復不可能なほどに醜くなってゆく肖像画に恐れをなしたドリアンは絵にナイフを突き立て、床に倒れこんで絶命します。倒れたドリアンの顔は醜くゆがみ、残された肖像画は最初に描かれたときと同じ美しさを保っていました。
今後の世界がこの小説と同じ筋道をたどるなら、実体経済は回復して元のような経済に戻ってゆく一方、株式市場は壊滅的打撃を受けて機能不全に陥るということになるのでしょうか。万が一そういうことになるとすると、肖像画に突き立てられたナイフとは何でしょうか。
ドリアンの美貌(株式市場の活況)を支えてきたものは溢れ出さんばかりのカネ。
世界の政府は財政支出を行い、中央銀行は国債をはじめとする様々な金融商品を市場から買い上げ、カネを市場に供給しました。財政出動により市場に溢れ出したカネは8兆ドル以上にものぼる膨大な規模となっています。
普通、財政出動により政府債務が膨張すると長期金利が上昇します。ところが金利は一向に上昇していません。これは中央銀行が国債を買っているからです。東南アジアの中には自国で発行した国債を自国の中央銀行が買うという財政ファイナンス(禁じ手)を始めた国も出てきています。禁じ手に近いことをやり続けても不都合なことが起きない現状は、歳をとることのないドリアンのように見えます。どこかで問題が起きることないのでしょうか。
実体経済が回復するにつれて市場に供給され続けたカネは回収されなければなりません。多くの問題は実体経済から乖離した国の通貨や金融商品が価値を失ってゆくという形でおきています。肖像画に突き立てられたナイフが何を意味するのかは分かりませんが、ドリアンの死(株式市場の崩壊)を防ぐには今後極めて慎重な出口戦略が求められます。
快楽主義を実践し、堕落と悪行の末に破滅する美青年とその画像との二重生活が奏でる、耽美と異端の一大交響楽。(新潮文庫掲載のあらすじより)
株式市場と実体経済の乖離とこの物語は一脈通ずるところがあります。株式市場をドリアンその人、実体経済を肖像としてみましょう。コロナ感染により実体経済は悲惨な状態になっています。一方株式市場はまるで何もなかったかのような快調ぶり。経済の下落や不安はすべて肖像画(現実世界)にのみ現れており、株式市場は美貌のドリアンのごとしです。
オスカー・ワイルドのこの小説は実物と肖像の乖離を物語とし、それがどのような結末を迎えるかが描かれています。時の経過と共に修復不可能なほどに醜くなってゆく肖像画に恐れをなしたドリアンは絵にナイフを突き立て、床に倒れこんで絶命します。倒れたドリアンの顔は醜くゆがみ、残された肖像画は最初に描かれたときと同じ美しさを保っていました。
今後の世界がこの小説と同じ筋道をたどるなら、実体経済は回復して元のような経済に戻ってゆく一方、株式市場は壊滅的打撃を受けて機能不全に陥るということになるのでしょうか。万が一そういうことになるとすると、肖像画に突き立てられたナイフとは何でしょうか。
ドリアンの美貌(株式市場の活況)を支えてきたものは溢れ出さんばかりのカネ。
世界の政府は財政支出を行い、中央銀行は国債をはじめとする様々な金融商品を市場から買い上げ、カネを市場に供給しました。財政出動により市場に溢れ出したカネは8兆ドル以上にものぼる膨大な規模となっています。
普通、財政出動により政府債務が膨張すると長期金利が上昇します。ところが金利は一向に上昇していません。これは中央銀行が国債を買っているからです。東南アジアの中には自国で発行した国債を自国の中央銀行が買うという財政ファイナンス(禁じ手)を始めた国も出てきています。禁じ手に近いことをやり続けても不都合なことが起きない現状は、歳をとることのないドリアンのように見えます。どこかで問題が起きることないのでしょうか。
実体経済が回復するにつれて市場に供給され続けたカネは回収されなければなりません。多くの問題は実体経済から乖離した国の通貨や金融商品が価値を失ってゆくという形でおきています。肖像画に突き立てられたナイフが何を意味するのかは分かりませんが、ドリアンの死(株式市場の崩壊)を防ぐには今後極めて慎重な出口戦略が求められます。
2020.06.07
自由と自粛
人は生まれながらにして自由で、その果実を享受する権利を有しています。自分のしたことに責任を負いさえすれば、何をやろうと人からとやかく言われることはありません。好き勝手なことをして痛い目あうのも自由、自分で責任をとればよいだけです。一つだけ制限があり、それは「人に迷惑をかけてはならない」ということ。我々はずっとそういう世界で生きてきました。そして今後もその世界は続いてゆくだろうと思っていました。
いきなり降って湧いたコロナという感染症が、自由を奪ってゆきました。多くの国でロックダウンにより移動の自由が奪われ、我が国でも自粛という名のもとに行動や活動に大幅な制約がかかりました。法的な強制力はなくとも自粛に従ったのは感染を恐れたからのみならず「人に迷惑をかけるかもしれない」ということを恐れたからなのでしょう。自分に症状がなくとも他人に感染させてしまうかもしれない、そして最悪人の命を奪うかもしれないというウイルスを前にして、人々は自粛を受け入れたのだと思います。
未だにしっくりこないのは「人への迷惑」というのがコロナ感染による、という一点に偏り過ぎていたのではないかと感じられるからです。我々は自由主義経済の下で生活しています。企業が活動できなくなれば従業員、顧客、社会に対して大きな迷惑をかけることになります。その重さと重大さはコロナ災害以上のものではないと言い切れるのでしょうか。他人の自由に制限をかけるには相応の覚悟と慎重さが要求されるはずです。国や自治体が国民の活動や事業に制限を加えるなら当事者にとっては極めて大きな迷惑となり得ます。
自粛に伴う損害が補償されたとしても、完全に収束するまでの全額の補償など財政的にも不可能です。また今や再び起きるかもしれない感染拡大への懸念も生まれておりいつまで自粛を続ければよいのか、答えはありません。
我が国の感染者や死亡者の数は欧米諸国と比べて幸いにも2桁少ない状況にあります。それでもコロナ感染はより重大なリスクとして経済も移動も大幅な制限をかけてきました。
憲法の規定では、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」となっています。
今回の対応は“公共の福祉に反しない限り”という観点から比較したとき緊急事態宣言のタイミング、外出自粛や休業要請は正しかったのか、自粛期間は妥当だったのか、公平性は担保されたのか等、今後のためにも検証されるべき課題だと思います。
基本的人権たる自由の制限を最小にする努力を疎かにすべきではありません。
いきなり降って湧いたコロナという感染症が、自由を奪ってゆきました。多くの国でロックダウンにより移動の自由が奪われ、我が国でも自粛という名のもとに行動や活動に大幅な制約がかかりました。法的な強制力はなくとも自粛に従ったのは感染を恐れたからのみならず「人に迷惑をかけるかもしれない」ということを恐れたからなのでしょう。自分に症状がなくとも他人に感染させてしまうかもしれない、そして最悪人の命を奪うかもしれないというウイルスを前にして、人々は自粛を受け入れたのだと思います。
未だにしっくりこないのは「人への迷惑」というのがコロナ感染による、という一点に偏り過ぎていたのではないかと感じられるからです。我々は自由主義経済の下で生活しています。企業が活動できなくなれば従業員、顧客、社会に対して大きな迷惑をかけることになります。その重さと重大さはコロナ災害以上のものではないと言い切れるのでしょうか。他人の自由に制限をかけるには相応の覚悟と慎重さが要求されるはずです。国や自治体が国民の活動や事業に制限を加えるなら当事者にとっては極めて大きな迷惑となり得ます。
自粛に伴う損害が補償されたとしても、完全に収束するまでの全額の補償など財政的にも不可能です。また今や再び起きるかもしれない感染拡大への懸念も生まれておりいつまで自粛を続ければよいのか、答えはありません。
我が国の感染者や死亡者の数は欧米諸国と比べて幸いにも2桁少ない状況にあります。それでもコロナ感染はより重大なリスクとして経済も移動も大幅な制限をかけてきました。
憲法の規定では、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」となっています。
今回の対応は“公共の福祉に反しない限り”という観点から比較したとき緊急事態宣言のタイミング、外出自粛や休業要請は正しかったのか、自粛期間は妥当だったのか、公平性は担保されたのか等、今後のためにも検証されるべき課題だと思います。
基本的人権たる自由の制限を最小にする努力を疎かにすべきではありません。
2020.05.10
チャンスがピンチに変わる時
経済活動が殆ど停止してしまった世界で、人々の生活や命をつなぎとめる役割を各国政府が一身に担っています。そのために支出されている財政支出額はすでに異常な額に達しています。感染者、死亡者の一番多い米国の財政赤字額は4兆ドル規模と見込まれ、前年(2019会計年度9840憶ドル)に比べて4倍もの水準です。
急激な財政支出は政府債務残高を押し上げており、債務残高のGDP比は米国131%(第二次世界大戦直後の119%をすでに超過)日本の同数値は250%を突破の見通し(2020.4.19日経新聞)、ユーロ圏の数値は111%(前年85%)と大幅膨張の見通し(2020.5.1日経新聞)となっています。
財政が持続可能となる条件は、債務残高のGDP比が発散しないことというのがファイナンスの常識です。ロックダウンや自粛が長引くほど政府は失業や休業の支出が増え、分子の債務残高は膨張します。一方、分母のGDPは経済活動の停滞により大幅縮小が不可避。結果は財政持続可能性に大きな疑問符がつくということです。
経済の回復遅れは、国の破綻につながりかねず時間との勝負の様相を呈しています。欧米諸国が感染再拡大のリスクを抱えながらもロックダウン解除、経済活動再開を許可したのは感染状況の見極めによるものばかりではないと思われます。
財政状況の悪化は長期金利上昇、中央銀行によるマネーサプライの供給は通貨安のリスクを伴っています。新興国(東南アジアや南米など)元々債務を多く抱えていましたが、コロナ対策のための財政出動、財政悪化が加わって通貨安が加速しています。通貨安は輸入物価上昇によりインフレを引き起こし財政悪化の悪循環に見舞われることになります。
産油国もオイルに対する需要急減などにより原油価格が下落、高い価格に支えられて好調だった経済が暗転、財政悪化により投資マネーの引き上げも視野に入ってきているものと思われます。
過去に起きてきた様々な問題は、単独で時間差をもってふりかかるのが普通でした。今回これらのリスクが一挙に同時に至る所で発生しています。どこで問題が起きても不思議はなく、連鎖的に発生する恐れも高まっています。
感染に関しては世界各国で制限が緩められ明るさも見え始めています。株価も驚くほどの下げを記録した3月から順調に回復しているように見えます。これはチャンス到来なのでしょうか。
今後の世界は、応急処置によって持ちこたえてきた施策の限界が見え始める局面に入ってゆくはずです。上記をはじめとして様々な所に埋まっている地雷(経済リスク)には十分すぎるほどの注意が必要となるでしょう。長期に亘る自粛を保ちながら以前のような実体経済に戻す(V字回復)のは言われているほどたやすいことではないと思われます。
急激な財政支出は政府債務残高を押し上げており、債務残高のGDP比は米国131%(第二次世界大戦直後の119%をすでに超過)日本の同数値は250%を突破の見通し(2020.4.19日経新聞)、ユーロ圏の数値は111%(前年85%)と大幅膨張の見通し(2020.5.1日経新聞)となっています。
財政が持続可能となる条件は、債務残高のGDP比が発散しないことというのがファイナンスの常識です。ロックダウンや自粛が長引くほど政府は失業や休業の支出が増え、分子の債務残高は膨張します。一方、分母のGDPは経済活動の停滞により大幅縮小が不可避。結果は財政持続可能性に大きな疑問符がつくということです。
経済の回復遅れは、国の破綻につながりかねず時間との勝負の様相を呈しています。欧米諸国が感染再拡大のリスクを抱えながらもロックダウン解除、経済活動再開を許可したのは感染状況の見極めによるものばかりではないと思われます。
財政状況の悪化は長期金利上昇、中央銀行によるマネーサプライの供給は通貨安のリスクを伴っています。新興国(東南アジアや南米など)元々債務を多く抱えていましたが、コロナ対策のための財政出動、財政悪化が加わって通貨安が加速しています。通貨安は輸入物価上昇によりインフレを引き起こし財政悪化の悪循環に見舞われることになります。
産油国もオイルに対する需要急減などにより原油価格が下落、高い価格に支えられて好調だった経済が暗転、財政悪化により投資マネーの引き上げも視野に入ってきているものと思われます。
過去に起きてきた様々な問題は、単独で時間差をもってふりかかるのが普通でした。今回これらのリスクが一挙に同時に至る所で発生しています。どこで問題が起きても不思議はなく、連鎖的に発生する恐れも高まっています。
感染に関しては世界各国で制限が緩められ明るさも見え始めています。株価も驚くほどの下げを記録した3月から順調に回復しているように見えます。これはチャンス到来なのでしょうか。
今後の世界は、応急処置によって持ちこたえてきた施策の限界が見え始める局面に入ってゆくはずです。上記をはじめとして様々な所に埋まっている地雷(経済リスク)には十分すぎるほどの注意が必要となるでしょう。長期に亘る自粛を保ちながら以前のような実体経済に戻す(V字回復)のは言われているほどたやすいことではないと思われます。
2020.04.10
色即是空の世界
コロナウイルスの感染者と死亡者の人数報告が日常となっています。日々増加する感染者。世界中の国々が今はとにかく感染を抑えようと、自宅に留まり外出を控えることを徹底しようとしています。今のところそれしか人の命を守る方法がないということでの外出自粛ということです。
これで事態が収束に向かってくれればやれやれ、ということになるのでしょうが長期化する可能性も否定できません。その場合クローズアップされるのが経済的な問題、収入の減少や失業者の爆発、企業倒産、さらには国家財政の破綻などです。長期に亘って経済が止まることは実体経済の崩壊を意味します。
1929年、米国の株価大暴落に端を発した大恐慌では経済の縮小により各国の失業率は20%以上へと転落し、貧困や病、更には自殺などにより多くの人の命が失われました。今回の問題はウイルスの拡大によりヒトの動きが止まったことによるもので、それが全世界で起きているので影響は大恐慌以上になる可能性も否定できません。(短期に収束できない場合)
「ヒトの命を守る」ことが最重要であるのは当然のことですが、命のはかなさは病だけに起因するわけではありません。経済の激しい落ち込みによって尊い命が失われるという現実は過去に何度も発生してきました。日本の失われた20年では自殺者の数が異常な数に膨れ上がったのは記憶に新しいところです。
今はとにかく感染拡大を防ぐことが先決ということで、人の移動や接触を伴う経済活動は自粛すべしということになっています。しかし感染は1~2カ月で消えてなくなるのでしょうか。収束が思うように進まなかった場合医療と経済活動のせめぎ遭いはより激しく厳しいものとなることが予想されます。感染拡大防止と経済活動制限の折り合いをどこでつけるのか。日本が直面しているのは感染阻止の問題だけではないはずです。都市封鎖まで踏み込んだ諸外国の経済縮小、それを織り込んだ自粛と活動の線引き判断ではないでしょうか。
仏教哲学の核となる言葉に「色即是空」があります。この世の物や現象(色)は時々刻々と変化しており、恒常不変の実体は存在しない(空)ということのようです。世界の情勢に目を向けた時この言葉の意味するところが正に発現しているような気がします。我々が日頃存在しているのが当然と思っていた様々な財やサービスなどの経済実体が一挙に消えてしまいました。この言葉と対をなす「空即是色」の世界に一刻も早く戻ることを願わずにいられません。
これで事態が収束に向かってくれればやれやれ、ということになるのでしょうが長期化する可能性も否定できません。その場合クローズアップされるのが経済的な問題、収入の減少や失業者の爆発、企業倒産、さらには国家財政の破綻などです。長期に亘って経済が止まることは実体経済の崩壊を意味します。
1929年、米国の株価大暴落に端を発した大恐慌では経済の縮小により各国の失業率は20%以上へと転落し、貧困や病、更には自殺などにより多くの人の命が失われました。今回の問題はウイルスの拡大によりヒトの動きが止まったことによるもので、それが全世界で起きているので影響は大恐慌以上になる可能性も否定できません。(短期に収束できない場合)
「ヒトの命を守る」ことが最重要であるのは当然のことですが、命のはかなさは病だけに起因するわけではありません。経済の激しい落ち込みによって尊い命が失われるという現実は過去に何度も発生してきました。日本の失われた20年では自殺者の数が異常な数に膨れ上がったのは記憶に新しいところです。
今はとにかく感染拡大を防ぐことが先決ということで、人の移動や接触を伴う経済活動は自粛すべしということになっています。しかし感染は1~2カ月で消えてなくなるのでしょうか。収束が思うように進まなかった場合医療と経済活動のせめぎ遭いはより激しく厳しいものとなることが予想されます。感染拡大防止と経済活動制限の折り合いをどこでつけるのか。日本が直面しているのは感染阻止の問題だけではないはずです。都市封鎖まで踏み込んだ諸外国の経済縮小、それを織り込んだ自粛と活動の線引き判断ではないでしょうか。
仏教哲学の核となる言葉に「色即是空」があります。この世の物や現象(色)は時々刻々と変化しており、恒常不変の実体は存在しない(空)ということのようです。世界の情勢に目を向けた時この言葉の意味するところが正に発現しているような気がします。我々が日頃存在しているのが当然と思っていた様々な財やサービスなどの経済実体が一挙に消えてしまいました。この言葉と対をなす「空即是色」の世界に一刻も早く戻ることを願わずにいられません。
2020.03.08
コロナとの闘い
コロナウイルスの拡大を防ぐべく、各国がヒトの移動を制限しています。また感染の恐れから出来るだけ外出を控えるいわゆる巣ごもりも多くなっているせいか、街には人影がまばらです。海外からのInboundに加え、海外へ旅行に出かけるOutboundも減少しているようです。その結果、旅行、飲食、娯楽、など様々なマーケットが大幅に縮小します。ヒトの移動減少の帰着するところは世界の需要縮小です。
また、工場での仕事も制限されておりモノの生産も大きく減少しています。企業は中国を始めとして世界中に生産拠点を拡大しているため労働力や原材料の供給が滞り、その結果生産の縮小が起こっています。帰着するところは世界の供給の縮小です。
経済変動は多くの場合、需要の低迷か供給の不足のどちらかにより引き起こされます。前者の場合デフレ傾向、後者ならインフレとなり対策として財政出動や金利変更が行われます。ところが今回のように需要と供給が手を携えて縮小するというのはまれ、経済が悪化するのは当然の摂理で世界中の株価暴落はそうした状況を織り込んでいるのでしょう。
過去の多くの大暴落の折には政策金利を引き下げてそのショックを緩和してゆくというのが常套手段でした。今回も米国FRBによる金利引き下げが行われました。何の手も打たずに事態を傍観しているわけにはいかないので各国も財政、金融政策を繰り出してくると思われます。ただそれでウイルス問題の根本的解決にはつながることはありません。
ヒト、モノの動きを取り戻すためにはウイルスの急拡大(いわゆるパンデミック)に対する恐怖を払拭するしかないでしょう。そのためにはどのような経路でコロナウイルスが拡散しているのか、そしてどのような薬を使えば回復できるのか、この2点を突き止めることに尽きると思われます。
問題はコロナの特殊性にあるようです。「インフルエンザは感染力が強く、ほとんどの人が他人を感染させるが、コロナは誰が感染させ易いかわかっていない」「これまでの研究報告によると症状が軽い人や全くない人が感染源になっている」(押谷東北大教授)「症状がほとんどない人もいるが、そういう人も感染源になる場合対応が難しい。人類が初めて経験するコロナウイルス感染症」「通常ウイルスに異変が起きて病原性や感染力を増す。コロナはほとんど変異していない。かなり特殊」(脇田国立感染症研究所長)(日経2020.2.28政府専門家会議 3委員議論より)
コロナウイルスに対しては各国が同じ方向を向き、進化を加速しつつある科学や医学の力を総動員して立ち向かうことが最優先事項と認識されていると思います。人類は共通の敵に対峙したとき必ず勝利する力を持っていると信じます。暫くいろいろな制約に耐えねばならないでしょうが需要も供給も消えてしまったわけではありません。では、需給が復活するのにどのくらいの時間を要するのかが見えていない中で優先すべき事はなんでしょうか。
需要の制約となっているヒトの動き。その制限を出来るところから解除していくことだろうと思われます。ここまでは大丈夫、これは危険といった線引きをすること。その上でさらなる分析、研究の結果を踏まえて「大丈夫」の領域を広げてゆくというステップになるのではないでしょうか。
また、工場での仕事も制限されておりモノの生産も大きく減少しています。企業は中国を始めとして世界中に生産拠点を拡大しているため労働力や原材料の供給が滞り、その結果生産の縮小が起こっています。帰着するところは世界の供給の縮小です。
経済変動は多くの場合、需要の低迷か供給の不足のどちらかにより引き起こされます。前者の場合デフレ傾向、後者ならインフレとなり対策として財政出動や金利変更が行われます。ところが今回のように需要と供給が手を携えて縮小するというのはまれ、経済が悪化するのは当然の摂理で世界中の株価暴落はそうした状況を織り込んでいるのでしょう。
過去の多くの大暴落の折には政策金利を引き下げてそのショックを緩和してゆくというのが常套手段でした。今回も米国FRBによる金利引き下げが行われました。何の手も打たずに事態を傍観しているわけにはいかないので各国も財政、金融政策を繰り出してくると思われます。ただそれでウイルス問題の根本的解決にはつながることはありません。
ヒト、モノの動きを取り戻すためにはウイルスの急拡大(いわゆるパンデミック)に対する恐怖を払拭するしかないでしょう。そのためにはどのような経路でコロナウイルスが拡散しているのか、そしてどのような薬を使えば回復できるのか、この2点を突き止めることに尽きると思われます。
問題はコロナの特殊性にあるようです。「インフルエンザは感染力が強く、ほとんどの人が他人を感染させるが、コロナは誰が感染させ易いかわかっていない」「これまでの研究報告によると症状が軽い人や全くない人が感染源になっている」(押谷東北大教授)「症状がほとんどない人もいるが、そういう人も感染源になる場合対応が難しい。人類が初めて経験するコロナウイルス感染症」「通常ウイルスに異変が起きて病原性や感染力を増す。コロナはほとんど変異していない。かなり特殊」(脇田国立感染症研究所長)(日経2020.2.28政府専門家会議 3委員議論より)
コロナウイルスに対しては各国が同じ方向を向き、進化を加速しつつある科学や医学の力を総動員して立ち向かうことが最優先事項と認識されていると思います。人類は共通の敵に対峙したとき必ず勝利する力を持っていると信じます。暫くいろいろな制約に耐えねばならないでしょうが需要も供給も消えてしまったわけではありません。では、需給が復活するのにどのくらいの時間を要するのかが見えていない中で優先すべき事はなんでしょうか。
需要の制約となっているヒトの動き。その制限を出来るところから解除していくことだろうと思われます。ここまでは大丈夫、これは危険といった線引きをすること。その上でさらなる分析、研究の結果を踏まえて「大丈夫」の領域を広げてゆくというステップになるのではないでしょうか。
2020.02.06
縦と横が示唆すること
武漢で起きたウイルス騒動は瞬時に世界中に広がり、患者数の増加や居場所の情報も時間差なく伝えられています。ニュースの伝わる速さはネットのお陰で過去とは比べ物にならないものとなっており、情報を受け取った個人や企業の対応も相応に早まります。全世界がこうした横に広がるリスクに対しては歩調をそろえて取り組もうとするので、今回の騒ぎは意外に早く収束するかもしれません。
一方、時間の経過とともに起きる縦の変化(市街の発展のような)はネットでとらえる事ができないので、変化を捉えるには実際にその場所に行ってみるしかないのであります。都市はしばらく来ていないと変化していることが目に見えてわかります。
昨年11月から12月にかけて十数年ぶりにフロリダに来ていました。首都マイアミは以前車がないとどこへも行けない街でした。今や公共の交通機関が巡らされておりmetro moverという高架を走る列車(といっても2両編成でタイアで走る)が主要な観光地を結んでいます。驚くことに運賃がただ。ダウンタウンからマイアミビーチにいく場合、metro moverからmetro bus(2.5$)に乗り継げば車なしで行けます。Vizcayaというマイアミの誇る博物館(豪邸)もmetro railの駅が博物館前に出来ているので公共交通機関で行けるようになったことに驚きました。
ビスケー湾(ダウンタウンとマイアミビーチの間にある湾)にあるダッジ島(Dodge Island)、世界最大のクルーズターミナルとして作られた人工島です。7つのクルーズターミナルがありますが、大型客船も停泊できるようになったのは2016年からだったようです。
フロリダにはマイアミに加えてフォートローダーデール(Fort Lauderdaleマイアミの北40km)にもクルーズターミナルがあります。両方の港を合わせるとカリブ海へのクルーズ港はフロリダが独占しているといっても過言ではないと思われます。
先回来た時(2005.11月)米国は住宅価格が高騰しており、日本の不動産バブル崩壊を経験していた私は現地を見て、やがて米国も不動産バブル崩壊が起きることを確信するに至ったのでした。不幸にも予測はリーマンショック(2008.9月)という形で実現、世界を揺るがす事態となったのは記憶に新しいところです。
他方、クルーズに関しては米国から学ぶところも多々あると感じました。日本でも人気が高まっていますがフロリダに比べるとクルーズターミナルの数や規模が見劣りの感は否めません。観光立国を目指すのであれば飛行機だけでは不足です。四方を海に囲まれている日本は船による旅客移動に適した立地にあると思われます。接岸に問題があるのならマイアミのような人工島を作っても良いのではないでしょうか。羽田の離着陸機を増やすことによる航空機の騒音問題、インバウンド観光客宿泊施設の不足などクルーズ船活用によって解決できそうな課題もあることでしょう。最近、横浜にハンマーヘッドという客船ターミナルが完成し稼働を始めています。これまでの大さん橋に加えて横浜の魅力を高めてくれるものと期待しています。さらに多くの港が日本の主たる都市に出来れば観光のみならず、緊急時の避難、物流、退避場所としても有効な手段となると思われます。
一方、時間の経過とともに起きる縦の変化(市街の発展のような)はネットでとらえる事ができないので、変化を捉えるには実際にその場所に行ってみるしかないのであります。都市はしばらく来ていないと変化していることが目に見えてわかります。
昨年11月から12月にかけて十数年ぶりにフロリダに来ていました。首都マイアミは以前車がないとどこへも行けない街でした。今や公共の交通機関が巡らされておりmetro moverという高架を走る列車(といっても2両編成でタイアで走る)が主要な観光地を結んでいます。驚くことに運賃がただ。ダウンタウンからマイアミビーチにいく場合、metro moverからmetro bus(2.5$)に乗り継げば車なしで行けます。Vizcayaというマイアミの誇る博物館(豪邸)もmetro railの駅が博物館前に出来ているので公共交通機関で行けるようになったことに驚きました。
ビスケー湾(ダウンタウンとマイアミビーチの間にある湾)にあるダッジ島(Dodge Island)、世界最大のクルーズターミナルとして作られた人工島です。7つのクルーズターミナルがありますが、大型客船も停泊できるようになったのは2016年からだったようです。
フロリダにはマイアミに加えてフォートローダーデール(Fort Lauderdaleマイアミの北40km)にもクルーズターミナルがあります。両方の港を合わせるとカリブ海へのクルーズ港はフロリダが独占しているといっても過言ではないと思われます。
先回来た時(2005.11月)米国は住宅価格が高騰しており、日本の不動産バブル崩壊を経験していた私は現地を見て、やがて米国も不動産バブル崩壊が起きることを確信するに至ったのでした。不幸にも予測はリーマンショック(2008.9月)という形で実現、世界を揺るがす事態となったのは記憶に新しいところです。
他方、クルーズに関しては米国から学ぶところも多々あると感じました。日本でも人気が高まっていますがフロリダに比べるとクルーズターミナルの数や規模が見劣りの感は否めません。観光立国を目指すのであれば飛行機だけでは不足です。四方を海に囲まれている日本は船による旅客移動に適した立地にあると思われます。接岸に問題があるのならマイアミのような人工島を作っても良いのではないでしょうか。羽田の離着陸機を増やすことによる航空機の騒音問題、インバウンド観光客宿泊施設の不足などクルーズ船活用によって解決できそうな課題もあることでしょう。最近、横浜にハンマーヘッドという客船ターミナルが完成し稼働を始めています。これまでの大さん橋に加えて横浜の魅力を高めてくれるものと期待しています。さらに多くの港が日本の主たる都市に出来れば観光のみならず、緊急時の避難、物流、退避場所としても有効な手段となると思われます。
2019.11.20
定価がなくなる日
世界中にあるアウトレット。そこで買い物をすると得した気持ちになります。定価の20%引き等、数値表示がされている為どのくらい得をしたかが実感されるのです。買い物をする人達は割引率もさることながら「定価」というものが正しい価格であると信用しているので、そこから割り引かれた%が大きいほどお得感を感じているハズです。たくさんのブランド袋を抱えて車に乗り込んでゆく人達の顔には笑みが溢れています。
「定価」とは企業が付けた価格です。商品にどのような値段をつけるか、というのは企業の存続をかけた重要な戦略です。製作にかかった直接のコスト、販売にかかる人件費や広告宣伝費、どのくらいの数量が売れるのか、利益はどのくらい取るのか等を勘案して設定されるのですが、数量(売れゆき)が予測通りになることはまれだと思われます。その結果在庫を抱えることになった場合値引きをして在庫処分する場所としてアウトレットが存在しています。
もし提供者が様々なデータを正確に取り込むことが出来たなら、「定価」はどうなるでしょうか。「定価」は「時価」に変わるかもしれません。例えば株式市場のようなイメージ。企業価値に「定価」はありません。市場参加者の心理や需給、経済の外部環境や利益を生み出す力等をおり込みながら時々刻々時価が形成されています。
株式市場取引ほどではないにしても価格が変化する商品が増えつつあります。例えば航空券やホテル宿泊料。これらは供給量が決まっているので需要量に応じて価格を変化させています。その目的は売れ残りを最小化することです。
需給に応じて価格を変える方法はダイナミックプライシングと呼ばれ、コンサートやスポーツイベントでも使用されていますが小売業においても取り入れ開始、と報じられています。一部の家電量販店では在庫量、競合店価格情報に加え売れ筋死に筋などを分析して売値に反映させデジタル表示されているとのこと。価格が時々刻々と変わるわけではないものの、「定価」はあって無きが如しという意味では株式市場の価格表示に近づいているように感じます。
また、百貨店で販売されるアパレル等の値付けはメーカーが行っていますがメーカーは売れ残りリスクを自社で負っているのでその分価格は高くなっています。こうしたリスクを反映する価格をデジタル表示出来れば価格は下げられることになります。
モノの価格が株価のように変動した場合、消費者は「定価」と比べてお得な買い物をしたという喜びが無くなるでしょう。また他人と比べて割高な値段で買ってしまった、買うタイミングを間違えたといった後悔を感じることもあり得ます。妥当価格を見定める見識が求められるという面倒もあります。
もしかすると「定価」は人に幸福感を提供する為に存在しているのかもしれません。しかしながら今後さらにデジタル技術が進歩したとき、「定価」という概念は残るのでしょうか。完全に無くなることはないにしても増々希薄になってゆくものと思われます。消費者は自分なりの価値と価格を見極める力がモノを言う時代になることでしょう。
「定価」とは企業が付けた価格です。商品にどのような値段をつけるか、というのは企業の存続をかけた重要な戦略です。製作にかかった直接のコスト、販売にかかる人件費や広告宣伝費、どのくらいの数量が売れるのか、利益はどのくらい取るのか等を勘案して設定されるのですが、数量(売れゆき)が予測通りになることはまれだと思われます。その結果在庫を抱えることになった場合値引きをして在庫処分する場所としてアウトレットが存在しています。
もし提供者が様々なデータを正確に取り込むことが出来たなら、「定価」はどうなるでしょうか。「定価」は「時価」に変わるかもしれません。例えば株式市場のようなイメージ。企業価値に「定価」はありません。市場参加者の心理や需給、経済の外部環境や利益を生み出す力等をおり込みながら時々刻々時価が形成されています。
株式市場取引ほどではないにしても価格が変化する商品が増えつつあります。例えば航空券やホテル宿泊料。これらは供給量が決まっているので需要量に応じて価格を変化させています。その目的は売れ残りを最小化することです。
需給に応じて価格を変える方法はダイナミックプライシングと呼ばれ、コンサートやスポーツイベントでも使用されていますが小売業においても取り入れ開始、と報じられています。一部の家電量販店では在庫量、競合店価格情報に加え売れ筋死に筋などを分析して売値に反映させデジタル表示されているとのこと。価格が時々刻々と変わるわけではないものの、「定価」はあって無きが如しという意味では株式市場の価格表示に近づいているように感じます。
また、百貨店で販売されるアパレル等の値付けはメーカーが行っていますがメーカーは売れ残りリスクを自社で負っているのでその分価格は高くなっています。こうしたリスクを反映する価格をデジタル表示出来れば価格は下げられることになります。
モノの価格が株価のように変動した場合、消費者は「定価」と比べてお得な買い物をしたという喜びが無くなるでしょう。また他人と比べて割高な値段で買ってしまった、買うタイミングを間違えたといった後悔を感じることもあり得ます。妥当価格を見定める見識が求められるという面倒もあります。
もしかすると「定価」は人に幸福感を提供する為に存在しているのかもしれません。しかしながら今後さらにデジタル技術が進歩したとき、「定価」という概念は残るのでしょうか。完全に無くなることはないにしても増々希薄になってゆくものと思われます。消費者は自分なりの価値と価格を見極める力がモノを言う時代になることでしょう。
2019.10.18
倒錯の世界
リーマンショック後、世界の中央銀行は金利引き下げによって金融危機からの脱却を目指してきました。しかしショックの度合があまりにも大きかった為金利引き下げだけでは足りず、量的緩和策(QE)をも導入して市中に出回るマネーの量を増やし続けました。
それでも経済浮揚効果が十分でないと見て、幾つかの国々はマイナス金利まで踏み込んでいます。(日本は2016.2実施、その他、EU、デンマーク、スウェーデン、スイス等)これ等一連の政策は民間銀行からの貸し出しを増やし、マネーが実体経済に十分に行き渡ることを目的としたものでした。
ところが世界に溢れ出たマネーは2018.7から始まった米中貿易戦争等による景気減速を恐れ、安全性が高いと考えられた債券に流れ込み債券のマイナス利回りが発生しました。マイナス利回りというのは(債券を)買う側が金利を支払うという倒錯の世界であります。
なぜかくも不思議なことが実現するのかと言えば、債券満期を迎える前にさらに高い価格で買ってくれる買い手が現れる(ババ抜き)か、中央銀行が買い取った価格より高く買ってくれると考えている(マネーの逆流)からに他なりません。今や日本のみならずフランス、ドイツ、スイス等の国債もマイナス利回りとなっており、世界に流通している債券残高の1/4がマイナス利回りという債券バブル状況にあります。
このようなプロセスは債券を大量に保有する民間銀行の採算を悪化させ、借り入れと貸し出しの金利差縮小により融資に資金がまわらない等の悪循環を生み出しています。これまで、金利を下げれば景気は回復に向かうというのが当然の考え方であり政策でもありましたが、今や下げ過ぎの金利水準(reversal rate)は金融仲介機能を阻害し逆効果になるのではないかという疑念を産んでいます。
倒錯の世界の次に来るかもしれない暗黒の世界。そのような暗渠に陥らない現実的方法はマネーを実経済に回すこと。その為には設備投資や貿易、消費を阻害している主たる原因、貿易戦争を止めることを急ぐべき段階にきています。
それでも経済浮揚効果が十分でないと見て、幾つかの国々はマイナス金利まで踏み込んでいます。(日本は2016.2実施、その他、EU、デンマーク、スウェーデン、スイス等)これ等一連の政策は民間銀行からの貸し出しを増やし、マネーが実体経済に十分に行き渡ることを目的としたものでした。
ところが世界に溢れ出たマネーは2018.7から始まった米中貿易戦争等による景気減速を恐れ、安全性が高いと考えられた債券に流れ込み債券のマイナス利回りが発生しました。マイナス利回りというのは(債券を)買う側が金利を支払うという倒錯の世界であります。
なぜかくも不思議なことが実現するのかと言えば、債券満期を迎える前にさらに高い価格で買ってくれる買い手が現れる(ババ抜き)か、中央銀行が買い取った価格より高く買ってくれると考えている(マネーの逆流)からに他なりません。今や日本のみならずフランス、ドイツ、スイス等の国債もマイナス利回りとなっており、世界に流通している債券残高の1/4がマイナス利回りという債券バブル状況にあります。
このようなプロセスは債券を大量に保有する民間銀行の採算を悪化させ、借り入れと貸し出しの金利差縮小により融資に資金がまわらない等の悪循環を生み出しています。これまで、金利を下げれば景気は回復に向かうというのが当然の考え方であり政策でもありましたが、今や下げ過ぎの金利水準(reversal rate)は金融仲介機能を阻害し逆効果になるのではないかという疑念を産んでいます。
倒錯の世界の次に来るかもしれない暗黒の世界。そのような暗渠に陥らない現実的方法はマネーを実経済に回すこと。その為には設備投資や貿易、消費を阻害している主たる原因、貿易戦争を止めることを急ぐべき段階にきています。
2019.07.24
2000万円不足?
金融庁・金融審議会の報告書が、平均的高齢夫婦世帯では、年金だけでは2000万円不足と指摘したことがクローズアップされ社会問題化しました。同報告書によると「老後の生活設計を考えたことがある」人は全体の67.8%、30代以上で軒並み50%以上、その理由としては「老後の生活が不安だから」であり「お金」が主要要因になっていることが窺える、とされています。
人間は過去を懐かしんだり悔んだりしながら現在を生きていますが、将来がはっきりと見えている人は一人もいません。不安というのは何がおきるか判らないがゆえに生じる妄想の産物です。但しこれまで生きてきた経験から現在の延長線上に起きるであろうことを思い浮かべるので、単なる妄想よりは実現性は高いのでしょう。
不安の源は2000万という数字ではなく、酷い目に合うことなく人間らしく生を全うしたいというささやかな望みに対する懐疑にあるのではないでしょうか。将来そのような境遇に合わない為に必要なのはカネだけではないでしょうが、あれば少しは安心できるだろうからということで目安として提示したところ、逆に不安を煽る結果となってしまったということかもしれません。
年金だけでは足りないのは皆分かっているでしょう。その不足を長期の投資で補ったらどうか、というのも間違ってはいないと思います。ただ政策担当者たる国家が、個人だけに責任転嫁するというのはいかがなものでしょうか。
政治の第一義的使命は何でしょうか。小手先の制度改定によりパッチワークを続けることなどでは決してありません。国を豊かにして生活のレベルをかさ上げすることにあるのではないでしょうか。「失われた20年」のような状況に陥らないようにすること、不幸にも陥ってしまったなら早急にそこから脱出させることです。世界を見渡しても今後世の中が良くなっていくとは考えにくい状況にあります。どのような舵取りをすればこの目的を達することができるのか、与党のみならず野党も第一義的使命を全うする決意と覚悟が望まれます。
国民は報告書の提案のように投資のための金融知識を身につけていくべきでしょう。一方、国の経済を継続的成長に導ける能力のある政治家を見極め、選ぶことも同じくらい重要な一歩であると思います。20年後の将来、GDPが右肩上がりを続け2000万円問題は過去の笑い話であったという報告書が提出されることを期待しています。
人間は過去を懐かしんだり悔んだりしながら現在を生きていますが、将来がはっきりと見えている人は一人もいません。不安というのは何がおきるか判らないがゆえに生じる妄想の産物です。但しこれまで生きてきた経験から現在の延長線上に起きるであろうことを思い浮かべるので、単なる妄想よりは実現性は高いのでしょう。
不安の源は2000万という数字ではなく、酷い目に合うことなく人間らしく生を全うしたいというささやかな望みに対する懐疑にあるのではないでしょうか。将来そのような境遇に合わない為に必要なのはカネだけではないでしょうが、あれば少しは安心できるだろうからということで目安として提示したところ、逆に不安を煽る結果となってしまったということかもしれません。
年金だけでは足りないのは皆分かっているでしょう。その不足を長期の投資で補ったらどうか、というのも間違ってはいないと思います。ただ政策担当者たる国家が、個人だけに責任転嫁するというのはいかがなものでしょうか。
政治の第一義的使命は何でしょうか。小手先の制度改定によりパッチワークを続けることなどでは決してありません。国を豊かにして生活のレベルをかさ上げすることにあるのではないでしょうか。「失われた20年」のような状況に陥らないようにすること、不幸にも陥ってしまったなら早急にそこから脱出させることです。世界を見渡しても今後世の中が良くなっていくとは考えにくい状況にあります。どのような舵取りをすればこの目的を達することができるのか、与党のみならず野党も第一義的使命を全うする決意と覚悟が望まれます。
国民は報告書の提案のように投資のための金融知識を身につけていくべきでしょう。一方、国の経済を継続的成長に導ける能力のある政治家を見極め、選ぶことも同じくらい重要な一歩であると思います。20年後の将来、GDPが右肩上がりを続け2000万円問題は過去の笑い話であったという報告書が提出されることを期待しています。
2019.06.28
ベトナム ダナン旅行記

3月中旬、ダナンへ行った。南北に細長いベトナムの中ほどに位置する場所で、ベトナム戦争の頃米軍の駐屯地のあったところ。長いビーチに面したリゾートで、寒い日本から飛んでくると頬も緩む。
ビーチから道路を渡った道沿いにはレストランが多い。レストラン前には水が張ってあるたらいがいくつもあり、その中に生きた魚や貝、エビ、ロブスターまで。ここで好きなものを指さすと新鮮なまま調理されて出てくる。
ビーチサイドには軽食も採れるバーがある。陽が傾きかける頃、バーの椅子に腰かけて海を見ながら酒を飲む人多数。これは贅沢、お気に入りの場所となった。

ダナンはこのビーチを売りものとしており、すでにホテルは山ほどあるが、なんせビーチは長いので新しいホテルがどんどん出来ている。
ダナンを南に30Km行ったところにある町ホイアン。街全体が世界文化遺産に指定されている。
16世紀末以降、国際貿易港として繁栄。ベトナム政府も観光スポットとして力を入れている場所だからか各ホテルからは無料のシャトルバスがでている。夕暮れ時ホイアンの街は提灯の光に照らされ、中国人街を中心に古い歴史的建造物とそこで買い物や飲食を楽しむ人々で賑わう。

ダナンの北100Km、ベトナム最後の王朝本拠地跡フエ。中国支配から独立、13代続いたが1883年フランスにより占領された。その後べトナム戦争時にはこのあたりが最大の激戦地となる。
門をくぐって正面の建物は68年のテト攻勢で完全に崩壊、王宮の80%が焼失。TVカメラが初めて戦地に入って世界中に放映されたのでフエの名前は一躍有名になった。

欧、米等の列強のエゴに翻弄され、歴史の荒波にもまれ続けたベトナム。しかし現在進行中の米中貿易戦争はベトナム発展のチャンスにつながる可能性が高いとみなされ始めている。
中国企業はベトナムで生産して、ベトナムから輸出することで米国の制裁関税を免れ得る。また、これまで中国を製造拠点としてきた国々も米中貿易戦争の影響を避けるべく製造拠点をベトナムに移しつつある。中国にある米国企業も生産拠点をベトナムに移しているようだ。
ベトナムは棚ぼたの利益を生産と輸出の両面から得られることになりそうである。今度こそ「苦あれば楽あり」ということになってほしい。
2019.05.14
麻酔の効かないカラダ
米中の貿易戦争がエスカレートしています。米国は1~2弾で中国からの輸入品500億ドル分につき既に25%の制裁関税を実行、5月10日第3弾で2000億ドル分に25%課税を決定、さらに次の4弾で3250億ドル分に25%をかけるとしています。これに対し中国も米国からの輸入品に対し制裁関税で対抗し続けています。
お互いに協議による解決を目指していますが協議は行き詰まっています。原因は話し合いで解決することが難しい国家主権の修正というところに本質的問題があることだと思われます。自国第一主義の米国に対し、国家資本主義の中国。経済においては資本主義という共通項があっても、政治においては民主主義と共産主義という水と油の関係にあります。
この問題を貿易と関税という力関係で解決しようとしても解決の道筋は見えません。
お互いの妥協点が見つからず第四弾が実行され、解決なく継続していった場合何が起きるでしょうか。大きく分けて以下3つが考えられます。
① 売上減少、コスト上昇(supply chainの見直し等に伴う)による各国企業の収益の低下
② 企業の投資減少、国家による技術囲い込み競争による技術発展の停滞
③ 世界経済成長率下落、インフレ昂進、各国税収低下、財政出動余力低迷
なんといっても恐ろしいのは①②③の結果、世界的危機に対する対応力が著しく低下することです。既に危険水域にある世界経済に一度コトが起きると回復するのが極めて困難になります。11年前のリーマンショック時、米国は政策金利を一挙に5%引き下げ0%に近い政策金利を維持し続けました。最近になってようやく2.5%に戻した段階にあります。しかし再びリーマンショック並みの危機が発生した場合、現行政策金利を0に下げてもその効果はリーマン対応時の半分程度に過ぎません。世界の先進各国もリーマンショック後の政策金利引き下げ、現状はほぼ金利ゼロのままです。
中国はリーマンショック時、4兆元もの財政支出をして自国並びに世界の危機回避に貢献しました。今回、貿易戦争の悪影響を避けるべく約2兆元の財政出動をしていると報じられています。もし再びリーマン級の危機に世界が見舞われた場合、中国の財政出動も限定的とならざるを得ないと危惧します。
自分のカラダが麻酔の十分に効かない状態にあるなら、大手術を要するような病巣が発見されないことを祈るしかありません。自国の政治的課題を解決するために、世界を巨大なリスクにさらすなら、麻酔なしの手術の痛みに耐える覚悟が問われます。
お互いに協議による解決を目指していますが協議は行き詰まっています。原因は話し合いで解決することが難しい国家主権の修正というところに本質的問題があることだと思われます。自国第一主義の米国に対し、国家資本主義の中国。経済においては資本主義という共通項があっても、政治においては民主主義と共産主義という水と油の関係にあります。
この問題を貿易と関税という力関係で解決しようとしても解決の道筋は見えません。
お互いの妥協点が見つからず第四弾が実行され、解決なく継続していった場合何が起きるでしょうか。大きく分けて以下3つが考えられます。
① 売上減少、コスト上昇(supply chainの見直し等に伴う)による各国企業の収益の低下
② 企業の投資減少、国家による技術囲い込み競争による技術発展の停滞
③ 世界経済成長率下落、インフレ昂進、各国税収低下、財政出動余力低迷
なんといっても恐ろしいのは①②③の結果、世界的危機に対する対応力が著しく低下することです。既に危険水域にある世界経済に一度コトが起きると回復するのが極めて困難になります。11年前のリーマンショック時、米国は政策金利を一挙に5%引き下げ0%に近い政策金利を維持し続けました。最近になってようやく2.5%に戻した段階にあります。しかし再びリーマンショック並みの危機が発生した場合、現行政策金利を0に下げてもその効果はリーマン対応時の半分程度に過ぎません。世界の先進各国もリーマンショック後の政策金利引き下げ、現状はほぼ金利ゼロのままです。
中国はリーマンショック時、4兆元もの財政支出をして自国並びに世界の危機回避に貢献しました。今回、貿易戦争の悪影響を避けるべく約2兆元の財政出動をしていると報じられています。もし再びリーマン級の危機に世界が見舞われた場合、中国の財政出動も限定的とならざるを得ないと危惧します。
自分のカラダが麻酔の十分に効かない状態にあるなら、大手術を要するような病巣が発見されないことを祈るしかありません。自国の政治的課題を解決するために、世界を巨大なリスクにさらすなら、麻酔なしの手術の痛みに耐える覚悟が問われます。
2019.04.04
優秀な血統のうそ
一昔前と比較すると、個人の満足度は格段に上昇しているのではないでしょうか。モノやサービスにコストがかからなくなってきたからです。必要なサービスのみにカネを払えばよいので、個人が保有しておかねばならない金銭は少なくて済みます。コストがかからないのに、提供されるモノやサービスの質はどんどん良くなっているのを実感します。
例えば情報。座ったままでkey wordを入れれば良いだけです。Googleなどがなかった頃には本屋や図書館を巡り歩いてようやくたどり着けるのは求めていた情報の一部に過ぎない、というのが普通でした。SNSがなかった頃、人と人のつながりは長い付き合いでもない限り限定的かつ浅薄なものに過ぎなかったのです。
音楽や動画、写真なども、驚くほど多様な選択肢の中から自分の好みの1つをたちどころに廉価で入手できるようになっており、医療分野においても多数の患者の画像データを蓄積、分析することでより正確な病名や治療法が見出されてゆくのでしょう。健康や長寿も夢物語の話ではなくなっています。満足度と幸福感がパラレルな関係にあるなら、人々は昔よりずっと幸せになっているのではないでしょうか。
事実を裏付ける真実の特定精度も向上してゆくことでしょう。
データ・サイエンティストと言われる人々は事実と相関性の高いデータを見つけ出すことを仕事としています。例えば優勝する確率が高い競馬馬はどのような特性をもっているのか、一般的には勝率は血統だと考えられており、馬主は血統の良い馬を高いコストをかけて入手しています。
ところが、あるサイエンティストは本当の特性を見事に言い当てることが出来ました。競馬馬が優勝できるか否かは左心室の大きさによると見抜いたのです。(「誰もが嘘をついている」Everybody liesより)今後、人類も世界も加速度的に進歩してゆくと思われますが、何がこうした満足感や進歩を支えるのでしょうか。
ゼロに近い値段でサービスを提供したり、真実にせまったり、を可能にしているのはデータです。企業は膨大なデータを収集、加工、提供して効果の高いソリューション(広告など)を提供し、そこから得た収入でサービスの利用料金を低下させるという循環を繰り返します。最近は「データの価値」にスポットライトがあたっており、世界に溢れるデータを集めることがこうしたビジネスを可能ならしめているのは事実でしょう。
ただ、既に長い月日が流れ今や当たり前の感覚になっていますが、データがその価値を実現させることができたのはアナログをデジタルに変える技術があったからです。血統が優れていてもタフな心臓がなければ勝負に勝てないという事実を見逃してはなりません。ビッグデータを形にしているタフな心臓。それはデジタル化技術ではないでしょうか。
例えば情報。座ったままでkey wordを入れれば良いだけです。Googleなどがなかった頃には本屋や図書館を巡り歩いてようやくたどり着けるのは求めていた情報の一部に過ぎない、というのが普通でした。SNSがなかった頃、人と人のつながりは長い付き合いでもない限り限定的かつ浅薄なものに過ぎなかったのです。
音楽や動画、写真なども、驚くほど多様な選択肢の中から自分の好みの1つをたちどころに廉価で入手できるようになっており、医療分野においても多数の患者の画像データを蓄積、分析することでより正確な病名や治療法が見出されてゆくのでしょう。健康や長寿も夢物語の話ではなくなっています。満足度と幸福感がパラレルな関係にあるなら、人々は昔よりずっと幸せになっているのではないでしょうか。
事実を裏付ける真実の特定精度も向上してゆくことでしょう。
データ・サイエンティストと言われる人々は事実と相関性の高いデータを見つけ出すことを仕事としています。例えば優勝する確率が高い競馬馬はどのような特性をもっているのか、一般的には勝率は血統だと考えられており、馬主は血統の良い馬を高いコストをかけて入手しています。
ところが、あるサイエンティストは本当の特性を見事に言い当てることが出来ました。競馬馬が優勝できるか否かは左心室の大きさによると見抜いたのです。(「誰もが嘘をついている」Everybody liesより)今後、人類も世界も加速度的に進歩してゆくと思われますが、何がこうした満足感や進歩を支えるのでしょうか。
ゼロに近い値段でサービスを提供したり、真実にせまったり、を可能にしているのはデータです。企業は膨大なデータを収集、加工、提供して効果の高いソリューション(広告など)を提供し、そこから得た収入でサービスの利用料金を低下させるという循環を繰り返します。最近は「データの価値」にスポットライトがあたっており、世界に溢れるデータを集めることがこうしたビジネスを可能ならしめているのは事実でしょう。
ただ、既に長い月日が流れ今や当たり前の感覚になっていますが、データがその価値を実現させることができたのはアナログをデジタルに変える技術があったからです。血統が優れていてもタフな心臓がなければ勝負に勝てないという事実を見逃してはなりません。ビッグデータを形にしているタフな心臓。それはデジタル化技術ではないでしょうか。
2019.02.17
損をするのが好きな人
日本人は投資より貯蓄を選ぶ人が多いのですがなぜでしょうか。以下のような理由が考えられます。勤勉が美徳という昔からの教育の結果、「濡れ手に粟」のような利益を追求する投資はけしからんという倫理観に基づくもの、投資はリスクがあるので例え利息が微々たるものであっても損失の発生しない貯蓄のほうが安心であるという心理的安定志向によるもの、投資は難しくうまくいくかどうかわからないのに長い時間をかけて学ぶというのが面倒という時間対効果を重視した効率面からのもの等です。
日本と米国を比較した場合、この投資と貯蓄の割合が著しく異なることは毎年公表されている資金循環統計の比較により明らかです。家計金融資産に占める貯蓄の割合は、米国13%に対して、日本52.5%、株、投信等投資割合は米国48%に対して日本14.9%となっています。(2018.3末 資金循環統計)
いつまでたっても貯蓄偏重の傾向から抜け出せないことに問題意識を持った政府はNISAなど新制度を導入して貯蓄から投資への流れを作ろうとしました。NISAとは一定額の投資から生じる利益に対して通常ならかかる税金を0にするというものです。
問題は利益に税金がかからないようにすれば人々は貯蓄より投資を選択するようになるのか、ということです。利益がでても20%近い税金がかからないのはありがたいことではありますが、投資は利益がでることもあれば、損がでることもあります。一般的に人々が投資に向かわないのは「損をするのが嫌だから」という気持ちによるところが大きいのではないでしょうか。
利益に税金がかからないと言われて、それでは投資してみようと思う人がどのくらいいるのか、よくわかりません。特に貯蓄から投資への流れを作るという趣旨から考えると、初めて投資を考えている人の背中を押すには損が出ても一定の救済措置がある方が有効だと思われます。
具体的には給与収入から投資損失を一定額控除出来るという税制を導入するというのはどうでしょう。現在の証券税制において、損失が控除できるのは有価証券の利益との間のみとなっています。投資損失が出ても収入からも損失を控除できるならリスクはとりやすいと思われます。
損をするのが好きな人は日本にも米国にもいないはずです。ただ、有価証券からの損益通算に加えて、他の収入からも一定額損失控除できるという税制を導入している米国で、貯蓄より投資を選択する人が多いというのは自然なこと。貯蓄と投資の割合に差がでるのは国民性というよりも税制の違いにあり、ということかもしれません。
日本と米国を比較した場合、この投資と貯蓄の割合が著しく異なることは毎年公表されている資金循環統計の比較により明らかです。家計金融資産に占める貯蓄の割合は、米国13%に対して、日本52.5%、株、投信等投資割合は米国48%に対して日本14.9%となっています。(2018.3末 資金循環統計)
いつまでたっても貯蓄偏重の傾向から抜け出せないことに問題意識を持った政府はNISAなど新制度を導入して貯蓄から投資への流れを作ろうとしました。NISAとは一定額の投資から生じる利益に対して通常ならかかる税金を0にするというものです。
問題は利益に税金がかからないようにすれば人々は貯蓄より投資を選択するようになるのか、ということです。利益がでても20%近い税金がかからないのはありがたいことではありますが、投資は利益がでることもあれば、損がでることもあります。一般的に人々が投資に向かわないのは「損をするのが嫌だから」という気持ちによるところが大きいのではないでしょうか。
利益に税金がかからないと言われて、それでは投資してみようと思う人がどのくらいいるのか、よくわかりません。特に貯蓄から投資への流れを作るという趣旨から考えると、初めて投資を考えている人の背中を押すには損が出ても一定の救済措置がある方が有効だと思われます。
具体的には給与収入から投資損失を一定額控除出来るという税制を導入するというのはどうでしょう。現在の証券税制において、損失が控除できるのは有価証券の利益との間のみとなっています。投資損失が出ても収入からも損失を控除できるならリスクはとりやすいと思われます。
損をするのが好きな人は日本にも米国にもいないはずです。ただ、有価証券からの損益通算に加えて、他の収入からも一定額損失控除できるという税制を導入している米国で、貯蓄より投資を選択する人が多いというのは自然なこと。貯蓄と投資の割合に差がでるのは国民性というよりも税制の違いにあり、ということかもしれません。
2019.01.30
市場はリスクをおり込んだのか?
昨年末から年始にかけて世界の株式市場は大荒れとなりました。日経平均は何度も20,000円を割り込み2019年はどのような年になるのか、今後の世界はどのように動いていくのか、いやな予感に包まれた年明けでした。
年末の25日、日経平均は1日で1,010円も下げ2018年最大の下落となりました。とんだクリスマスプレゼントを受け取ったわけですがこのプレゼント、送り主はトランプ大統領。議会との溝拡大、FRB議長の解任言及などを嫌気した市場は1,000ドルを超える下げで応え、その流れを日本市場が引き継いだのでした。
続いて20,000円を割り込んだのは本年4日の大発会。28日の大納会と比べて452円安ととんだお年玉を受け取ったのでしたが、このお年玉送り主はアップルのクックCEO。前日3日アップルの業績の下方修正発表により、NYダウは660$の下落、その流れを引き継いでの日本株の下げでした。また、3日の円ドルレートは一時104円台と数分間で5円も急騰(ドル安)しました。米中の貿易戦争は中国企業への悪影響が大きいと思われていたところ、米国への影響も予想外に大きいというショックがさらにダウの下げを加速したということでしょう。
さすがにここまで世界を揺るがす事態となると、根本的対応をせざるを得ないということで金融面ではFRBが利上げスピードを抑える方向に転換、米中も貿易戦争の解決に向けて妥協点を真剣に探り始めているようです。こうした流れを市場が織り込み始めているわけですが、果たして今後株価も底を打ってめでたしめでたしとなるのでしょうか。
残念ながらそうは思えません。
現在、市場変動の背後にあるのは複合的リスクだからです。中国と米国という二巨大市場で貿易というモノの流れが停滞し始めており、その影響が他の先進国や新興国に広がるので世界経済が減速するのは明白です。また金融(カネ)面では、リーマンショックの影響を吸収すべく世界中の中央銀行が緩和策を続けてきたマネーが吸収されずに溢れかえったったままです。カネの行き場がないのにモノの流れが制限され、実体経済にカネが回っていかなければカネの価値は下がり経済は低迷します。
これまで起きてきた世界危機は原因となった国が限定され、時間的にもタイムラグを伴っていました。またその影響の拡散を防ぐため、各国が協調して手を打つことでなんとか乗り越えてきたというのが実態です。
今回の米中貿易戦争はその何れもが異なります。世界の主要国が共通の認識と方向性をもって解決にあたる道筋が見えれば、やがて市場の行き過ぎが是正されるというのが「リスクの織り込み」ということでしょうが、歩調が合っているとは言い難いのが現実。過去に例を見ない形の今回の危機、どのような結末を迎えるのか注意深く見ておく必要があります。
年末の25日、日経平均は1日で1,010円も下げ2018年最大の下落となりました。とんだクリスマスプレゼントを受け取ったわけですがこのプレゼント、送り主はトランプ大統領。議会との溝拡大、FRB議長の解任言及などを嫌気した市場は1,000ドルを超える下げで応え、その流れを日本市場が引き継いだのでした。
続いて20,000円を割り込んだのは本年4日の大発会。28日の大納会と比べて452円安ととんだお年玉を受け取ったのでしたが、このお年玉送り主はアップルのクックCEO。前日3日アップルの業績の下方修正発表により、NYダウは660$の下落、その流れを引き継いでの日本株の下げでした。また、3日の円ドルレートは一時104円台と数分間で5円も急騰(ドル安)しました。米中の貿易戦争は中国企業への悪影響が大きいと思われていたところ、米国への影響も予想外に大きいというショックがさらにダウの下げを加速したということでしょう。
さすがにここまで世界を揺るがす事態となると、根本的対応をせざるを得ないということで金融面ではFRBが利上げスピードを抑える方向に転換、米中も貿易戦争の解決に向けて妥協点を真剣に探り始めているようです。こうした流れを市場が織り込み始めているわけですが、果たして今後株価も底を打ってめでたしめでたしとなるのでしょうか。
残念ながらそうは思えません。
現在、市場変動の背後にあるのは複合的リスクだからです。中国と米国という二巨大市場で貿易というモノの流れが停滞し始めており、その影響が他の先進国や新興国に広がるので世界経済が減速するのは明白です。また金融(カネ)面では、リーマンショックの影響を吸収すべく世界中の中央銀行が緩和策を続けてきたマネーが吸収されずに溢れかえったったままです。カネの行き場がないのにモノの流れが制限され、実体経済にカネが回っていかなければカネの価値は下がり経済は低迷します。
これまで起きてきた世界危機は原因となった国が限定され、時間的にもタイムラグを伴っていました。またその影響の拡散を防ぐため、各国が協調して手を打つことでなんとか乗り越えてきたというのが実態です。
今回の米中貿易戦争はその何れもが異なります。世界の主要国が共通の認識と方向性をもって解決にあたる道筋が見えれば、やがて市場の行き過ぎが是正されるというのが「リスクの織り込み」ということでしょうが、歩調が合っているとは言い難いのが現実。過去に例を見ない形の今回の危機、どのような結末を迎えるのか注意深く見ておく必要があります。
2018.12.18
危険水域
日米共に、株価の下落幅拡大が目立つようになってきました。株価はEPS(一株利益)とPER(株価収益率)の積で決まりますが、この2つが今後も下落するリスクが高まっています。背景は米中貿易戦争と米中先端技術の主導権争いです。
米中両国が高い関税をかけあえば、お互いの輸出低下につながります。企業にとってみると既存の販売先が縮小するので、売上げが減少します。またコストを最小化すべく世界中に張り巡らされたサプライチェーンは再構築を迫られ、過剰な経費を負担することになるでしょう。この結果、企業は売上げ減少、コスト上昇、利益減少により予測EPSは低下を免れません。
一方、関税のかけ合いは両国の経済成長を低下させるので、GDPNo.1,2の成長低下により世界の他の国々への影響は計り知れものとなること必定です。また関税のかけ合いは輸入物価の上昇を意味するので消費(GDPに占める割合最大)を低下させます。最終的に、両国の消費者がそのつけを払わされることになってしまいます。
ざっくり言うと、一国の名目GDPは市場PERの分子(株式時価総額)に連動しているので、経済の縮小なら予測市場PERは低下してゆくことになります。かくして、予測個別EPSと予測市場PERは手を携えるようにして低下してゆき、その積である個別株価の下落は不可避となってしまいます。
今月3日、米国で逆イールド・スプレッド現象が発生しました。(2年債と5年債の利回り逆転。2年債:2.82%、5年債:2.81%)2年と5年のイールド・スプレッドはその後も継続しています。過去逆イールド・スプレッドは過去2回発生しており、発生後しばらくして大きな経済危機が起きています。一回目はITバブル崩壊、2回目は住宅バブル崩壊です。
債券利回りは長期のものほど高く、短期物は低いのが正常な姿なので、この逆転発生が意味するところは、足元よりも将来のほうが景気悪化するという不気味なサインであります。(通常yield spreadは2年債と10年債で比較することになっており、今のところ10年債との比較では逆イールドを免れている。3日の10年債利回り:2.97%)
債券や株は将来を敏感に反映します。両者とも現状が危険水域にあることを警告しているようです。
米中両国が高い関税をかけあえば、お互いの輸出低下につながります。企業にとってみると既存の販売先が縮小するので、売上げが減少します。またコストを最小化すべく世界中に張り巡らされたサプライチェーンは再構築を迫られ、過剰な経費を負担することになるでしょう。この結果、企業は売上げ減少、コスト上昇、利益減少により予測EPSは低下を免れません。
一方、関税のかけ合いは両国の経済成長を低下させるので、GDPNo.1,2の成長低下により世界の他の国々への影響は計り知れものとなること必定です。また関税のかけ合いは輸入物価の上昇を意味するので消費(GDPに占める割合最大)を低下させます。最終的に、両国の消費者がそのつけを払わされることになってしまいます。
ざっくり言うと、一国の名目GDPは市場PERの分子(株式時価総額)に連動しているので、経済の縮小なら予測市場PERは低下してゆくことになります。かくして、予測個別EPSと予測市場PERは手を携えるようにして低下してゆき、その積である個別株価の下落は不可避となってしまいます。
今月3日、米国で逆イールド・スプレッド現象が発生しました。(2年債と5年債の利回り逆転。2年債:2.82%、5年債:2.81%)2年と5年のイールド・スプレッドはその後も継続しています。過去逆イールド・スプレッドは過去2回発生しており、発生後しばらくして大きな経済危機が起きています。一回目はITバブル崩壊、2回目は住宅バブル崩壊です。
債券利回りは長期のものほど高く、短期物は低いのが正常な姿なので、この逆転発生が意味するところは、足元よりも将来のほうが景気悪化するという不気味なサインであります。(通常yield spreadは2年債と10年債で比較することになっており、今のところ10年債との比較では逆イールドを免れている。3日の10年債利回り:2.97%)
債券や株は将来を敏感に反映します。両者とも現状が危険水域にあることを警告しているようです。
2018.12.04
行列の出来る店@ワイキキ
ハワイのオアフ島、アラモアナ公園から西に向かって大規模な開発が進んでいます。ワードという新たに開発の進んでいる地区には、新しいコンドミニアム、whole foods(Amazonが買収したスーパーマーケット、品揃え豊富で新鮮な素材を扱っていることで有名)ショッピングゾーン等が広がっており、昔は倉庫地帯であったこの場所がオシャレな一帯に変身を遂げつつあります。
この開発はさらに西に延びており、何年か先(2025予定のようです)にはカポレイ(真珠湾西側)を起点として、空港を通りハワイ最大の人気商業施設「アラモアナショッピングセンター」まで電車が通るそうです。アメリカはハワイに限らず車社会が常識で、そもそも電車が通ることが珍しいので、これは画期的なプロジェクト。電車はワイキキ地域には乗り入れないので、ワイキキのホテルに宿泊する観光客はアラモアナで下車してタクシーかバスに乗り換えるということになると思われます。
ワイキキエリアでいつ行っても行列が出来ている店があります。1つはカラカウア通りに面したEggs’ Things。卵を使った朝食と、ホイップクリームとナッツが贅沢に乗っているパンケーキがウリの店。価格は$10~$13とお手頃で、大きく開いた窓からはワイキキビーチが目の前というロケーション。同じ食事をするなら景色の良いところを選びたい、ということで並んででも待つということなのでしょう。ホイップクリームの盛りっぷりも人気の秘密と思いました。
もう1つは道路を一本内陸に入ったクヒオ通り沿いにある丸亀製麺。ハワイにうどんはミスマッチな感じがするので、何故こんなに人気があるのか正直、理解に苦しんだ挙句メニューを見てみました。うどん、てんぷらなど日本よりも値段は高めですが、物価の高いハワイにあってこの値段は価格破壊の域にあり、出来たものを自分でテーブルに持っていくセルフ方式なのでチップも不要。 日本の料理は高いのが常識となっているのでこの値段はウケるのでしょう。開店時間も7:00~22:00と、いつ行っても並びさえすれば食べられるので時間を気にする必要もありません。
番外編は、Ruth’s Chris Steak House.ワイキキ・ビーチ・ウオークの2階。17:00開店ですがその前から店の前には行列が出来ています。ステーキハウスなので値は張りますが実に美味。米国農務省認定の最高級熟成牛肉を980°で焼き上げた肉が供されます。店の説明によれば、この店はもとニューオーリンズに住むルースさんが自分のレシピによるステーキハウスを開設するにあたり、自宅を抵当に入れて開始し、同地で営業したところ高い評判を得て、全米各地に展開するに至ったとのことです。
どの店も国籍や人種に関係なく行列ができる店ということになりますが、いくつか共通項があるように思います。一言で言うと4つのPがターゲットとする顧客の基準にマッチしているということです。(マーケティング戦略4つのP:price/place/product/promotion)
どの一つが欠けても行列はできないか、長くは続かないということになるのだと思われます。
この開発はさらに西に延びており、何年か先(2025予定のようです)にはカポレイ(真珠湾西側)を起点として、空港を通りハワイ最大の人気商業施設「アラモアナショッピングセンター」まで電車が通るそうです。アメリカはハワイに限らず車社会が常識で、そもそも電車が通ることが珍しいので、これは画期的なプロジェクト。電車はワイキキ地域には乗り入れないので、ワイキキのホテルに宿泊する観光客はアラモアナで下車してタクシーかバスに乗り換えるということになると思われます。
ワイキキエリアでいつ行っても行列が出来ている店があります。1つはカラカウア通りに面したEggs’ Things。卵を使った朝食と、ホイップクリームとナッツが贅沢に乗っているパンケーキがウリの店。価格は$10~$13とお手頃で、大きく開いた窓からはワイキキビーチが目の前というロケーション。同じ食事をするなら景色の良いところを選びたい、ということで並んででも待つということなのでしょう。ホイップクリームの盛りっぷりも人気の秘密と思いました。
もう1つは道路を一本内陸に入ったクヒオ通り沿いにある丸亀製麺。ハワイにうどんはミスマッチな感じがするので、何故こんなに人気があるのか正直、理解に苦しんだ挙句メニューを見てみました。うどん、てんぷらなど日本よりも値段は高めですが、物価の高いハワイにあってこの値段は価格破壊の域にあり、出来たものを自分でテーブルに持っていくセルフ方式なのでチップも不要。 日本の料理は高いのが常識となっているのでこの値段はウケるのでしょう。開店時間も7:00~22:00と、いつ行っても並びさえすれば食べられるので時間を気にする必要もありません。
番外編は、Ruth’s Chris Steak House.ワイキキ・ビーチ・ウオークの2階。17:00開店ですがその前から店の前には行列が出来ています。ステーキハウスなので値は張りますが実に美味。米国農務省認定の最高級熟成牛肉を980°で焼き上げた肉が供されます。店の説明によれば、この店はもとニューオーリンズに住むルースさんが自分のレシピによるステーキハウスを開設するにあたり、自宅を抵当に入れて開始し、同地で営業したところ高い評判を得て、全米各地に展開するに至ったとのことです。
どの店も国籍や人種に関係なく行列ができる店ということになりますが、いくつか共通項があるように思います。一言で言うと4つのPがターゲットとする顧客の基準にマッチしているということです。(マーケティング戦略4つのP:price/place/product/promotion)
どの一つが欠けても行列はできないか、長くは続かないということになるのだと思われます。
2018.10.27
Sound Cruising 2018
六本木、赤坂にあるライブハウス13軒。チケット代5000円也で5日間、期間中なら行ってみたいところに何回でも、というライブミュージック大サービス企画。今回初めてチケット購入し、何軒か行ってみました。
驚くなかれ、どこのライブハウスも満席。ジャズのみならず、ブルースやpopsなど幅広いジャンル、店ごとに出演者も多士済々、1杯1000円の飲み物をオーダーすること以外、何のコストもかからないのでこれまで行ったことのなかったライブハウスにも気軽に足を運ぶことができます。
この企画の優れているところは、客にもミュジシャンにも、店にも(多分)メリットがあるところ。通常、ライブハウスにはミュージック チャージ(3000円~4000円)があり、加えて客は飲食費を払って音楽を楽しむということになっています。1軒の店で腰を落ち着けてひいきのミュジシャンの歌や演奏を聴くということになるので、他のライブハスやミュジシャンに巡り合うチャンスは制限されてしまいます。しかし、この企画に乗っかるとこれまで知らなかった店やミュジシャンをたくさん知ることになります。
また、特別なPRをしなくとも見たり聴いたりしてもらう機会をどんどん増やすことが出来るので、ミュジシャンにとってもありがたいイベントとなっていると思われます。音楽の場合、実際に来てもらって聴いてもらい、雰囲気を味わってもらわなければその魅力は十分に伝わりません。まさか道で客引きをするわけにもいかず、同じお客に足を運んでもらうにも限度があるでしょうから、見込み客を増やすのが一番良いのです。しかしネットに写真を載せたりブログを書いたりによる新規開拓は限度があります。百聞は一見にしかずであります。
ライブハウスにとってのメリットはずばり、新規客開拓です。大体においてライブハウスは敷居が高く感じられ、気軽にひょいひょいはいるような所ではないというのが実感です。
固く閉ざされたドアの向こう側でどのような世界が繰り広げられているのかわからず、また一度入ったらなかなか抜け出しにくい雰囲気を感じて一歩踏み込む勇気を持てずにいる音楽愛好家も少なくないと思われます。そのような気持ちのバリアーを振り払ってくれる効果が期待できます。
もう一つ店にとっての経営上のメリットは、観客回転数が高くなることです。お客は1杯飲んで、その店での演奏を堪能したら、また別の店に出向いて1杯飲みながら違うミュジシャンの演奏を楽しむということが気楽にできるので、2~3軒ライブハウスのはしごをするのが普通です。店からすると1顧客の滞在時間が短く、入れ替わりでお客が入るので、顧客数は増えます。客単価は減っても、回転数増加で収入は確保できるでしょうし、各店ともcash on delivery(飲むたびに現金で決済)で統一しているので店舗運営コストも抑えられます。万一、十分に回収できなかったとしても広告宣伝費と考えれば安いものでしょう。
世の中は音楽の世界に限らず、異なる個人の好みを手軽に安く満足させられる方向に動いています。選択肢は多いほど良いというものではありませんが、各自の趣味嗜好にあった選択が出来やすくすることが、結果的にビジネスの繁栄にも繋がるのではないかと思わされたクルージングの一夜でした。
驚くなかれ、どこのライブハウスも満席。ジャズのみならず、ブルースやpopsなど幅広いジャンル、店ごとに出演者も多士済々、1杯1000円の飲み物をオーダーすること以外、何のコストもかからないのでこれまで行ったことのなかったライブハウスにも気軽に足を運ぶことができます。
この企画の優れているところは、客にもミュジシャンにも、店にも(多分)メリットがあるところ。通常、ライブハウスにはミュージック チャージ(3000円~4000円)があり、加えて客は飲食費を払って音楽を楽しむということになっています。1軒の店で腰を落ち着けてひいきのミュジシャンの歌や演奏を聴くということになるので、他のライブハスやミュジシャンに巡り合うチャンスは制限されてしまいます。しかし、この企画に乗っかるとこれまで知らなかった店やミュジシャンをたくさん知ることになります。
また、特別なPRをしなくとも見たり聴いたりしてもらう機会をどんどん増やすことが出来るので、ミュジシャンにとってもありがたいイベントとなっていると思われます。音楽の場合、実際に来てもらって聴いてもらい、雰囲気を味わってもらわなければその魅力は十分に伝わりません。まさか道で客引きをするわけにもいかず、同じお客に足を運んでもらうにも限度があるでしょうから、見込み客を増やすのが一番良いのです。しかしネットに写真を載せたりブログを書いたりによる新規開拓は限度があります。百聞は一見にしかずであります。
ライブハウスにとってのメリットはずばり、新規客開拓です。大体においてライブハウスは敷居が高く感じられ、気軽にひょいひょいはいるような所ではないというのが実感です。
固く閉ざされたドアの向こう側でどのような世界が繰り広げられているのかわからず、また一度入ったらなかなか抜け出しにくい雰囲気を感じて一歩踏み込む勇気を持てずにいる音楽愛好家も少なくないと思われます。そのような気持ちのバリアーを振り払ってくれる効果が期待できます。
もう一つ店にとっての経営上のメリットは、観客回転数が高くなることです。お客は1杯飲んで、その店での演奏を堪能したら、また別の店に出向いて1杯飲みながら違うミュジシャンの演奏を楽しむということが気楽にできるので、2~3軒ライブハウスのはしごをするのが普通です。店からすると1顧客の滞在時間が短く、入れ替わりでお客が入るので、顧客数は増えます。客単価は減っても、回転数増加で収入は確保できるでしょうし、各店ともcash on delivery(飲むたびに現金で決済)で統一しているので店舗運営コストも抑えられます。万一、十分に回収できなかったとしても広告宣伝費と考えれば安いものでしょう。
世の中は音楽の世界に限らず、異なる個人の好みを手軽に安く満足させられる方向に動いています。選択肢は多いほど良いというものではありませんが、各自の趣味嗜好にあった選択が出来やすくすることが、結果的にビジネスの繁栄にも繋がるのではないかと思わされたクルージングの一夜でした。
2018.10.09
ボケ知らずの歩き方
高齢化とともに、認知症のリスクがますますクローズアップされるようになってきました。
人間だれしも、ただ長生きすることだけを望んでいるわけではなく、健康で生き生きと人生を楽しめてこその長寿と思っているはずです。
最近テレビでは健康番組がやたら目につきます。認知症に限らず、それぞれ専門分野の医師が出演して懇切丁寧な予防法や原因説明をしてくれるのでつい観てしまうという方も多いのではないでしょうか。日本が世界の中でも長寿国家である理由の一端を間違いなく担っていると思います。
病気になる人が増えると医療費が社会保障費を押し上げ財政を圧迫するので、健康なお年寄りが増えることは日本にとっても良いことです。娯楽として見ることが、個人にとっても国家にとっても直接的な利益をもたらす番組を惜しげもなく放送している国は多くはないと思われます。
ただ、番組の数に比例して扱う病気の種類や病気にならない為の対処法等が増加の一途をたどっているため、健康オタクのようにならないとも限りません。また、長寿は年金の支払い増加という財政負担が発生することも事実ではあります。
政府は首相を議長とする「未来投資会議」で雇用年齢を65歳以上に伸ばす、70歳を超えて公的年金の受給を開始できる制度改正等を検討してゆくようです。年金をもらってのんびり余生を送るという希望を胸に頑張ってきた方々には、いささか肩身の狭い社会になってゆくかもしれません。
先日偶然に見たテレビで、あることをすると認知症の発生率が1/7になったというのがありました。認知症は全身の血流が悪くなって、これにつれて頭の血流も悪くなることが原因の一つとなるとのこと。その為にやるべきは、一日5,000歩歩くことだそうです。
ワタシも徘徊と間違われないようにしながら、歩く時間をのばしてみようかなと思ったのでした。
人間だれしも、ただ長生きすることだけを望んでいるわけではなく、健康で生き生きと人生を楽しめてこその長寿と思っているはずです。
最近テレビでは健康番組がやたら目につきます。認知症に限らず、それぞれ専門分野の医師が出演して懇切丁寧な予防法や原因説明をしてくれるのでつい観てしまうという方も多いのではないでしょうか。日本が世界の中でも長寿国家である理由の一端を間違いなく担っていると思います。
病気になる人が増えると医療費が社会保障費を押し上げ財政を圧迫するので、健康なお年寄りが増えることは日本にとっても良いことです。娯楽として見ることが、個人にとっても国家にとっても直接的な利益をもたらす番組を惜しげもなく放送している国は多くはないと思われます。
ただ、番組の数に比例して扱う病気の種類や病気にならない為の対処法等が増加の一途をたどっているため、健康オタクのようにならないとも限りません。また、長寿は年金の支払い増加という財政負担が発生することも事実ではあります。
政府は首相を議長とする「未来投資会議」で雇用年齢を65歳以上に伸ばす、70歳を超えて公的年金の受給を開始できる制度改正等を検討してゆくようです。年金をもらってのんびり余生を送るという希望を胸に頑張ってきた方々には、いささか肩身の狭い社会になってゆくかもしれません。
先日偶然に見たテレビで、あることをすると認知症の発生率が1/7になったというのがありました。認知症は全身の血流が悪くなって、これにつれて頭の血流も悪くなることが原因の一つとなるとのこと。その為にやるべきは、一日5,000歩歩くことだそうです。
ワタシも徘徊と間違われないようにしながら、歩く時間をのばしてみようかなと思ったのでした。
2018.09.10
一杯6000円のコーヒー
8月に入ってトルコの通貨リラが一日で20%も下落しました。トルコの対外債務は4500億ドルを超えており外貨準備高の4倍近い水準にあります。通貨が下落すると返済しなければならない外貨建て借金が膨らみますが、返済に充てられる外貨が借金の四分の一しかないので、貸付の多い外国銀行(スペイン、フランス、イタリア)に懸念が広がっています。またトルコの国債、企業の発行した債券はデフォルト(利払い不能)の恐れが出てくる為、価格が下落して投資家は損失を被っています。
おカネの価値が下がると輸入価格が上昇する為、国内でインフレが発生します。(トルコの8月のインフレ率は18%)インフレはおカネの価値が下がることを意味するので、20%下落した日には多くの人がリラをドルやユーロ等に替えに走りました。この時コーヒーを飲んでいて出遅れた人は、瞬く間に6,000円の損失を被ったとのことです。(日経新聞による)
タンゴの国、南米アルゼンチンは過去に何度かデフォルトをおこしていますが、IMFの支援を受け入れて一息ついていたところでした。そこへトルコリラの大幅下落のニュースが入りペソに波及、あわてた中央銀行は政策金利を大幅に引き上げましたが、効果がないばかりか悪化してしまいました。ペソは年初と比較して50%も下落、インフレ率は30%を超えています。
通貨下落は伝染します。特に経済的基礎体力の弱い新興国には瞬く間に波及します。南アフリカのランド、ブラジルのレアル等も月間で10%程度の下落です。今後、貿易による悪影響が中国に及ぶと東南アジア諸国の通貨に波及していくことは避けられないものと思われます。
1997年に通貨危機がありましたが、根本原因は今回も同様です。すなわち、米国の金利引き上げが先進国のマネーをドルに引き付け、新興国に流れ込んでいた資金が流出するという構図です。新興国からは資金が流出するばかりでなくドル建てで借りていた債務が膨張して、借入したとき以上の返済を迫られそれらが自国通貨の下落につながるという循環です。
リーマンショックからちょうど10年目の今年、また同じような危機が起こらないことを願うばかりですが、地震と同じように長い年月をかけて歪みがたまり一挙に跳ねるという現象は、マクロ経済にも当てはまります。
米国の金利引き上げは、現在は好調な米国経済がインフレに向かうことを防ぐための手段なので実行されねばなりませんが、問題はトランプ政権が貿易に関税をかけてモノの流れまでも歪ませていることです。金融と物流の歪みが一挙に跳ねたとき、世界はどのような景色を見ることになるのでしょうか。
世界のどこかで、トルココーヒーより苦く、6000円よりも高いコーヒーを飲まねばならない国が増えないことを祈りたいと思います。
おカネの価値が下がると輸入価格が上昇する為、国内でインフレが発生します。(トルコの8月のインフレ率は18%)インフレはおカネの価値が下がることを意味するので、20%下落した日には多くの人がリラをドルやユーロ等に替えに走りました。この時コーヒーを飲んでいて出遅れた人は、瞬く間に6,000円の損失を被ったとのことです。(日経新聞による)
タンゴの国、南米アルゼンチンは過去に何度かデフォルトをおこしていますが、IMFの支援を受け入れて一息ついていたところでした。そこへトルコリラの大幅下落のニュースが入りペソに波及、あわてた中央銀行は政策金利を大幅に引き上げましたが、効果がないばかりか悪化してしまいました。ペソは年初と比較して50%も下落、インフレ率は30%を超えています。
通貨下落は伝染します。特に経済的基礎体力の弱い新興国には瞬く間に波及します。南アフリカのランド、ブラジルのレアル等も月間で10%程度の下落です。今後、貿易による悪影響が中国に及ぶと東南アジア諸国の通貨に波及していくことは避けられないものと思われます。
1997年に通貨危機がありましたが、根本原因は今回も同様です。すなわち、米国の金利引き上げが先進国のマネーをドルに引き付け、新興国に流れ込んでいた資金が流出するという構図です。新興国からは資金が流出するばかりでなくドル建てで借りていた債務が膨張して、借入したとき以上の返済を迫られそれらが自国通貨の下落につながるという循環です。
リーマンショックからちょうど10年目の今年、また同じような危機が起こらないことを願うばかりですが、地震と同じように長い年月をかけて歪みがたまり一挙に跳ねるという現象は、マクロ経済にも当てはまります。
米国の金利引き上げは、現在は好調な米国経済がインフレに向かうことを防ぐための手段なので実行されねばなりませんが、問題はトランプ政権が貿易に関税をかけてモノの流れまでも歪ませていることです。金融と物流の歪みが一挙に跳ねたとき、世界はどのような景色を見ることになるのでしょうか。
世界のどこかで、トルココーヒーより苦く、6000円よりも高いコーヒーを飲まねばならない国が増えないことを祈りたいと思います。
2018.06.09
オリンピック後の日本
オリンピックが終わった後、日本国内にはインフラ分野で有望な投資先がなくなってゆくのではないかと危惧されます。また、2025年には65歳以上が人口の30%に増加、高齢化が一気に進むと報じられていますが、労働人口が減り高齢者が増えるということは、税収が減り、社会保障を中心とする負担は増えることを意味します。こうした問題は財政赤字を拡大させるとともに経済力を低下させます。今後の日本の行く末に期待はもてるのでしょうか。
一方、日本にはオリンピックまでにインフラ開発や交通手段のKnowhow蓄積が加速し、過去の貧弱な道路やうんざりするような渋滞を解消してきた知恵や経験が山積みになっているはずです。例えばC2(首都高中央環状線)は日本で一番長い山手トンネル(8.2Km)を開通させ、都内の渋滞を避けながら目的地までスムーズな運行を可能にしました。C2の外側には東京外かく環状道路が完成しつつあり、さらにその外側には圏央道が出来上がっています。その結果、C2に乗れば都内ばかりでなく地方へも、国道や県道を経由することなく行くことが出来るのです。中央高速、関越道、東北道、常磐道、東関道、東名高速などへのアクセスもスムーズ。地方への物流や、レジャーの連絡道としても一挙に利便性が増したと実感できています。
世界を見渡すとこうした分野に工夫が求められている国々は枚挙に暇がありません。
例えばバリ島は世界に冠たるリゾート地ではありますが、リゾートに至る道幅は極めて狭く渋滞は日常茶飯事。排気ガスによる空気の汚れや車線すらない一本道の道路など、事故や危険と隣り合わせになっている状況。現状を放置している限り行き詰まることは明白で、アジア諸国にはこのような問題がいたるところに転がっています。
タイ、ベトナム、マレーシアなど回ってみれば気付くことですが、共通して解決されねばならないながら放置されているのが道路交通分野です。これら新興国は押しなべて人口増加のスピードが速い。このままだと人口が減少していかざるを得ない日本とは、対極にあります。またアマゾン効果等による物流増加対応の為の道路依存は今後も世界各国で高まる一方でしょう。
こうした中、日本に求められているのは単に工事を受注するということだけではなく、「渋滞を解消する」という施策とパッケージにした解決策提供であると考えます。
日本が過去培ってきた渋滞解消のknowhowには高い経済価値があると評価されると思います。3つの環状道路が計画されたのは東京五輪の前年、1963年(日経新聞による)日本の場合、土地の買収等に時間がかかり10年近い年月を要した訳ですがこうした問題の少ない新興国では、もっと短期に解消させることができることでしょう。中国が一帯一路政策で西へと開発の手を伸ばすのを手を拱いてみている余裕は日本にはありません。「渋滞解消」をビジネスとして海外に提供することは双方の利益となるものと思われます。
一方、日本にはオリンピックまでにインフラ開発や交通手段のKnowhow蓄積が加速し、過去の貧弱な道路やうんざりするような渋滞を解消してきた知恵や経験が山積みになっているはずです。例えばC2(首都高中央環状線)は日本で一番長い山手トンネル(8.2Km)を開通させ、都内の渋滞を避けながら目的地までスムーズな運行を可能にしました。C2の外側には東京外かく環状道路が完成しつつあり、さらにその外側には圏央道が出来上がっています。その結果、C2に乗れば都内ばかりでなく地方へも、国道や県道を経由することなく行くことが出来るのです。中央高速、関越道、東北道、常磐道、東関道、東名高速などへのアクセスもスムーズ。地方への物流や、レジャーの連絡道としても一挙に利便性が増したと実感できています。
世界を見渡すとこうした分野に工夫が求められている国々は枚挙に暇がありません。
例えばバリ島は世界に冠たるリゾート地ではありますが、リゾートに至る道幅は極めて狭く渋滞は日常茶飯事。排気ガスによる空気の汚れや車線すらない一本道の道路など、事故や危険と隣り合わせになっている状況。現状を放置している限り行き詰まることは明白で、アジア諸国にはこのような問題がいたるところに転がっています。
タイ、ベトナム、マレーシアなど回ってみれば気付くことですが、共通して解決されねばならないながら放置されているのが道路交通分野です。これら新興国は押しなべて人口増加のスピードが速い。このままだと人口が減少していかざるを得ない日本とは、対極にあります。またアマゾン効果等による物流増加対応の為の道路依存は今後も世界各国で高まる一方でしょう。
こうした中、日本に求められているのは単に工事を受注するということだけではなく、「渋滞を解消する」という施策とパッケージにした解決策提供であると考えます。
日本が過去培ってきた渋滞解消のknowhowには高い経済価値があると評価されると思います。3つの環状道路が計画されたのは東京五輪の前年、1963年(日経新聞による)日本の場合、土地の買収等に時間がかかり10年近い年月を要した訳ですがこうした問題の少ない新興国では、もっと短期に解消させることができることでしょう。中国が一帯一路政策で西へと開発の手を伸ばすのを手を拱いてみている余裕は日本にはありません。「渋滞解消」をビジネスとして海外に提供することは双方の利益となるものと思われます。
2018.04.12
「嫌われる勇気」はビジネスに役立つか?
マズローとアドラーは承認欲求について正反対の立場を採っています。前者は人間の欲求の最高位に自己実現欲求を置き、そこに至るまでの一段階として承認欲求があるとしています。マズローの見解に従えば、人から認められたいというのはヒトとして当然の欲求ということになるのでしょう。
一方、アドラーは人から認められることに執着することが不幸につながるので、そうならない為にも「嫌われる勇気」をもつこと、これにより承認の欲求から自由になれるとしています。人に認められることを求めるより他者への貢献感が幸せにつながると考えているようです。フェースブック等の「いいね」の数が人間の価値の尺度という主張がありましたが、真向反対する立場だと思われます。
ビジネスの目的は自社製品やサービスを認知してもらい購買に結び付けることにあるので、出来るだけ多くの人に良いものと認めてもらわねば仕事として成り立ちません。多くのデータを分析してどのようなニーズがあるのかを導き出そうというのが最近のビッグデータ隆盛の背景です。従ってマズロー的承認欲求に執着するのは自然なことではあります。
一方、創作や芸術を追及している人達にとって重要なのは自らの中にある表現欲求に忠実であることです。たとえ人に認められなくとも自分の拘りを優先したいというのが創作者の本能なのだろうと思えます。不幸にも作品が世に受け入れられず、死後になってようやく世間が高い評価を下すようになった、という例は数多あります。世間に妥協しなかった彼らは「嫌われる勇気」を実践したということなのでしょう。
昨今のビジネスにおいて勝ち組となっている企業の中には、アドラー的要素を組織の中に組み込んで他との差別化を図っている企業が出てきています。必至になって顧客ニーズをリサーチしこれに応えようとするよりは、世の中にない新たな商品を提案して膨大なマーケットを自ら作り上げてしまうというスタイルです。
世の中にないもの、ということになると当然のことながらビッグデータをいくらリサーチしても何も出てきません。そこで、社員の労働時間の一定割合を本業の仕事と全く関係ないことに費やすことを許すことで新しいブレーク スルーを産みだそうということが試みられます。
アドラー的特質を持つイノベーターが社内から多く輩出されるような企業風土を作ること、それが、事業優位性の維持につながる時代に入っているのではないでしょうか。
一方、アドラーは人から認められることに執着することが不幸につながるので、そうならない為にも「嫌われる勇気」をもつこと、これにより承認の欲求から自由になれるとしています。人に認められることを求めるより他者への貢献感が幸せにつながると考えているようです。フェースブック等の「いいね」の数が人間の価値の尺度という主張がありましたが、真向反対する立場だと思われます。
ビジネスの目的は自社製品やサービスを認知してもらい購買に結び付けることにあるので、出来るだけ多くの人に良いものと認めてもらわねば仕事として成り立ちません。多くのデータを分析してどのようなニーズがあるのかを導き出そうというのが最近のビッグデータ隆盛の背景です。従ってマズロー的承認欲求に執着するのは自然なことではあります。
一方、創作や芸術を追及している人達にとって重要なのは自らの中にある表現欲求に忠実であることです。たとえ人に認められなくとも自分の拘りを優先したいというのが創作者の本能なのだろうと思えます。不幸にも作品が世に受け入れられず、死後になってようやく世間が高い評価を下すようになった、という例は数多あります。世間に妥協しなかった彼らは「嫌われる勇気」を実践したということなのでしょう。
昨今のビジネスにおいて勝ち組となっている企業の中には、アドラー的要素を組織の中に組み込んで他との差別化を図っている企業が出てきています。必至になって顧客ニーズをリサーチしこれに応えようとするよりは、世の中にない新たな商品を提案して膨大なマーケットを自ら作り上げてしまうというスタイルです。
世の中にないもの、ということになると当然のことながらビッグデータをいくらリサーチしても何も出てきません。そこで、社員の労働時間の一定割合を本業の仕事と全く関係ないことに費やすことを許すことで新しいブレーク スルーを産みだそうということが試みられます。
アドラー的特質を持つイノベーターが社内から多く輩出されるような企業風土を作ること、それが、事業優位性の維持につながる時代に入っているのではないでしょうか。
2017.08.19
フレンチ・クオーターの熱い夜
日本国内の音楽ライブ市場は2010年から2015年の5年で約2倍に拡大,(1600億→3400億)2020年以降には座席供給量が不足すると予想されています。(ぴあ総研調査)CD販売が縮小する一方、ライブには多数が足を運ぶというモノからコトへの流れ。
ライブビジネスのこの流れを一層加速させ定着させるには何が必要とされるでしょうか。
言うまでもないことですが、ライブ運営に必要なのは集客力。音楽好きが多数集まってライブ演奏を楽しみ、そこで飲食し、帰りがけにCD等物品を買ってくれれば利益は出ます。問題は2つあり、一つは集客力のあるミュジシャンは限られていること。テレビ等のメディアを通じて知名度の高まったミュジシャンには集客力がありますが運営者にとってはコスト高となり、加えて会場費、宣伝費などのリスクを抱えることになります。もう一つはジャンルがライブ会場によって限定されてしまうこと。殆どのライブハウスはジャンルが決まっており、ジャズライブハウスにビートルズ(そっくりさん)が出演することはなく、ロックのライブハウスで4ビートのジャズが演奏されることもありません。従って客はどんなジャンルを聴きたいのか、だれの演奏を聴きたいのか等を決め、その後出かけて行くという面倒なステップを踏むことになるでしょう。
ちょっと思い立ってライブにでも、と思い立った人のおそらく半数が今日は暑いのでまた今度、雨が降りそうなので次回に等ということになっているのではないかと思われます。
アメリカはミシシッピー州、ニューオリンズのフレンチ・クオーター地区にあるバーボンストリ-ト。このストリートの両側にライブハウスが軒を連ねており、演奏されている音楽はジャズ・R&B・ブルース・POPS等多岐に亘っています。
面白いのはどこも扉が開けっ放しとなっていること。従ってお客は自分の好みの音楽が聞こえているライブハウスに入って音楽を楽しみ、満足したらまた別の店に入るというライブハウス巡りが好きなだけ無料で出来るということです。お客は中で売られているビールを飲んだり、回ってくるバケツにチップを入れたりします。(ビールは有料だが特に高くもなく、チップは小額 でも入れなくとも良い。)空腹を覚えたら同じ通りに何軒もあるオイスターバーやレストラン、ファストフード店など好きなところで食事をして、またライブ巡りに行けば良いのです。
当然お客の滞在時間は長くなるので多額のお金が使われ、世界中から観光客を含む音楽好きが集まってくるので1年中人の波が絶えることがありません。ミュジシャンは耳の肥えたお客を引き付けられるよう切磋琢磨するのでレベルはどんどん高くなり、ストリートの店舗側もミュジシャンも毎日コンスタントに落とされる多額の$によって潤うという仕組み。有名どころの演奏を聞きたければバーボンストリートから少し離れたところにBB KING BLUES CLUBのようなライブハウス(有料)もあります。
地域振興においてヒト・モノ・カネの順番が逆というケースが散見されます。まずカネ(やファンド)を用意し膨大なコストをかけて箱モノを作り、しかる後に集客を図る。ところが往々にして思ったほどヒトが集まらず立派な建物が野ざらしにとなり投資が無駄に終わるというアレです。
バーボンストリートのライブハウスの建物は超豪華とは言いかねるグレードですが、演奏されている音楽レベルは高く、レストランの食事も満足のいくものでした。つまり所謂コンテンツ・ファーストの徹底が多くの顧客を引き寄せるというモデルです。
日本においても、音楽に特化したオトナのスポットとして運営するのに大いに参考になるものと思います。
また世界に発信すれば国内の音楽好きばかりでなくより多くの海外観光客を呼び込め、インバウンド需要を更に大きなものとすることができることでしょう。地域、ミュジシャン、飲食店、ライブハウスの四者全てにとって有益な仕組みたりうるではないか、と熱く思ったフレンチ・クオーターの夜でした。
ライブビジネスのこの流れを一層加速させ定着させるには何が必要とされるでしょうか。
言うまでもないことですが、ライブ運営に必要なのは集客力。音楽好きが多数集まってライブ演奏を楽しみ、そこで飲食し、帰りがけにCD等物品を買ってくれれば利益は出ます。問題は2つあり、一つは集客力のあるミュジシャンは限られていること。テレビ等のメディアを通じて知名度の高まったミュジシャンには集客力がありますが運営者にとってはコスト高となり、加えて会場費、宣伝費などのリスクを抱えることになります。もう一つはジャンルがライブ会場によって限定されてしまうこと。殆どのライブハウスはジャンルが決まっており、ジャズライブハウスにビートルズ(そっくりさん)が出演することはなく、ロックのライブハウスで4ビートのジャズが演奏されることもありません。従って客はどんなジャンルを聴きたいのか、だれの演奏を聴きたいのか等を決め、その後出かけて行くという面倒なステップを踏むことになるでしょう。
ちょっと思い立ってライブにでも、と思い立った人のおそらく半数が今日は暑いのでまた今度、雨が降りそうなので次回に等ということになっているのではないかと思われます。
アメリカはミシシッピー州、ニューオリンズのフレンチ・クオーター地区にあるバーボンストリ-ト。このストリートの両側にライブハウスが軒を連ねており、演奏されている音楽はジャズ・R&B・ブルース・POPS等多岐に亘っています。
面白いのはどこも扉が開けっ放しとなっていること。従ってお客は自分の好みの音楽が聞こえているライブハウスに入って音楽を楽しみ、満足したらまた別の店に入るというライブハウス巡りが好きなだけ無料で出来るということです。お客は中で売られているビールを飲んだり、回ってくるバケツにチップを入れたりします。(ビールは有料だが特に高くもなく、チップは小額 でも入れなくとも良い。)空腹を覚えたら同じ通りに何軒もあるオイスターバーやレストラン、ファストフード店など好きなところで食事をして、またライブ巡りに行けば良いのです。
当然お客の滞在時間は長くなるので多額のお金が使われ、世界中から観光客を含む音楽好きが集まってくるので1年中人の波が絶えることがありません。ミュジシャンは耳の肥えたお客を引き付けられるよう切磋琢磨するのでレベルはどんどん高くなり、ストリートの店舗側もミュジシャンも毎日コンスタントに落とされる多額の$によって潤うという仕組み。有名どころの演奏を聞きたければバーボンストリートから少し離れたところにBB KING BLUES CLUBのようなライブハウス(有料)もあります。
地域振興においてヒト・モノ・カネの順番が逆というケースが散見されます。まずカネ(やファンド)を用意し膨大なコストをかけて箱モノを作り、しかる後に集客を図る。ところが往々にして思ったほどヒトが集まらず立派な建物が野ざらしにとなり投資が無駄に終わるというアレです。
バーボンストリートのライブハウスの建物は超豪華とは言いかねるグレードですが、演奏されている音楽レベルは高く、レストランの食事も満足のいくものでした。つまり所謂コンテンツ・ファーストの徹底が多くの顧客を引き寄せるというモデルです。
日本においても、音楽に特化したオトナのスポットとして運営するのに大いに参考になるものと思います。
また世界に発信すれば国内の音楽好きばかりでなくより多くの海外観光客を呼び込め、インバウンド需要を更に大きなものとすることができることでしょう。地域、ミュジシャン、飲食店、ライブハウスの四者全てにとって有益な仕組みたりうるではないか、と熱く思ったフレンチ・クオーターの夜でした。
2016.12.02
トランプは、めくってみなけりゃ判らない
トランプ氏が大統領選に勝利した翌日、朝刊を見ると「今後成長率を現在の2倍に引き上げる」との公約が発表されていました。「アメリカを再び偉大な国にする」というキャンペーン標語は何度も聞いていましたが、「メキシコとの国境に壁を作る」とか「移民を本国に送還する」など荒唐無稽な発言の印象が強すぎて、どのようにアメリカを偉大な国にするのかをまともに聞く気にもならず、本人も語らなかったと思われます。
これまでのところ発表されている具体策は経済政策(貿易を除く)に関してみる限り合理的なので、もっと早く語ってほしかったと思っている人は多かったのではないでしょうか。減税と財政支出で経済を刺激して持続的成長につなげるという施策ですので、ここまで株価が上昇してきたのに不思議はありません。
問題は為替です。選挙期間中トランプ候補は一貫してドルは高すぎると主張してきましたし、金利引き上げを示唆したFRBのイエレン議長をクビにするとまで言っています。しかしながらトランプ氏の施策には大いなる矛盾があります。具体策にある経済政策が奏功し、経済成長の結果インフレ率が上昇すれば米ドルは高くなるのが道理です。実際、現在のところ米ドルはほとんどの国の通貨に対して上昇しています。しかしトランプ氏は米ドルを安くしたいと言っているのです。どのようにその矛盾を解決するのでしょうか。
主たる方法は2つ考えられます。①FRBに圧力をかけて利子率を経済成長率以下に抑え込む。②主要国を集めてドル安、主要国通貨高となるよう誘導する。
いずれも経済的合理性を無視した危険な方法で、結果としてバブルを引き起こす可能性を否定できません。①は米国内にコントロール不能なバブルを発生させる恐れ、②は米国の要求を受け入れた国がバブルに巻き込まれるという可能性です。
②は過去、日本で実際に起きた事実です。1985年レーガン政権が貿易、財政の双子の赤字を解消する為、各国財務大臣を呼んで決定されたプラザ合意。目指したのはドル安でした。当時、日本の当局はこの合意を実行する為円買いドル売りを、米国は金利引き下げを行いました。この結果円高が急激に進み日銀は金利引き下げを継続して行なった為、市場に溢れ出たお金(過剰流動性)が株や土地に流れ込んで異常な高値を形成するバブルが出現したのでした。
本来、輸出が好調で経済が活況なら金利は引き上げられねばなりません。にもかかわらず米国の円高誘導への要請に応じて、逆に金利を引き下げてしまったことがバブルを誘発したというのが歴史の示すところ。その後のバブル崩壊により日本は20年以上にもわたるデフレ経済に苦しむことになりました。他国からの要請に対してどのようなスタンスで臨むのが国益に適うのか、真剣に考えなければならない実例だと思います。
ドル安に関してはもう一点、自己実現的に達成されてしまうケースが考えられます。保護主義に基づく貿易収支の悪化に財政出動による財政悪化の加わった、いわゆる双子の赤字の拡大。現時点でも既にNAFTA見直しやTPPへの不参加表明という保護貿易主義を前面に押し出しているので、やがては自然にドル安とならざるを得ないという見方もできるでしょう。
来年1月にはトランプ大統領が誕生することが決まっています。米国第一主義を掲げるトランプ政権が対外的にどのような(無謀な?)政策を打ち出してくるのか今のところ全くわかりませんが、世界にとっての経済合理性に則ったものであるか否か、この観点から注意深く見守っていかねばならないと思います。
これまでのところ発表されている具体策は経済政策(貿易を除く)に関してみる限り合理的なので、もっと早く語ってほしかったと思っている人は多かったのではないでしょうか。減税と財政支出で経済を刺激して持続的成長につなげるという施策ですので、ここまで株価が上昇してきたのに不思議はありません。
問題は為替です。選挙期間中トランプ候補は一貫してドルは高すぎると主張してきましたし、金利引き上げを示唆したFRBのイエレン議長をクビにするとまで言っています。しかしながらトランプ氏の施策には大いなる矛盾があります。具体策にある経済政策が奏功し、経済成長の結果インフレ率が上昇すれば米ドルは高くなるのが道理です。実際、現在のところ米ドルはほとんどの国の通貨に対して上昇しています。しかしトランプ氏は米ドルを安くしたいと言っているのです。どのようにその矛盾を解決するのでしょうか。
主たる方法は2つ考えられます。①FRBに圧力をかけて利子率を経済成長率以下に抑え込む。②主要国を集めてドル安、主要国通貨高となるよう誘導する。
いずれも経済的合理性を無視した危険な方法で、結果としてバブルを引き起こす可能性を否定できません。①は米国内にコントロール不能なバブルを発生させる恐れ、②は米国の要求を受け入れた国がバブルに巻き込まれるという可能性です。
②は過去、日本で実際に起きた事実です。1985年レーガン政権が貿易、財政の双子の赤字を解消する為、各国財務大臣を呼んで決定されたプラザ合意。目指したのはドル安でした。当時、日本の当局はこの合意を実行する為円買いドル売りを、米国は金利引き下げを行いました。この結果円高が急激に進み日銀は金利引き下げを継続して行なった為、市場に溢れ出たお金(過剰流動性)が株や土地に流れ込んで異常な高値を形成するバブルが出現したのでした。
本来、輸出が好調で経済が活況なら金利は引き上げられねばなりません。にもかかわらず米国の円高誘導への要請に応じて、逆に金利を引き下げてしまったことがバブルを誘発したというのが歴史の示すところ。その後のバブル崩壊により日本は20年以上にもわたるデフレ経済に苦しむことになりました。他国からの要請に対してどのようなスタンスで臨むのが国益に適うのか、真剣に考えなければならない実例だと思います。
ドル安に関してはもう一点、自己実現的に達成されてしまうケースが考えられます。保護主義に基づく貿易収支の悪化に財政出動による財政悪化の加わった、いわゆる双子の赤字の拡大。現時点でも既にNAFTA見直しやTPPへの不参加表明という保護貿易主義を前面に押し出しているので、やがては自然にドル安とならざるを得ないという見方もできるでしょう。
来年1月にはトランプ大統領が誕生することが決まっています。米国第一主義を掲げるトランプ政権が対外的にどのような(無謀な?)政策を打ち出してくるのか今のところ全くわかりませんが、世界にとっての経済合理性に則ったものであるか否か、この観点から注意深く見守っていかねばならないと思います。
2016.03.14
「マネー・ショート 華麗なる大逆転」感想と疑問
映画はリーマンショック発生の原因となった米国不動産バブルと、そうした不動産への抵当権担保証券(MBS)の欠陥に気付いたヘッジファンド・マネージャーがこれを売るべき(ショート)との確信を持ったことから、同じ効果を発揮出来る関連商品(CDS)を使って勝負をかけ勝利するに至ったプロセスを描いた実話ストーリー。
リーマンショックがどのように引き起こされたのか、その引き金となった金融商品はどんな欠陥を持っていたのか等、難しい話を分かりやすく解き明かしています。専門用語は美女が出てきて解説してくれる等の工夫もあって、2時間超の映画を退屈することなく楽しめました。(美女の裸体と手にしたシャンパンにはグッときて解説の内容は殆ど頭に残っていませんが。)
MBSの欠陥に気付いて「ショート」にかけたヘッジファンド・マネージャー達の心理状況が見どころです。不合理であるとの確信をもってCDSを仕入れる為訪問した投資銀行では、自らの見解を説明するや、そんなはずはないと馬鹿にされ変人扱いされます。必ず下げると確信していたMBSは上昇を続け、組成したファンド利回りは悪化の一途。出資者からも背を向けられ返金を求められ、訴訟まで起こされます。
最終的には「ショート」にかけた少数派の判断は正しかったことがあきらかになり、価格は暴落を始めます。しかしMBS関連商品を大量に保有、CDSを提供等していた証券や銀行には莫大な損失が積み上がり、世界中のカネの流れが止まる寸前の大パニックに陥ります。「ショート」にかけたヘッジファンドは大きな利益を手にするのですが、世界を恐慌寸前まで追い込むきっかけを作った罪悪感のようなものを内包した苦い勝利であったように描かれています。
この映画は一度観ただけなので、どこまで正確にお伝え出来ているかわかりませんが、個人的な感想と疑問を書いておきます。
(感想)
マーケットの趨勢に逆らって投資することのストレス、そして何よりも権威に対抗して自らの判断を貫き通すことの過酷さなどが体感できる映画でした。
(疑問)
格付け機関(スタンダード&プアーズやムーディーズ等)がMBS等のリスクを正当に評価し、妥当な格付けをしていれば不当な価格、関連商品の過剰な拡大は防げたはずです。分析して妥当な格付けを行い、投資家に情報提供するのが仕事である格付け機関が何故ヘッジファンド・マネージャー以下の判断しか出来なかったのか、不明です。
リーマンショックがどのように引き起こされたのか、その引き金となった金融商品はどんな欠陥を持っていたのか等、難しい話を分かりやすく解き明かしています。専門用語は美女が出てきて解説してくれる等の工夫もあって、2時間超の映画を退屈することなく楽しめました。(美女の裸体と手にしたシャンパンにはグッときて解説の内容は殆ど頭に残っていませんが。)
MBSの欠陥に気付いて「ショート」にかけたヘッジファンド・マネージャー達の心理状況が見どころです。不合理であるとの確信をもってCDSを仕入れる為訪問した投資銀行では、自らの見解を説明するや、そんなはずはないと馬鹿にされ変人扱いされます。必ず下げると確信していたMBSは上昇を続け、組成したファンド利回りは悪化の一途。出資者からも背を向けられ返金を求められ、訴訟まで起こされます。
最終的には「ショート」にかけた少数派の判断は正しかったことがあきらかになり、価格は暴落を始めます。しかしMBS関連商品を大量に保有、CDSを提供等していた証券や銀行には莫大な損失が積み上がり、世界中のカネの流れが止まる寸前の大パニックに陥ります。「ショート」にかけたヘッジファンドは大きな利益を手にするのですが、世界を恐慌寸前まで追い込むきっかけを作った罪悪感のようなものを内包した苦い勝利であったように描かれています。
この映画は一度観ただけなので、どこまで正確にお伝え出来ているかわかりませんが、個人的な感想と疑問を書いておきます。
(感想)
マーケットの趨勢に逆らって投資することのストレス、そして何よりも権威に対抗して自らの判断を貫き通すことの過酷さなどが体感できる映画でした。
(疑問)
格付け機関(スタンダード&プアーズやムーディーズ等)がMBS等のリスクを正当に評価し、妥当な格付けをしていれば不当な価格、関連商品の過剰な拡大は防げたはずです。分析して妥当な格付けを行い、投資家に情報提供するのが仕事である格付け機関が何故ヘッジファンド・マネージャー以下の判断しか出来なかったのか、不明です。
2016.02.01
黒田さんが偉いワケ
日銀の役割は「物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資する」(日銀法2条)こととなっています。日本の現状を見ると、インフレは1%以下に収まっており、デフレからは脱却しつつあります。物価は安定しており、国民経済は健全な発展に向かっているように見えます。日銀はその役割を果たしているということになるのでしょう。
今回(2016.1.26)、黒田日銀総裁はマイナス金利を導入する旨発表しました。あえて過激な政策を導入する必要があるのか、今回の決定は法の理念を逸脱しているのではないかとの批判もありうるでしょう。
現在の外部経済環境を見るに、中国を始めとする新興国の経済が予想以上減速しており、世界の株式市場を大きく揺さぶっています。現在のみならず、将来における「国民経済の健全な発展」をも考慮に入れるなら現状維持策は、デフレ経済に逆戻りという大きなリスクを抱え込むことになると思われます。
一般的に政策実施に携わる人々は、法律の則を超えないことに多大な注意を向けます。しかし国民の利益を願うなら、法律の一言一句に拘る前に経済の本質を見据えるべきではないでしょうか。日銀法に米国のFRB連邦準備法(2条A)にあるような「最大雇用の促進」が記載されていないからと言って抜本的デフレ対策を先延ばしするという余裕は日本にないのです。
日銀法上「物価の安定を図る」ことは理念(2条)とされているだけで、目的とされているわけではありません。また雇用の最大化については言及もされていません。法律の枠内で日銀総裁としての業務を全うすれば足りると考えるなら、あえてリスクを負ってまでマイナス金利を導入する必要はないということになります。
しかし、デフレは経済を縮小させ失業率を高める「健全な発展」の対局にあるものです。デフレから脱却出来ないなら持続可能な日本の発展は夢、まぼろしとなるでしょう。デフレ脱却のためできることは何でもする、という姿勢を今回も明確にした黒田日銀総裁には大いなるエールを送りたいと思います。
日本銀行法
(目的)
第一条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。
2 日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。
(通貨及び金融の調節の理念)
第二条 日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。
Federal Reserve Act
Section 2A. Monetary policy objectives
The Board of Governors of the Federal Reserve System and the Federal Open Market Committee shall maintain long run growth of the monetary and credit aggregates commensurate with the economy’s long run potential to increase production, so as to promote effectively the goals of maximum employment, stable prices, and moderate long-term interest rates.
今回(2016.1.26)、黒田日銀総裁はマイナス金利を導入する旨発表しました。あえて過激な政策を導入する必要があるのか、今回の決定は法の理念を逸脱しているのではないかとの批判もありうるでしょう。
現在の外部経済環境を見るに、中国を始めとする新興国の経済が予想以上減速しており、世界の株式市場を大きく揺さぶっています。現在のみならず、将来における「国民経済の健全な発展」をも考慮に入れるなら現状維持策は、デフレ経済に逆戻りという大きなリスクを抱え込むことになると思われます。
一般的に政策実施に携わる人々は、法律の則を超えないことに多大な注意を向けます。しかし国民の利益を願うなら、法律の一言一句に拘る前に経済の本質を見据えるべきではないでしょうか。日銀法に米国のFRB連邦準備法(2条A)にあるような「最大雇用の促進」が記載されていないからと言って抜本的デフレ対策を先延ばしするという余裕は日本にないのです。
日銀法上「物価の安定を図る」ことは理念(2条)とされているだけで、目的とされているわけではありません。また雇用の最大化については言及もされていません。法律の枠内で日銀総裁としての業務を全うすれば足りると考えるなら、あえてリスクを負ってまでマイナス金利を導入する必要はないということになります。
しかし、デフレは経済を縮小させ失業率を高める「健全な発展」の対局にあるものです。デフレから脱却出来ないなら持続可能な日本の発展は夢、まぼろしとなるでしょう。デフレ脱却のためできることは何でもする、という姿勢を今回も明確にした黒田日銀総裁には大いなるエールを送りたいと思います。
日本銀行法
(目的)
第一条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。
2 日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。
(通貨及び金融の調節の理念)
第二条 日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。
Federal Reserve Act
Section 2A. Monetary policy objectives
The Board of Governors of the Federal Reserve System and the Federal Open Market Committee shall maintain long run growth of the monetary and credit aggregates commensurate with the economy’s long run potential to increase production, so as to promote effectively the goals of maximum employment, stable prices, and moderate long-term interest rates.
2016.01.15
オイルとショック
オイルショックと今回の逆オイルショックではバレル当たりの価格幅が大きく異なります。
42年前(1973.10)のオイルショック時、OPECが原油価格をいきなり70%(3$→5$)
引き上げ、翌年オイル価格はさらに2倍(5$→12$弱)に引き上げられました。
その結果原油価格一挙に約4倍(3$→12$)となりましたが、価格幅は9$に過ぎません。
今回の所謂逆オイルショックでは原油価格100$超→36$、下落幅は70$を超えており
上昇幅と下落幅の差から見れば、今回はもっと良い影響があって良さそうに思うのですが。
オイルショック時、産業界も個人も右往左往、人々はトイレットペーパーを買いに走り
企業は投資抑制に舵をきりました。前年からの列島改造ブームによる地価、物価の上昇と相俟って
物価は1年で23%も上昇、物価抑制のため政策金利は9%まで上昇、日本経済は戦後初めての
マイナス成長に陥いり、先進国経済はインフレと景気減速の同時進行するスタグフレーション
に見舞われ、戦後の成長経済はズタズタになりました。
今回の原油価格下落は先進国消費者にとって朗報であり、店頭のガソリン価格等に顕著にその
影響が現れています。しかし原油の下落幅から見れば、もっと大きく経済回復に貢献してよい
ハズですが、今のところ先進国経済が劇的に改善したという状況ではありません。
原油下落が前回オイルショックの時ほど実体経済に反映されない理由は、新興国と先進国の相互
依存性にあるのではないかと考えています。
オイルショック以来、産油国には莫大な富が流入しました。地下から絶え間なく湧き出る
オイル。その価格が一挙に膨れ上がったので、産油国にとっては笑いの止まらない状況が
続きました。ドバイに建設されたブルジュ・ハリファは、世界一の高さを誇りオイルマネー
の富の象徴のような存在となっています。一方、オイル消費国たる先進国にとっては富の
流出となります。オイルによる富の流れは先進国から産油国へというほぼ一方的なものでした。
今回の逆オイルショックを富の流れという観点で 見てみると、産油国→先進国という一方的な
流れとはなっていません。産油国の損失は先進国の損失でもあるという双方向性が今回の特徴
です。先進国の損失とは①オイルに投資してきたファンドの損失②米国シェールオイル企業へ
の出資者損失③産油国を含む新興国に進出している企業の損失など複合的なものです。
オイル価格が急激に上昇した2004~2008までの上げは、余剰マネーが原油という比較的
小さなマーケットに流れ込んだことが最大の理由といわれています。その結果、今回の
価格大幅下落の影響は、原油市場に多額の資金を持ち込んだプレイヤーの損失という形で
まずは商品に投資するファンド等が被り(上記①)、次に②③を理由とした株式市場の
下げが発生しました。また、中東産油国もSWF(国富を投じたファンド)等が国家財政
穴埋め目的でファンドの現金化をせまられ、これまで投資してきた株式市場などでの売却
を余儀なくされました。さらに、株式を始めとするマーケットの価格下落は先進国の実体
経済にも影響がおよび、経済を阻害する方向に働いたと考えられます。
上記③は貿易を通じた相互依存性によるものでもあります。現代社会では先進国と新興国
の関係がより緊密になってきています。先進国で生産された製品は新興国にも多数、輸出
されています。オイルをはじめとする資源を産出する新興国の経済が原油価格下落で低迷
すると、その影響はすぐに先進国の輸出減少となって現れます。
現在の世界は、40年前の産油国対消費国という単純な図式で動く世の中ではなくなりました。
マネーの動きや貿易が、国家を超えて相互に影響を与えながらより深く、より広く、より早く
世界を動かす複雑な社会へと変化を遂げているのです。
42年前(1973.10)のオイルショック時、OPECが原油価格をいきなり70%(3$→5$)
引き上げ、翌年オイル価格はさらに2倍(5$→12$弱)に引き上げられました。
その結果原油価格一挙に約4倍(3$→12$)となりましたが、価格幅は9$に過ぎません。
今回の所謂逆オイルショックでは原油価格100$超→36$、下落幅は70$を超えており
上昇幅と下落幅の差から見れば、今回はもっと良い影響があって良さそうに思うのですが。
オイルショック時、産業界も個人も右往左往、人々はトイレットペーパーを買いに走り
企業は投資抑制に舵をきりました。前年からの列島改造ブームによる地価、物価の上昇と相俟って
物価は1年で23%も上昇、物価抑制のため政策金利は9%まで上昇、日本経済は戦後初めての
マイナス成長に陥いり、先進国経済はインフレと景気減速の同時進行するスタグフレーション
に見舞われ、戦後の成長経済はズタズタになりました。
今回の原油価格下落は先進国消費者にとって朗報であり、店頭のガソリン価格等に顕著にその
影響が現れています。しかし原油の下落幅から見れば、もっと大きく経済回復に貢献してよい
ハズですが、今のところ先進国経済が劇的に改善したという状況ではありません。
原油下落が前回オイルショックの時ほど実体経済に反映されない理由は、新興国と先進国の相互
依存性にあるのではないかと考えています。
オイルショック以来、産油国には莫大な富が流入しました。地下から絶え間なく湧き出る
オイル。その価格が一挙に膨れ上がったので、産油国にとっては笑いの止まらない状況が
続きました。ドバイに建設されたブルジュ・ハリファは、世界一の高さを誇りオイルマネー
の富の象徴のような存在となっています。一方、オイル消費国たる先進国にとっては富の
流出となります。オイルによる富の流れは先進国から産油国へというほぼ一方的なものでした。
今回の逆オイルショックを富の流れという観点で 見てみると、産油国→先進国という一方的な
流れとはなっていません。産油国の損失は先進国の損失でもあるという双方向性が今回の特徴
です。先進国の損失とは①オイルに投資してきたファンドの損失②米国シェールオイル企業へ
の出資者損失③産油国を含む新興国に進出している企業の損失など複合的なものです。
オイル価格が急激に上昇した2004~2008までの上げは、余剰マネーが原油という比較的
小さなマーケットに流れ込んだことが最大の理由といわれています。その結果、今回の
価格大幅下落の影響は、原油市場に多額の資金を持ち込んだプレイヤーの損失という形で
まずは商品に投資するファンド等が被り(上記①)、次に②③を理由とした株式市場の
下げが発生しました。また、中東産油国もSWF(国富を投じたファンド)等が国家財政
穴埋め目的でファンドの現金化をせまられ、これまで投資してきた株式市場などでの売却
を余儀なくされました。さらに、株式を始めとするマーケットの価格下落は先進国の実体
経済にも影響がおよび、経済を阻害する方向に働いたと考えられます。
上記③は貿易を通じた相互依存性によるものでもあります。現代社会では先進国と新興国
の関係がより緊密になってきています。先進国で生産された製品は新興国にも多数、輸出
されています。オイルをはじめとする資源を産出する新興国の経済が原油価格下落で低迷
すると、その影響はすぐに先進国の輸出減少となって現れます。
現在の世界は、40年前の産油国対消費国という単純な図式で動く世の中ではなくなりました。
マネーの動きや貿易が、国家を超えて相互に影響を与えながらより深く、より広く、より早く
世界を動かす複雑な社会へと変化を遂げているのです。
2015.11.01
くいの残らないマンション販売法
下請け業者のくい打ち工事データ改ざんにより、くいの一部が地盤に届いていなかったことが明らかとなり、マンション販売業者は自社負担で住人に対して保障を提示し始めたことが報道されています。新聞紙上ではデータ改ざんが起きた原因として2つのポイントが指摘されました。(2015.10.25日経)
1.工期に厳格なマンション業界の体質。施工の現場がどんなに苦しい事態に陥っても
販売会社は工期の見直しに応じてくれない。完成前に売り始める「青田売り」が
基本で引き渡しは転勤、入学を控えた3,9月に集中しがち。仮に予定日までに工事
が終わらないとクレームが発生する。
2.利益確保には工期を短くして資金回収を早めることが腕の見せ所となる事業構造。
用地取得などの資金を借入でまかなうので、金利負担増加や資金ショートを避ける
ためにも工期を短くして資金回収を早めないと、利益が圧迫される。
構造的な問題は2.の方により多くあると思われます。
どのような解決方法が考えられるでしょうか。
日本の慣行では購入者は代金の殆どを完成時に支払って引き渡しを受けることになっているので、完成するまで業者には現金が入ってきません。マンションの販売から完成までには相当の期間がかかりますが、販売業者にはこの期間自己資金か借入で耐えなければならないということになります。また資材急騰や労働力不足などにより完成遅延が見込まれそうな場合、そのリスク(費用負担)は全て業者が負うことになるでしょう。
海外では異なった販売慣行が実施されているのが散見されます。売買契約を締結した購入者は何回かに分けて支払うというものです。購入者は最初に頭金を支払いますが、その後は工事の進捗度に応じて資金を業者に支払ってゆくのです。
例えば土台が完成した段階で10%、フレームワークができた段階で次の15%、壁が立ち上がり窓枠や扉枠の設置段階で追加10%、等と支払を分割して行い部屋が完成して入居できるようになったら最後の何パーセントかを支払って引き渡しを受ける。通常8回くらいに分けて支払うという形が多いようです。
この方法の場合、くいの長さ不足のような問題が発生したら土台の完成が遅れるので購入者は問題の所在を知ることになるでしょう。販売者は土台完成延期という短期間の金利負担や資材再調達等の負担は発生しますが問題を隠してでも工事を続行する誘因は生まれにくいでしょう。
業界の慣行や法律が問題の本質だとすれば、同じような事例は他にもある可能性が
あります。今後再び似たような事例が出てこないという保証もありません。
多くの人にとって一生の買い物となる住居であればなおのこと、今回の事例は深堀り
して対策を講じる必要があると思います。
1.工期に厳格なマンション業界の体質。施工の現場がどんなに苦しい事態に陥っても
販売会社は工期の見直しに応じてくれない。完成前に売り始める「青田売り」が
基本で引き渡しは転勤、入学を控えた3,9月に集中しがち。仮に予定日までに工事
が終わらないとクレームが発生する。
2.利益確保には工期を短くして資金回収を早めることが腕の見せ所となる事業構造。
用地取得などの資金を借入でまかなうので、金利負担増加や資金ショートを避ける
ためにも工期を短くして資金回収を早めないと、利益が圧迫される。
構造的な問題は2.の方により多くあると思われます。
どのような解決方法が考えられるでしょうか。
日本の慣行では購入者は代金の殆どを完成時に支払って引き渡しを受けることになっているので、完成するまで業者には現金が入ってきません。マンションの販売から完成までには相当の期間がかかりますが、販売業者にはこの期間自己資金か借入で耐えなければならないということになります。また資材急騰や労働力不足などにより完成遅延が見込まれそうな場合、そのリスク(費用負担)は全て業者が負うことになるでしょう。
海外では異なった販売慣行が実施されているのが散見されます。売買契約を締結した購入者は何回かに分けて支払うというものです。購入者は最初に頭金を支払いますが、その後は工事の進捗度に応じて資金を業者に支払ってゆくのです。
例えば土台が完成した段階で10%、フレームワークができた段階で次の15%、壁が立ち上がり窓枠や扉枠の設置段階で追加10%、等と支払を分割して行い部屋が完成して入居できるようになったら最後の何パーセントかを支払って引き渡しを受ける。通常8回くらいに分けて支払うという形が多いようです。
この方法の場合、くいの長さ不足のような問題が発生したら土台の完成が遅れるので購入者は問題の所在を知ることになるでしょう。販売者は土台完成延期という短期間の金利負担や資材再調達等の負担は発生しますが問題を隠してでも工事を続行する誘因は生まれにくいでしょう。
業界の慣行や法律が問題の本質だとすれば、同じような事例は他にもある可能性が
あります。今後再び似たような事例が出てこないという保証もありません。
多くの人にとって一生の買い物となる住居であればなおのこと、今回の事例は深堀り
して対策を講じる必要があると思います。
2015.09.14
異常な8月
世界中の株式マーケットが乱高下を繰り返し、資源も為替も激しく変動した8月。新聞には「リーマンショック以来の」という表現が頻出していました。一体8月に何が起きたというのでしょうか。
世界のマーケットが大きく変動することはある程度予測されていました。9月には米国が金利を上げる可能性が高いとのメッセージをFRBが送っていたからです。米国が金利を上げれば、世界中に溢れていたmoneyが流出することを意味するので、資産価格下落をもたらします。
また米ドル上昇、新興国通貨下落も予想されていました。
ここまでは、予測の範囲内であり世界はこうした事態に身構えていたはずです。しかし米国経済は好調であり利上げできる環境が整ったという判断の下、政策転換が行われるのであれば多少の変動は吸収出来るであろうとの判断があったということでしょう。しかしこれはその他の状況に変更がなければという前提の話です。
混乱の発端は、中国の実体経済が思いのほか悪いというメッセージが突然発せられたことです。通貨元の突然の切り下げ、金利と預金準備率の同時引き下げ等これまでの慣例を破った手段が次々に講じられるにおよび、世界経済の上昇というトレンドは変調をきたしているという恐れが世界を覆いました。結局7年前のリーマンショックから世界はまだ、立ち直れていないというショックだったと思います。
7年前、金融が凍りついた世界に対処するため米国は金利引き下げ、さらには0金利下での量的緩和策を取り、その後3回にわたるQE(量的金融緩和)により7年間で4兆ドルものドル拠出により世界のリスク市場を支えました。当時既にGDP第2位の地位にあった中国は、財政出動によって経済の浮揚を実現させたということになっていました。
7年後の現在、米国はようやく金利引き上げという回復への入り口に立ったのですが、中国の財政出動は経済成長を必ずしも後押ししない形で行われていた為、不動産や株のバブルを産み、時を同じくしてバブル崩壊に直面したということになるのではないでしょうか。
日本の例を見るまでもなく、バブル崩壊による逆資産効果は長期に亘るデフレ傾向をもたらします。高い経済成長を標榜していた中国が実は停滞状況に陥っているとすると、世界経済の回復は遠ざかってしまったということになります。この8月はそうした実体が一挙に噴出した月だったのかもしれません。
世界のマーケットが大きく変動することはある程度予測されていました。9月には米国が金利を上げる可能性が高いとのメッセージをFRBが送っていたからです。米国が金利を上げれば、世界中に溢れていたmoneyが流出することを意味するので、資産価格下落をもたらします。
また米ドル上昇、新興国通貨下落も予想されていました。
ここまでは、予測の範囲内であり世界はこうした事態に身構えていたはずです。しかし米国経済は好調であり利上げできる環境が整ったという判断の下、政策転換が行われるのであれば多少の変動は吸収出来るであろうとの判断があったということでしょう。しかしこれはその他の状況に変更がなければという前提の話です。
混乱の発端は、中国の実体経済が思いのほか悪いというメッセージが突然発せられたことです。通貨元の突然の切り下げ、金利と預金準備率の同時引き下げ等これまでの慣例を破った手段が次々に講じられるにおよび、世界経済の上昇というトレンドは変調をきたしているという恐れが世界を覆いました。結局7年前のリーマンショックから世界はまだ、立ち直れていないというショックだったと思います。
7年前、金融が凍りついた世界に対処するため米国は金利引き下げ、さらには0金利下での量的緩和策を取り、その後3回にわたるQE(量的金融緩和)により7年間で4兆ドルものドル拠出により世界のリスク市場を支えました。当時既にGDP第2位の地位にあった中国は、財政出動によって経済の浮揚を実現させたということになっていました。
7年後の現在、米国はようやく金利引き上げという回復への入り口に立ったのですが、中国の財政出動は経済成長を必ずしも後押ししない形で行われていた為、不動産や株のバブルを産み、時を同じくしてバブル崩壊に直面したということになるのではないでしょうか。
日本の例を見るまでもなく、バブル崩壊による逆資産効果は長期に亘るデフレ傾向をもたらします。高い経済成長を標榜していた中国が実は停滞状況に陥っているとすると、世界経済の回復は遠ざかってしまったということになります。この8月はそうした実体が一挙に噴出した月だったのかもしれません。
2015.07.29
ROEの落とし穴
企業の収益性を評価する代表的指標としてROEが頻繁に取り上げられています。ROEは株主資本を使ってどの位の利益をあげたのかを示す値なので、この値を高めることが重要であることに異論はありません。
ただ言及されることは少ないのですが、ROEの落とし穴ともいうべき注意すべきポイントがあります。すなわち、借入金利がROAより高い場合(ROA<i)ROEは下落するということです。(下記公式参照。)
ROE= [ROA+(ROA-i)x D/E ]x(1-T)
ROA: 総資産を使ってどのくらい事業利益(営業利益+金融収益) をあげているかを示す指標
D/E: 負債に対する自己資本の比率
T:法人税率
日本は15年以上にもわたってデフレが続いていたので、現在のところ借入金利は極めて低いままです。ところが今やデフレ脱却は現実のものとなりつつあり、今後インフレの世界に突入してゆくはずなので、借入金利も当然上昇となります。それでは借入金利が1%→3%に上昇した場合のどのような影響があるかシミュレーションしてみます。
ROAは2%,D/Eは10倍とすると
金利1%: ROE=2+(2-1)x10=12%
金利」3%: ROE=2+(2-3)x10=-8%
借入金利が1%→3%上昇しただけで、企業価値ROEは12%のプラスから8%のマイナス へと大幅に転落します。従って企業価値を毀損しないためには、ROAが常に金利よりも高くなるような経営をしてゆく必要があるのです。金利は一度上昇を始めると経営努力でどうにかできるという類のものではありません。金利の低い今こそが事業利益率を高めることを目標とした経営を始めるタイミングです。
ただ言及されることは少ないのですが、ROEの落とし穴ともいうべき注意すべきポイントがあります。すなわち、借入金利がROAより高い場合(ROA<i)ROEは下落するということです。(下記公式参照。)
ROE= [ROA+(ROA-i)x D/E ]x(1-T)
ROA: 総資産を使ってどのくらい事業利益(営業利益+金融収益) をあげているかを示す指標
D/E: 負債に対する自己資本の比率
T:法人税率
日本は15年以上にもわたってデフレが続いていたので、現在のところ借入金利は極めて低いままです。ところが今やデフレ脱却は現実のものとなりつつあり、今後インフレの世界に突入してゆくはずなので、借入金利も当然上昇となります。それでは借入金利が1%→3%に上昇した場合のどのような影響があるかシミュレーションしてみます。
ROAは2%,D/Eは10倍とすると
金利1%: ROE=2+(2-1)x10=12%
金利」3%: ROE=2+(2-3)x10=-8%
借入金利が1%→3%上昇しただけで、企業価値ROEは12%のプラスから8%のマイナス へと大幅に転落します。従って企業価値を毀損しないためには、ROAが常に金利よりも高くなるような経営をしてゆく必要があるのです。金利は一度上昇を始めると経営努力でどうにかできるという類のものではありません。金利の低い今こそが事業利益率を高めることを目標とした経営を始めるタイミングです。
2015.06.12
ヴェネツィア 富と権力
世界の歴史に多大な影響を与えた地域はどのように生まれてきたのか、そこにはいくつかの共通項があるようです。現代ではアメリカのシリコンバレーが代表的ですが、中世ではルネッサンス文化の開花に大きく貢献したイタリアの諸都市、中でもヴェネツィアはその代表ともいえるでしょう。ルネッサンス文化を支えた富と権力はどのように獲得されてきたのでしょうか。
結論から先に言うと、ヒト・モノ・カネ・風土が生んだというのが私の仮説です。最近読んだ本「バランスシートで読み解く世界経済史」(ジェーン・グリーソン・ホワイト)にヒントがあったので、この本を参考文献として考えてみます。
15世紀中ごろ、十字軍による聖地エルサレムの奪還が叫ばれ騎士団は聖地をめざしましたが、その通リ道であったヴェネツィアは中世交易の中心となっていきました。交易はヒトとモノの流れを意味します。アドリア海に面した港という立地も海上交易の拠点としてヒト、モノを引き付けたことでしょう。
中世のヨーロッパは宗教の影響が強く教会は融資の際、固定金利を付けることを禁止していました。「ヴェネツィアに誕生したダティーニは為替手形により教会の目をかいくぐり、国際的マーチャントバンカーとして貿易と信用のネットワークを構築。それにより産み出された巨大な富が建築、美術、学問に投じられた。」かくしてカネの面からもヴェネツィアはルネッサンスの資金供給源となったのです。
風土の面からヴェネツィアに富と権力をもたらしたのは実利主義といえるでしょう。「ヴェネツィアは中世ヨーロッパにおいて、パリ、ナポリに次ぐ3番目の規模を誇っていた。ヴェネツィアは他の都市国家と違い、教会の支配よりも商業を優先、異教徒オスマントルコとも講和条約を結んで争いに巻き込まれることなくビジネスを続けた」のです。
この本の副題「double entry」は複式簿記のことですが、ルカ・パチョーリというルネッサンス時代の修道士、数学者によるもので、パチョーリはレオナルド・ダビンチに数学を教えた人でもあったようです。複式簿記は現代でも世界中のビジネス実務で使われていますが、ビジネスの結果生み出される成果を記録、把握する為の基本的インフラです。パチョーリというヒトがヴェネツィアに誕生したことがヴェネツィアの経済的発展を後押ししたのは間違いありません。
十字軍遠征という宗教的背景を利用し交易を行う一方、教会の権威や支配には距離を置くというしたたかな戦略。これにより獲得したモノやカネ、それを背後から支えたヒトや風土によりヴェネツィアは栄え、ルネッサンスは花開きました。ヒト・モノ・カネ・風土はビジネス、投資を成功に導く本質的要素であることを示しています。
結論から先に言うと、ヒト・モノ・カネ・風土が生んだというのが私の仮説です。最近読んだ本「バランスシートで読み解く世界経済史」(ジェーン・グリーソン・ホワイト)にヒントがあったので、この本を参考文献として考えてみます。
15世紀中ごろ、十字軍による聖地エルサレムの奪還が叫ばれ騎士団は聖地をめざしましたが、その通リ道であったヴェネツィアは中世交易の中心となっていきました。交易はヒトとモノの流れを意味します。アドリア海に面した港という立地も海上交易の拠点としてヒト、モノを引き付けたことでしょう。
中世のヨーロッパは宗教の影響が強く教会は融資の際、固定金利を付けることを禁止していました。「ヴェネツィアに誕生したダティーニは為替手形により教会の目をかいくぐり、国際的マーチャントバンカーとして貿易と信用のネットワークを構築。それにより産み出された巨大な富が建築、美術、学問に投じられた。」かくしてカネの面からもヴェネツィアはルネッサンスの資金供給源となったのです。
風土の面からヴェネツィアに富と権力をもたらしたのは実利主義といえるでしょう。「ヴェネツィアは中世ヨーロッパにおいて、パリ、ナポリに次ぐ3番目の規模を誇っていた。ヴェネツィアは他の都市国家と違い、教会の支配よりも商業を優先、異教徒オスマントルコとも講和条約を結んで争いに巻き込まれることなくビジネスを続けた」のです。
この本の副題「double entry」は複式簿記のことですが、ルカ・パチョーリというルネッサンス時代の修道士、数学者によるもので、パチョーリはレオナルド・ダビンチに数学を教えた人でもあったようです。複式簿記は現代でも世界中のビジネス実務で使われていますが、ビジネスの結果生み出される成果を記録、把握する為の基本的インフラです。パチョーリというヒトがヴェネツィアに誕生したことがヴェネツィアの経済的発展を後押ししたのは間違いありません。
十字軍遠征という宗教的背景を利用し交易を行う一方、教会の権威や支配には距離を置くというしたたかな戦略。これにより獲得したモノやカネ、それを背後から支えたヒトや風土によりヴェネツィアは栄え、ルネッサンスは花開きました。ヒト・モノ・カネ・風土はビジネス、投資を成功に導く本質的要素であることを示しています。
2015.05.05
価格の無常について
「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」鴨長明の方丈記の有名な一節で、移りゆくものの無常をうたったものとされています。
話はいささか世俗的になりますが、株価も時々刻々と値を変えて株価ボードで点滅を続け、「とどまりたるためしなし」を実感させられます。株価というものはよどみに浮かぶ泡沫のようなものなのでしょうか。
価格が絶え間なく変わるのは市場で売りと買いがぶつかって、値付けが行われているからですが、個人、機関投資家、金融機関、海外投資家など市場への参加者の売買基準は異なります。
株価は企業の価値なのでその本質的価値に収斂してゆくはずですが、それでは企業の本質的価値とは何でしょう。色々な説がありますがここでは保有資産+稼ぐ力と考えておきます。前者の保有資産はバランスシートに出ているので誰が見ても同じ数字になります。
問題は後者の稼ぐ力。会社は経済活動をすることで利益を得ているので、長期的に利益を維持、成長させられる能力が稼ぐ力と言えるでしょう。市場参加者は企業の稼ぐ力に着目して売り買いの決断をしているはずですが、企業の稼ぐ能力判断は投資家によって異なるというのが実態です。株価が変動する1つ目の理由です。
株価を動かすもう一つの要因は需給関係です。例えば法人投資家なら決算対策の売買があるでしょうし、ファンドならファンド出資者の意向により左右されます。リーマンショックでファンド出資者からの解約が相次いだときには、返済資金確保の必要から本質的価値の高い銘柄から売却して返済資金を確保するということは実際に行われました。たとえ本質的価値が高い銘柄であっても売られざるを得ないという状況は往々にして起こります。従って、短期的需給関係による価格は株価の本質的価値とは無関係です。
市場で勝ち組となる秘訣は、企業の本質価値にこだわり続け需給関係による値動きに無頓着でいることだと思います。株価が下落したとき、株価ボードに表示されている価格が本質的価値より大幅に低いと判断できれば、思い切って買えばよいのです。いずれ株価は本質価値に収斂してくるので利益は自ずと買い手のものとなります。
人は市場の大幅な下げに直面した時恐怖にかられます。損失が拡大するのは嫌なので恐怖から逃れようという心理が働き、売却に走るのでしょう。しかしそのような心理に抵抗することが出来なければ勝ち組になることは難しい。そして下落の恐怖感から自由でいられるポイントは、保有する銘柄が市場で表示されている価格以上の本質価値があるという確信です。
価値と価格は必ずしも同じではありません。日常の買い物でも安くてお得とか、割高という判断をしているわけですが、この場合比較しているのは同じような他の製品であったり、これまで商品についていた値札だったりします。スーパーで大根を買うならこれでよいでしょうが、投資の世界に同じ感覚を持ち込むなら決して報われることはありません。この世界ではむしろ価格のウラをかくくらいがちょうど良い。そしてこのような行動を担保するのが「本質価値」判断なのです。
話はいささか世俗的になりますが、株価も時々刻々と値を変えて株価ボードで点滅を続け、「とどまりたるためしなし」を実感させられます。株価というものはよどみに浮かぶ泡沫のようなものなのでしょうか。
価格が絶え間なく変わるのは市場で売りと買いがぶつかって、値付けが行われているからですが、個人、機関投資家、金融機関、海外投資家など市場への参加者の売買基準は異なります。
株価は企業の価値なのでその本質的価値に収斂してゆくはずですが、それでは企業の本質的価値とは何でしょう。色々な説がありますがここでは保有資産+稼ぐ力と考えておきます。前者の保有資産はバランスシートに出ているので誰が見ても同じ数字になります。
問題は後者の稼ぐ力。会社は経済活動をすることで利益を得ているので、長期的に利益を維持、成長させられる能力が稼ぐ力と言えるでしょう。市場参加者は企業の稼ぐ力に着目して売り買いの決断をしているはずですが、企業の稼ぐ能力判断は投資家によって異なるというのが実態です。株価が変動する1つ目の理由です。
株価を動かすもう一つの要因は需給関係です。例えば法人投資家なら決算対策の売買があるでしょうし、ファンドならファンド出資者の意向により左右されます。リーマンショックでファンド出資者からの解約が相次いだときには、返済資金確保の必要から本質的価値の高い銘柄から売却して返済資金を確保するということは実際に行われました。たとえ本質的価値が高い銘柄であっても売られざるを得ないという状況は往々にして起こります。従って、短期的需給関係による価格は株価の本質的価値とは無関係です。
市場で勝ち組となる秘訣は、企業の本質価値にこだわり続け需給関係による値動きに無頓着でいることだと思います。株価が下落したとき、株価ボードに表示されている価格が本質的価値より大幅に低いと判断できれば、思い切って買えばよいのです。いずれ株価は本質価値に収斂してくるので利益は自ずと買い手のものとなります。
人は市場の大幅な下げに直面した時恐怖にかられます。損失が拡大するのは嫌なので恐怖から逃れようという心理が働き、売却に走るのでしょう。しかしそのような心理に抵抗することが出来なければ勝ち組になることは難しい。そして下落の恐怖感から自由でいられるポイントは、保有する銘柄が市場で表示されている価格以上の本質価値があるという確信です。
価値と価格は必ずしも同じではありません。日常の買い物でも安くてお得とか、割高という判断をしているわけですが、この場合比較しているのは同じような他の製品であったり、これまで商品についていた値札だったりします。スーパーで大根を買うならこれでよいでしょうが、投資の世界に同じ感覚を持ち込むなら決して報われることはありません。この世界ではむしろ価格のウラをかくくらいがちょうど良い。そしてこのような行動を担保するのが「本質価値」判断なのです。
2015.03.29
TESLAに乗ってみた!!
南青山に電気自動車(EV)Teslaのショールームがあります。展示されている車のボンネットの中は空洞、エンジンがありません。シャーシにモーターが取り付けてありこれが車輪を回転させるのです。エンジンがないので車重は軽いということはなく、普通の車と変わらないそうです。モーターを駆動させるリチウム・イオン・バッテリー・パックがシャーシいっぱいに敷き詰めてあるからです。
この車、馬力もスピードもスーパーカー並みということで早速試乗させてもらいました。アクセルを踏むと音もなく動き出しますが、ちょっとアクセルを踏むと同乗者はいっせいにのけぞります。セダンタイプでありながら5秒で100kmまで加速するという、まさにスーパーカー。しかも東京から名古屋まで走ってもかかる電気代は500円程度という驚きのパフォーマンスです。日本国内には既に1000以上のバッテリー充電装置が設置されており一回の充電で500km弱の走行可能、家庭のコンセントからも充電できるそうです。
ダッシュボードにはメーターの類は必要最小限。その代りハンドルの左横の既存車ならステレオや変速ギアがあるあたりにかけて大型のスクリーンがついており、これがネットにつながっています。シリコンバレー(本社:カリフォルニア州パロアルト)で生み出された車だけあってネットと車の融合を実現しています。
蓄電池や水素を燃料として走る車がガソリン車に取って代わる日はそれほど先の話ではないような気がします。都内で深呼吸をしても排気ガスにむせ返ることもなく、車の騒音に悩まされることのないエコ・フレンドリーな都会に変わってゆくかもしれません。
一方、ITや家電等様々な業界からの参入によって、自動車や部品メーカーは厳しい淘汰の時代に突入して行くことになるでしょう。Teslaは環境や業界を巻き込みながら「変化」という荒野を駆け抜けて行く象徴なのかもしれません。
この車、馬力もスピードもスーパーカー並みということで早速試乗させてもらいました。アクセルを踏むと音もなく動き出しますが、ちょっとアクセルを踏むと同乗者はいっせいにのけぞります。セダンタイプでありながら5秒で100kmまで加速するという、まさにスーパーカー。しかも東京から名古屋まで走ってもかかる電気代は500円程度という驚きのパフォーマンスです。日本国内には既に1000以上のバッテリー充電装置が設置されており一回の充電で500km弱の走行可能、家庭のコンセントからも充電できるそうです。
ダッシュボードにはメーターの類は必要最小限。その代りハンドルの左横の既存車ならステレオや変速ギアがあるあたりにかけて大型のスクリーンがついており、これがネットにつながっています。シリコンバレー(本社:カリフォルニア州パロアルト)で生み出された車だけあってネットと車の融合を実現しています。
蓄電池や水素を燃料として走る車がガソリン車に取って代わる日はそれほど先の話ではないような気がします。都内で深呼吸をしても排気ガスにむせ返ることもなく、車の騒音に悩まされることのないエコ・フレンドリーな都会に変わってゆくかもしれません。
一方、ITや家電等様々な業界からの参入によって、自動車や部品メーカーは厳しい淘汰の時代に突入して行くことになるでしょう。Teslaは環境や業界を巻き込みながら「変化」という荒野を駆け抜けて行く象徴なのかもしれません。
2015.03.02
ピケティーの不等式
フランスの経済学者トマ・ピケティーは格差問題についてR>Gの不等式を使って説明しました。簡単に言うと、株式や債券等に投資をして得られる収益率Rは経済成長率Gよりも常に大きい。従って多くの資産を持つ人はますます富み、そうでない人との格差は広がる一方であるということです。
経済格差は様々な問題を引き起こしますから、是正されねばならないでしょう。問題はその方法です。ピケティーは税制変更による是正を提案していますが、実現は簡単ではありません。一方、上記不等式は「投資をしないことが格差を拡大する」と見ることも出来ます。投資の収益率が賃金の伸びより高いなら、会社から給料を得ているだけの人よりも、その一部を投資に回している人のほうが有利、ということをR>Gは示唆しているからです。
日本の現状は国民金融資産約1654兆円の52%以上が貯蓄に回っているので日本人は投資による収益率Rの恩恵を十分に享受しているとは言えません。日本人同士で比較すると、貯蓄だけの人と投資もしている人の格差は益々開いてゆくことを意味しています。
また、この貯蓄比率が13%である米国と比較すると家計資産の日米格差も益々拡大してゆくということになります。より直接的に投資収益率Rを表す、株、債券、投信への投資比率 で比較すると日本16%に対して米国51%となっています。米国に於いては、報酬における収入格差も大きいので投資にまわせる資産の大きさの差がそのまま格差拡大につながってしまい、そこは問題ですが、家計レベルでみると投資果実を半数以上の51%が享受しています。
日本においては、収入格差が米国ほど大きくはないのですが、投資収益を得ている家計が16%と極めて少ないことに問題があります。ピケティーの不等式が正しいなら、今後日本において投資が増えない限り個人間、国家間の格差は拡大してゆくことになるでしょう。投資をすることが格差是正につながるなら問題の解決法はより身近にある、ということになるのではないでしょうか。
*上記、国民金融資産は、資金循環表「家計の資産合計」の数値(日銀統計局2014・12)による。
経済格差は様々な問題を引き起こしますから、是正されねばならないでしょう。問題はその方法です。ピケティーは税制変更による是正を提案していますが、実現は簡単ではありません。一方、上記不等式は「投資をしないことが格差を拡大する」と見ることも出来ます。投資の収益率が賃金の伸びより高いなら、会社から給料を得ているだけの人よりも、その一部を投資に回している人のほうが有利、ということをR>Gは示唆しているからです。
日本の現状は国民金融資産約1654兆円の52%以上が貯蓄に回っているので日本人は投資による収益率Rの恩恵を十分に享受しているとは言えません。日本人同士で比較すると、貯蓄だけの人と投資もしている人の格差は益々開いてゆくことを意味しています。
また、この貯蓄比率が13%である米国と比較すると家計資産の日米格差も益々拡大してゆくということになります。より直接的に投資収益率Rを表す、株、債券、投信への投資比率 で比較すると日本16%に対して米国51%となっています。米国に於いては、報酬における収入格差も大きいので投資にまわせる資産の大きさの差がそのまま格差拡大につながってしまい、そこは問題ですが、家計レベルでみると投資果実を半数以上の51%が享受しています。
日本においては、収入格差が米国ほど大きくはないのですが、投資収益を得ている家計が16%と極めて少ないことに問題があります。ピケティーの不等式が正しいなら、今後日本において投資が増えない限り個人間、国家間の格差は拡大してゆくことになるでしょう。投資をすることが格差是正につながるなら問題の解決法はより身近にある、ということになるのではないでしょうか。
*上記、国民金融資産は、資金循環表「家計の資産合計」の数値(日銀統計局2014・12)による。
2015.02.09
潮目変化の読み方
現状の日経平均株価は2年前と比較すると約2倍(17,500/8,700=2.01)、ドル円の為替水準は2年前の約1.5倍(118/80=1.475)となっています。2年前に日本株やドルに投資をしていれば大きな利益を得ていたことになりますが、皆さんいかがだったでしょうか。
成果の良否は2年前に株やドルが上がると予測できたか否か、という1点にかかっていました。今、株価や為替がどうなっているかはマーケットを見れば誰にでもわかることですが、2年前にチャンスと判断して実際に投資行動を起こした人はそれほど多くはなかったようです。
変化に気付いていち早く行動に移し利益を上げるのは、残念ながらヘッジファンドを始めとする海外勢が中心となっています。彼等は2年前に潮目が変わったことを確信したのです。2年前彼等が着目したのは、第二次安倍内閣が3本の矢をもって経済政策を推し進めるという発表でした。
当時日本は、15年以上に亘るデフレ経済に慣れきっており、政策が変わったくらいで日本経済が好転してゆくと考えた人は少数派だったようです。アベノミクス政策発表直後のセミナー等で、日経平均は今後上昇すると思うか否かと尋ねてみたことがあります。上昇すると答えた人は圧倒的少数でした。
ではナゼ海外勢は積極的に日本買いに転じたのでしょうか。彼等はこの政策によって日本の経済成長が実現でき、デフレ経済から脱却できると考えたのだと思います。アベノミクスの本質はGDPの構成要素(消費、財政投資、設備投資、貿易収支)に3本の矢(金融政策、財政政策、成長政策)を打ち込むことによってGDPを上昇させることにあるはずです。日本経済が成長すれば、日経平均は上昇するというロジックで日本株に大量の買いを入れてきたということでしょう。
日本に住み日本人の頭で考えていると、往々にして大きな潮目の変化を発見し損なうことがあります。人間は過去の延長線上でモノを見る習性があり、そうすると潮目は見えません。変化に気付いて利益を獲得するためには外国人の目を持って外から日本を見るということが有効です。
成果の良否は2年前に株やドルが上がると予測できたか否か、という1点にかかっていました。今、株価や為替がどうなっているかはマーケットを見れば誰にでもわかることですが、2年前にチャンスと判断して実際に投資行動を起こした人はそれほど多くはなかったようです。
変化に気付いていち早く行動に移し利益を上げるのは、残念ながらヘッジファンドを始めとする海外勢が中心となっています。彼等は2年前に潮目が変わったことを確信したのです。2年前彼等が着目したのは、第二次安倍内閣が3本の矢をもって経済政策を推し進めるという発表でした。
当時日本は、15年以上に亘るデフレ経済に慣れきっており、政策が変わったくらいで日本経済が好転してゆくと考えた人は少数派だったようです。アベノミクス政策発表直後のセミナー等で、日経平均は今後上昇すると思うか否かと尋ねてみたことがあります。上昇すると答えた人は圧倒的少数でした。
ではナゼ海外勢は積極的に日本買いに転じたのでしょうか。彼等はこの政策によって日本の経済成長が実現でき、デフレ経済から脱却できると考えたのだと思います。アベノミクスの本質はGDPの構成要素(消費、財政投資、設備投資、貿易収支)に3本の矢(金融政策、財政政策、成長政策)を打ち込むことによってGDPを上昇させることにあるはずです。日本経済が成長すれば、日経平均は上昇するというロジックで日本株に大量の買いを入れてきたということでしょう。
日本に住み日本人の頭で考えていると、往々にして大きな潮目の変化を発見し損なうことがあります。人間は過去の延長線上でモノを見る習性があり、そうすると潮目は見えません。変化に気付いて利益を獲得するためには外国人の目を持って外から日本を見るということが有効です。
2015.01.19
カジノ?
カジノに対するイメージを聞いて回ったことがあります。概してお子さんをお持ちの女性は否定的なイメージを持たれているようです。ギャンブル依存症や治安の悪化などを懸念されており、日本にカジノは「よろしくない」ということのようです。どのくらいよろしくないのか、確認のため政府がモデルとしようとしているシンガポールのカジノへ昨年末行ってきました。以下、そのレポートです。
2010年開業したマリーナ・ベイ・サンズ。3棟のホテルの上に船のようなプラットフォームが乗っており舳にあたる部分にはエレベーター(56階)で上ることができます。ここからシンガポール全体が見渡せ360°のパノラマは壮大、一見の価値あり。
このホテルから海方面に向かって広大なショッピング・ゾーン(主に高級ブランド店や飲食店)が伸び、一番海に近い場所のグランドフロアーから下3階に豪華カジノが広がっています。入口は3つ。内2つは外国人用で、入るためにはパスポートが必要。もう1つはシンガポール人及び永住者用で有料。入口が違うのでシンガポール人専用のカジノがあるのかと思ったら、中では一緒でした。
平日の午後2時頃、カジノの中は9割方埋まっておりスロットでは多くの中国系(だと思う)の方々がに遊んでいます。ディラーの居るテーブルも6割位の着席率。モデルのような女性がすたすたと歩いてきてカードゲームに興じたりしていました。ソフトドリンク飲み放題、たばこ吸い放題。少々煙いのを除けば高級な大人の遊び場といった感じです。
マリーナ・ベイ・サンズ、もう一つの特徴は光と噴水、レザー光線、音楽が一体となって織りなされるダイナミックなショー。毎晩8:00と9:30に行われています。大人も子供も一緒に楽しめる大型施設の一角にカジノもある、というイメージでした。スケールの大きなホテル、ショッピングゾーン、ダイナミックなショー、の三位一体には既視感あり、調べてみました。やはり、ここの運営はラスベガス・サンズの手によるものだったのです。[ホテル前の広大な池で噴水が踊るベラッジオやベネチアンホテル等で有名]
カジノ合法化にむけて、議員連盟により提出されたIR法案(統合リゾート推進法)は民間の資金や活力を生かし、国のイメージ向上、海外集客促進などによる経済効果を狙っています。(国民の間にギャンブルを広めよう!という内容ではありません。)日本の成長にとっても大きく貢献できるプロジェクトになると思われます。
IR法案は先の衆議院選挙で廃案となりましたが、今国会への再提出予定と報じられています。成立後1年以内に国による法制上の手当てを義務付けていますので、ギャンブル依存症や治安の悪化、マネーロンダリングなどの対策もしっかりと行われることになるでしょう。
但し、カジノはシンガポールの他マカオや韓国、マレーシア等にも競合がおり、厳しい競争も予測される分野でもあります。日本らしい独創性のあるクールな統合施設を是非実現させてほしいものです。
2010年開業したマリーナ・ベイ・サンズ。3棟のホテルの上に船のようなプラットフォームが乗っており舳にあたる部分にはエレベーター(56階)で上ることができます。ここからシンガポール全体が見渡せ360°のパノラマは壮大、一見の価値あり。
このホテルから海方面に向かって広大なショッピング・ゾーン(主に高級ブランド店や飲食店)が伸び、一番海に近い場所のグランドフロアーから下3階に豪華カジノが広がっています。入口は3つ。内2つは外国人用で、入るためにはパスポートが必要。もう1つはシンガポール人及び永住者用で有料。入口が違うのでシンガポール人専用のカジノがあるのかと思ったら、中では一緒でした。
平日の午後2時頃、カジノの中は9割方埋まっておりスロットでは多くの中国系(だと思う)の方々がに遊んでいます。ディラーの居るテーブルも6割位の着席率。モデルのような女性がすたすたと歩いてきてカードゲームに興じたりしていました。ソフトドリンク飲み放題、たばこ吸い放題。少々煙いのを除けば高級な大人の遊び場といった感じです。
マリーナ・ベイ・サンズ、もう一つの特徴は光と噴水、レザー光線、音楽が一体となって織りなされるダイナミックなショー。毎晩8:00と9:30に行われています。大人も子供も一緒に楽しめる大型施設の一角にカジノもある、というイメージでした。スケールの大きなホテル、ショッピングゾーン、ダイナミックなショー、の三位一体には既視感あり、調べてみました。やはり、ここの運営はラスベガス・サンズの手によるものだったのです。[ホテル前の広大な池で噴水が踊るベラッジオやベネチアンホテル等で有名]
カジノ合法化にむけて、議員連盟により提出されたIR法案(統合リゾート推進法)は民間の資金や活力を生かし、国のイメージ向上、海外集客促進などによる経済効果を狙っています。(国民の間にギャンブルを広めよう!という内容ではありません。)日本の成長にとっても大きく貢献できるプロジェクトになると思われます。
IR法案は先の衆議院選挙で廃案となりましたが、今国会への再提出予定と報じられています。成立後1年以内に国による法制上の手当てを義務付けていますので、ギャンブル依存症や治安の悪化、マネーロンダリングなどの対策もしっかりと行われることになるでしょう。
但し、カジノはシンガポールの他マカオや韓国、マレーシア等にも競合がおり、厳しい競争も予測される分野でもあります。日本らしい独創性のあるクールな統合施設を是非実現させてほしいものです。